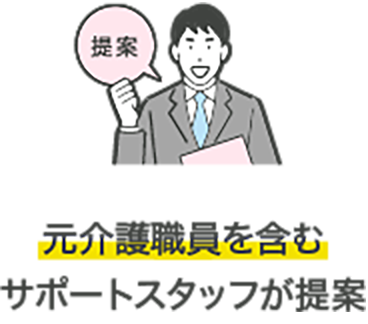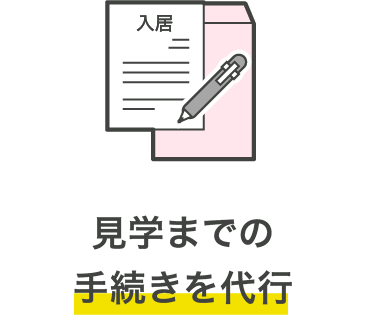介護の場面で聞くことが多くなった「地域包括ケアシステム」という用語ですが、この言葉から中身を連想することが難しく、イメージしづらいと感じている方も多いのではないでしょうか。
この「地域包括ケアシステム」は、今後超高齢化社会を迎える日本において、多くの高齢者の日常生活を支える需要な支援システムです。地域包括ケアシステムの中身を十分に把握することにより、安心した老後の介護生活を過ごすことができるでしょう。
今回は、地域包括ケアシステムの具体的な内容や抱えるメリット・デメリット、様々な課題などを詳しく解説していきます。ぜひ今回の記事に目を通し、地域包括ケアシステムに関する知識を深めていきましょう。
地域包括ケアシステムとは

地域包括ケアシステムとは、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもと、可能な限りこれまで通りの住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体制のことを指します。
現在日本では、他の先進諸国とは比較にならない速度で高齢化が進行しており、超高齢化社会を迎えつつあります。2020年の段階で65歳以上の人口は3,000万人を超えており、割合として国民の4人に1人が65歳の高齢者で構成されているのです。
2042年には65歳以上の方はピークの約3,900万人を迎えると言われています。それ以降も高齢者の人口割合は増加し続けることになり、高齢者に対する支援体制の確立は急務となっているのです。
特に医療や介護の分野での需要は急速に高まっており、団塊の世代が75歳以上となる2025年までには一定の支援体制を整える必要があります。
5つの構成要素
「地域包括ケアシステム」は、大きく分けて5つの要素から構成されています。具体的な要素は以下の通りです。
- 介護
- 医療
- 予防
- 生活支援、福祉サービス
- 住まいと住まい方
この5つの要素が互いに持つ共通項に応じて、さらに大きく3つ分類することができます。
- 住まいと住まい方
- 生活支援・福祉サービス
- 介護・医療・予防
この3つの内容はいずれも十分なケアシステムを構築する上で欠かせない重要要素となっています。それぞれの内容を紹介します。
住まいと住まい方
高齢者が安心して老後生活を営むためには、個人のプライバシーと尊厳が手厚く守られた住環境を確保することが極めて大切になります。
生活の基盤として必要な住まいが整備されており、本人の意思や収入、貯蓄や経済力に沿った適切な住まい方が確保されていることが地域包括ケアシステムの前提と言えるでしょう。
高齢者の尊厳を生涯守るためにも、住まいと住まい方には十分な配慮が求められます。
生活支援・福祉サービス
地域包括ケアシステムには、高齢者の心身の能力の低下や経済的状況、家族関係の変化などがある中でも、引き続き尊厳ある生活が継続できるような生活支援サービスが用意されています。
生活支援の具体的な中身としては、食事の準備や日用品の補助、近隣住民の声かけや見守りなどのインフォーマルな支援まで幅広く含まれています。高齢者の数に合わせて多数の担い手も必要です。
さらに高齢者の尊厳ある生活が守られるように、生活困窮者などには給付金制度や貸付制度などの福祉サービスも提供します。
介護・医療・予防
高齢者ひとりひとりが抱える課題にあわせて「介護・リハビリテーション」「医療・看護」「保健・予防」がそれぞれの専門職によって提供される環境が用意されます。
「介護・リハビリテーション」「医療・看護」「保健・予防」のそれぞれがバラバラに提供されるのではなく、全てが有機的に連携し、一体的に提供することで高齢者の利便性の維持や向上を図っています。
4つの「助」の連携
社会福祉に関しては「自助」「互助」「共助」「公助」の4つの「助」をバランスよく組み合わせて提供されています。今後はさらにそれぞれの助がサービスの質を深め、連携して高齢者を支えるシステム作りが重要となるでしょう。
ここからは、4つの「助」である「自助」「互助」「共助」「公助」のそれぞれの内容について解説していきます。
自助
「自助」とは、基本的に自分のことは自分で行うことを指します。自分で健康に気をつけ自己管理を行い、自費でサービスを受けることも含まれます。
共助
「共助」とは、住民同士支え合うことを意味します。リスクを共有する被保険者の負担で構成される介護保険などの、社会保険制度や介護サービスも含まれます。
互助
相互に支え合いボランティア活動や住民同士の組織活動を行います。医療、年金、介護保険などの制度を利用し支えることも「互助」に含まれますが、費用負担が制度的に裏付けされていない特徴があります。
公助
「公助」とは税による公の負担を指します。具体的には、一般財源による高齢者福祉事業や生活保護、人権擁護・虐待対策生活保護などの社会福祉制度を指します。
少子高齢化の流れが加速していく中で現在の財政状況を合わせて考えると、「共助」や「公助」の大幅な拡充を期待することは難しい現状があります。今後は「自助」や「互助」の果たす役割が大きくなることを意識した制度設計や民間の取り組みが重要になってくるでしょう。
介護施設への入居を検討・施設探しをしている方は、ケアスル介護での相談がおすすめです。
ケアスル介護なら、入居相談員にその場で条件に合った施設を教えてもらうことができます。
「自分に合った施設を選びたい」「予算内に合った施設を選びたい」という方は、ケアスル介護で無料相談をしてみてはいかがでしょうか。
ピッタリの施設を提案します
地域包括ケアシステムのメリット

地域包括ケアシステムのメリットは、大きく分けて以下の4つがあげられます。
- 医療と介護が一体化した継続的なサービス
- 認知症になった後でも自宅で生活ができる
- 地域に新しいサービスが生まれる
- 高齢者の社会参加の応援
地域包括ケアシステムが構築されると、医療と介護の連携サービスを提供できるようになります。高齢者の中には認知症の方も多く、在宅での介護サービスだけでなく医療サービスも必要とされている方がおられます。
医療と介護の手厚い支援が自宅で受けられるのであれば、安心して老後の生活を送ることができるでしょう。
さらに地域包括ケアシステムを基幹とした様々な付随的なサービスが誕生することにより、ここの高齢者の細かなニーズに対応できる環境を整備することができるようになります。
手厚い支援サービスの拡充により、元気な高齢者が増加することが予想されます。積極的に社会参加する高齢者も増えることから、彼らを応援することにもつながるでしょう。
地域包括ケアシステム実現に向けての取り組み

今後多くの地域で地域包括ケアシステムを実現するためには、解決しなければならない課題や問題点が多々あります。それらの課題に取り組みながら適切なプロセスを踏み、地域包括ケアシステムの実現に向けて進んでいく必要があるのです。
ここでは、地域包括ケアシステムを実現するために欠かすことのできない取り組みの中身について解説していきます。
構築時の3つのプロセス
地域包括ケアシステムの構築は日本全国一律に行われるわけではなく、県や市町村などの各自治体が、自らが作成する介護保険事業計画に沿って行われています。
しかし国は完全に地方の自治体に丸投げしているわけでなく、それぞれの自治体が理想的な地域包括ケアシステムを構築するために、以下の3つのプロセスを経る必要があることを提言しているのです。
- 地域の課題を理解し、社会資源を見つける
- 対応策を考える
- 具体策の実行
以下、この3つのプロセスについてそれぞれ解説していきます。
地域の課題を理解し、社会資源を見つける
まずはその地域で暮らす多くの高齢者がどのような課題を抱えているのかを把握することが重要です。積極的に住民会議やセミナー、パブリックコメントなどを実施してしっかりと高齢者の声に耳を向け、課題を把握していきます。
関連施設との情報共有も行い、課題解決につながる社会資源を見つけることができれば、自ずと解決策につながるサービスを考えるようになるでしょう。
対応策を考える
高齢者の抱える課題は共通項も多いですが、細かく見ればそれぞれの地域によって異なります。課題を見つけた後は地域に住む関係者がそれらの課題を共有し、課題を解決するための効果的な対応策を考える過程が必要になるでしょう。
具体策の実行
地域の課題ごとの対応策を具体的に策定した後は、それらの具体策を介護保険事業計画の中に盛り込み、施策として実行する必要があります。
具体策を実行するためには、地域ニーズに応じた在宅サービスの拡充や施設のバランスのとれた基盤整備、介護職人材の育成や処遇改善が必要になるでしょう。
地域ケア会議の5つの機能
地域ケア会議は、高齢者個人に対する支援の充実とそれらを支える社会基盤の整備とを同時に進めていく、地域包括ケアシステムの実現に向けた手法を指しています。
地域ケア会議には大きく分けて5つの機能が含まれています。
- 課題の個別対応機能
- 関係者同士をつなぐ機能
- 問題点を見つける機能
- 社会資源を見つける機能
- 政策化する機能
課題の個別対応
地域ケア会議には、現在高齢者が抱えている問題を個別に対応する機能があります。具体的には、自立支援に資するケアマネジメントの個別支援や支援困難事例等に関する事例に応じた相談や助言、自立支援に資するケアマネジメントの個別提供などがあげられます。
関係者同士をつなぐ
地域ケア会議では、関係者同士をつなぐ地域包括支援ネットワークの構築機能があります。自立支援に資するケアマネジメントの普及や関係者の共通認識を高め、地域住民との情報共有の場を設けます。関係者同士が互いの専門性を発揮しながら、課題の優先度の判断を行います。
問題点を見つける
地域全体で抱えている問題を見つける機能も、地域ケア会議に含まれています。具体的には、潜在ニーズの顕在化やサービス資源に関する様々な課題、ケアを提供する側のサービスの質に関する課題、利用者や住民等が抱えている地域特有の課題などがあげられます。
顕在ニーズ相互の関連づけを行うことによって、さらに問題点を深掘りできるようになるでしょう。
社会資源を見つける
地域ケア会議では、問題解決のために活用できる社会資源を見つける機能もあります。具体的には、有効な課題解決方法の確立とその普遍化、関係機関の役割の明確な区分けと役割分担、発見した社会資源の有効な配分調整、さらに新たな資源開発の検討などを行います。
政策化する
見つけた課題や問題点を解決するためには、具体的に動き出す必要があります。そのためには問題解決策を政策に反映させる政策化機能が欠かせません。
政策へと繋げるためには、需要に見合ったサービスの基盤の整備やその事業化・施策化、介護保険事業計画等への位置づけや、国や都道府県への提案などが必要になるでしょう。
地域包括支援センターでは、個別ケースのケアマネジメント支援のための実務者レベルの地域ケア会議を開催 するとともに、必要に応じて、蓄積された最適な手法や地域課題を関係者と共有するための地域ケア会議を開催することが求められます。

さらに市町村などの自治体には、有効な支援方法を普遍化する役割があります。地域課題を解決していくために代表者レベルの地域ケア会議を開催することが大切になります。
課題
今後さらに高齢化が進み、それぞれの地域における地域包括ケアシステムが果たすべき役割は非常に大きくなっていきます。同時に、地域包括ケアシステムを構築するにあたり、自治体ごとに様々な課題に直面し対応策を講じる必要性に迫られることでしょう。
地域包括ケアシステムが抱える主な課題は、以下の通りです。
- 医療や介護サービスのケアを提供する人数の不足
- 医療と介護の連携が十分でない
- 地域差がある
- 地域包括ケアシステムの認知度の低さ
- 対象が高齢者のみである
- 医療や介護サービスのケアを提供する人数の不足
医療や介護サービスのケアを提供する人数の不足
高齢者の割合が急速に増加する一方で、医療や介護サービスを提供する人材の数が十分でないことから、地域包括ケアシステムの制度は構築できても実際に稼動できない可能性が指摘されています。
医療と介護の連携が十分でない
今後医療的ケアと介護サービスの両方を求める高齢者が多くなることが予想される中、いまだに医療と介護の連携が十分でなく、それぞれが有している高齢者の情報を共有化する仕組み作りは急務と言えるでしょう。
地域差がある
地域包括ケアシステムの取り組みは各市町村レベルで行われます。自治体ごとに予算や人員の数は異なることから、地域包括ケアシステムの構築に関しては地域によって自ずと差が生じることになります。
地域包括ケアシステムの認知度の低さ
地域包括ケアシステムの構築を行政が積極的に進めている一方で、地域包括ケアシステムに関する周知が足りていないことから、地域包括ケアシステムの存在やその支援内容を知らない住民が大半だと言えます。
対象が高齢者のみである
法制度の中では、地域包括ケアシステムの対象者は65歳以上となっています。しかし現実的には65歳未満の方でも介護サービスを受けている方は多く、医療ケアや介護支援を兼ね備えた地域包括ケアシステムの必要性を感じている方も多くおられます。
介護施設への入居を検討・施設探しをしている方は、ケアスル介護での相談がおすすめです。
ケアスル介護なら、入居相談員にその場で条件に合った施設を教えてもらうことができます。
「自分に合った施設を選びたい」「予算内に合った施設を選びたい」という方は、ケアスル介護で無料相談をしてみてはいかがでしょうか。
ピッタリの施設を提案します
理解を深めてよりよい地域づくりに役立てよう

今回は地域包括ケアシステムの中身や地域包括ケアシステムが抱えるメリット・デメリットについて解説してきました。
地域包括ケアシステムは、やがて多くの方が高齢になり周りの助けが必要になった際も、昔から住み慣れた環境で人間らしく暮らし続けることを目標にした理想的なケアシステムです。
しかしながらまだまだ課題が多く、地域ごとにシステム内容に差が生じている実態があります。今後は地域包括ケアシステムに関する知識を深め、抱えている課題やデメリットも正しく理解し、よりみんなが暮らしやすい地域づくりに役立てることが重要になるでしょう。
地域包括ケアシステムとは、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもと、可能な限りこれまで通りの住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう行われる、地域の包括的な支援・サービス提供体制のことを指します。詳しくはこちらをご覧ください。
地域包括ケアシステムのメリットは、「医療と介護が一体化した継続的なサービス」「認知症になっても自宅で生活できる」「社会参加の応援」などが挙げられます。詳しくはこちらをご覧ください。