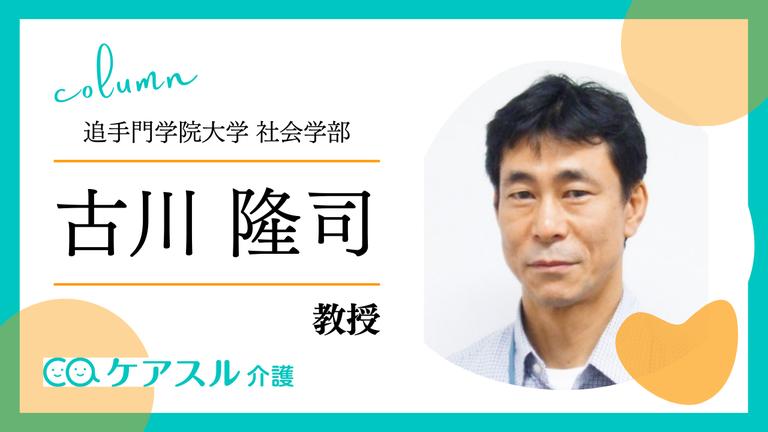今回は、認知症による触法行為とその支援についてお伝えしていきます。
追手門学院大学 社会学部
教員
放送大学大学院博士課程修了。
保育士・介護福祉士養成校を経て2006年度より現職。介護福祉士。
「罪を犯した障害者・高齢者の社会復帰支援」に関する国の研究班に参加。
記憶障害を中核症状とする認知症は、周辺症状でさまざまな生活課題を起こすおそれがあります。その一つが万引きといった触法行為です。たとえば買い物に行った先で支払いせず持ち帰ること、他人の家の前の鉢植えを持ち帰ることなどがあります。
認知症の場合意図的に万引きしたのでなく、支払いを忘れたとしても、行為自体は犯罪とみなされます。このため、周囲の理解を促す形でトラブルを避ける取り組みも支援側が試みなければなりません。ですが、行為が度重なるとか、店側も対応する人によって違いがあり、警察沙汰になることもあります。警察では事情聴取をおこない説諭することが多いですが、こちらも常習化すると、警察による逮捕で済まず、検察へ送検されたり、刑事裁判の被告となったりする場合もあります。
令和5年版犯罪白書によると、刑法犯の検挙件数に占める窃盗は46.7%、このうち高齢者による件数は46.8%を占めています。このうち、常習的な窃盗に対して有罪となり刑事施設に収容されている全被収容者のうち58.1%を占めています。必ずしも生活に困ったためだけでなく、認知症による不可抗力的なケースも相当数含まれていると考えられます。また、これらに対して社会福祉や介護サービスによる適切な支援があれば、刑事処分を受けずにケアを利用して地域での生活を続けられますし、見守りや地域社会での支え合いで触法行為を防げれば、その人らしい地域生活を支えることができるでしょう。
警察に検挙された場合や検察など刑事司法手続で扱われる場合、家族や支援者だけで対応できません。弁護士など法律の専門家に協力を求めることが大事です。お近くの弁護士会に相談しましょう。すぐに相談するのが難しい時は、福祉分野でも都道府県によっては社会福祉協議会や社会福祉士会によっては権利擁護事業に取り組んでいるところがあります。万一身近な人が触法行為によって警察に検挙された場合は、まずは専門的な支援をおこなっている団体に問い合わせることを勧めます。
認知症によるこれら触法行為が全て刑事司法手続で扱われるわけではありませんが、万引きが小売店へ大きなダメージになります。これら事業者も認知症への理解を示す一方、時に商売を続けられなくなるため、たとえば東京都では業界団体が全件通報するよう方針を決めています。地域の介護・福祉による相談支援を通して業界団体と話し合うことも大切ですし、「見守り」を関係者だけでなく商店街や小売業・金融サービスなど幅広い協力関係でおこなうことが必要です。
今日国が進めている孤立・孤独対策や重層的支援体制構築事業では、このような幅広い社会的な支えを作ることで、社会的に孤立する人を防ぎ、継続的な生活支援につなぐことが求められています。これは認知症のある人にもあてはまります。かれらのなした行為で社会的なつながりが途絶えれば,孤立状態になるからです。
その上で認知症のある人が安心して生活するには、認知症基本法に謳うような住み慣れた環境を築くことが不可欠です。触法行為はやむを得ないとしたら、それを受け止められる働きかけが関係者に求められているでしょう。