「認知症で寝ない親を介護していて、自分も体力の限界……」「仕事も家事も介護もしているから体力・気力的にもかなり辛い……」とお悩みではありませんか?
本記事では認知症で寝ない親の介護をしている方に向けて、原因や対処法を紹介します。
ほかにも認知症の親が寝たがらない理由、介助者がどのように体力・気力を維持したらよいのかについて解説します。
睡眠以外にも介護をしている方が苦労する入浴や食事など「認知症の方の日常生活」への対応方法を知りたい方も、ぜひ本記事を参考にしてください。
認知症の方が寝ない理由
認知症の方が寝ない理由として昼夜逆転があります。
認知症の症状によって日中の活動時間が少なくなり昼夜逆転が現れる場合があります。だれでも日中の活動時間が少なくなると体が疲れにくく、夜に眠くなりにくくなってしまうでしょう。
また、日中の活動量の低下以外の昼夜逆転の原因は、アルツハイマー型認知症の症状です。アルツハイマー型認知症の症状として以下のものがあげられます。
- 食事をしたことを忘れる(記憶障害)
- 時間や場所がわからなくなる(見当識障害)
- 体内時計が乱れる
- 睡眠が浅くなる
- 夜間不眠になる
これらの症状を併発することで昼夜逆転が起きやすくなります。
認知症の方が寝ないことで限界を迎えている介助者にしてほしい対処法
認知症の方が寝ないことで限界を迎えている介助者に実践してほしい対処法は次の5つです。
- 昼夜逆転しないように日中の活動量を増やす
- 寝室の環境を整える
- アルコールやニコチンの摂取を控えるようにする
- 気持ちに寄り添ってあげる
- 医療機関へ相談する
具体的にどのように実践すればよいのかを詳しく解説していきます。
1.昼夜逆転しないように日中の活動量を増やす
昼夜逆転しないようにするために日中の活動量を増やしましょう。
午前中に日光を浴びると体内時計がリセットされ、眠気を誘うホルモンのメラトニンの分泌が抑えられます。
メラトニンの分泌が抑えられると日中眠くなりにくく、昼寝のし過ぎを防げます。そして日中の活動量が増え、夜に自然と眠くなるのです。
昼寝をする場合は短い時間で済ませます。長く寝過ぎてしまうと昼夜逆転を招いてしまうため、布団やベッドで寝ないように注意が必要です。
家の中に入る日光だけでは十分ではなく、午前中に散歩をしたり、一緒に買い物に行ったりなど、屋外での適度な運動が必要です。
2.寝室の環境を整える
夜しっかり眠るためには部屋の環境を整えることが大切です。
夜は眠気を誘うホルモンのメラトニンを分泌させるため、認知症の方が不安に感じない程度に照明を暗くしたり間接照明を使ったりし、明るすぎない環境を整えましょう。
また、時計やテレビの音が気になって眠れない場合があります。寝室の時計は音の静かな物にしたり、寝室にテレビの音が届きにくくしたりする工夫が必要です。
ほかにも部屋の温度や湿度は適切か、体が冷えていないかも確認する必要があります。身体が冷えている場合は就寝する2~3時間前の足湯や入浴が効果的です。入浴や足湯が難しい場合は湯たんぽで足を温めるとよいでしょう。
3.アルコールやニコチンの摂取を控えるようにする
夜にしっかりと眠るためには、アルコールやニコチンの摂取を控えるようにすることが重要です。
アルコールは膀胱を刺激して尿意を催す作用があります。夜眠れなくなる原因として多いのが、「トイレ」の心配です。トイレに間に合わないかもしれないとの心配から夜眠れなくなってしまうことがあります。トイレの心配を減らすために、アルコールの摂取は控える必要があるでしょう。
また、ニコチンには交感神経を活発にする作用があるため、摂取すると眠りに入りにくくなってしまいます。夜しっかり眠るためにもニコチンの摂取は控える必要があります。
4.気持ちに寄り添ってあげる
認知症の方は日々の生活に不安を感じて過ごしているため、不安な気持ちに寄り添ってあげることが重要です。
認知症の方は暗かったり、自分のいる場所がわからなくなったりすると不安を感じてしまいます。また、昼間の出来事によって夜になっても不安を感じたまま過ごしていることもあるでしょう。
そんな認知症の方の安眠を促すためには、気持ちに寄り添ってリラックスさせてあげることが重要です。認知症の方の不安な気持ちを取り除くためには、よく話しを聞き、安心できるような声かけを心がけましょう。
5.医療機関へ相談する
生活の改善を図っても効果がないときは医療機関へ相談しましょう。
場合によっては睡眠薬が処方されることがあり、適切に使うことで認知症の方も介助者も双方がしっかりと休めるようになります。
家族が手持ちの睡眠薬を使用するケースも時折あるようですが、かえって昼間の眠気が強くなり、昼夜逆転が強くなってしまう場合もあります。また、夜間に起きたときにふらつくこともありますので、必ず医師の処方による内服をおすすめします。
医療機関を受診する際は普段から寝た時間や起きた時間といった認知症の方の睡眠記録をつけておくとより相談しやすくなります。昼寝の様子など、日中どのように過ごしているか可能な範囲で記録しておくとよいでしょう。日中デイサービスに通っている認知症の方は、デイサービスの記録を提示するのもよいでしょう。
認知症で寝ない親に限界を感じている方の工夫とは
認知症で寝ない親に限界を感じている方は、一人で抱え込まないようにする工夫が必要です。ついつい自分の事は後回しにしてしまう介助者も多いと思いますが、自分のことも大切にしなければいけません。
ここでは限界を感じている際の以下の3つの工夫を紹介します。
- 介助者が心療内科を受診して睡眠薬をもらう
- ポータブルトイレをベッドの横に置く
- 専門家(ケアマネジャーなど)に相談する
それぞれの内容を詳しく解説していきます。
1.介助者が心療内科を受診して睡眠薬をもらう
疲労が溜まりすぎて不眠になってしまう場合は心療内科を受診しましょう。場合によって睡眠薬を処方してもらうこともできます。
認知症の方の介護は介助者とって精神的な負担が大きく、介護疲れによって介助者が心身共に不調をきたしてしまう場合があります。
しかし、介助者が一人の場合は認知症の方が深夜徘徊など何かあった際に気づかない恐れがあります。心療内科を受診した際は、介護中であることを伝えて医者と二人三脚で介護の体制を整えていきましょう。
介助者は辛い気持ちを我慢せず、心療内科に相談をするなど一人で抱え込まないことが大切です。
2.ポータブルトイレをベッドの横に置く
夜間、認知症の方がトイレへ行く度に介助者の目も覚めてしまうようなら、ベッド横にポータブルトイレを置く方法があります。
ポータブルトイレとは持ち運びができる簡易的なトイレです。ベッド横に設置できるため、認知症の方にとっても介助者にとっても双方の負担を軽減することが期待できます。認知症の方がトイレに起きたものの、トイレまでの行き方がわからずに失禁するといったことを防ぐことにもつながり、介助者の夜間の負担が減ることが期待できます。
なお、立ち上がりが不安定な認知症の方の場合は介助者が同室でないと、ポータブルトイレでも転倒の危険があるのでご注意ください。
3.専門家(ケアマネジャーなど)に相談する
認知症の方の介護に少しでも疲れを感じたらケアマネジャーなどの介護の専門家に相談しましょう。
専門家に相談することで、より具体的な認知症の方への対応方法を知ることができます。
介助者は介護をする中で孤独を感じることが多いため、相談する相手がいるだけでも非常に心強く感じます。また、ケアマネジャーに相談することでさまざまな介護サービスへと繋げていくことができます。
介助者は限界を迎える前に専門家へ相談することが非常に大切です。
認知症の方が嫌がる睡眠以外の「日常動作」とは
認知症の方は睡眠以外にも嫌がる「日常動作」があります。日常動作とは日常生活を送るうえで必要最低限の動作のことです。認知症の方が嫌がる日常動作として以下のものがあります。
- 食事
- 入浴
- 服薬
食事・入浴・服薬は私たちも面倒くさいと感じることはあるでしょう。しかし認知症の方は認知症症状によりさまざまな理由で日常動作を嫌がる場合があります。
認知症の方が日常動作を嫌がる理由を詳しく解説していきます。
1.食事
認知症の方が嫌がることとして食事があります。
認知症の方が食事を嫌がるのは以下の理由があげられます。
- 食べ物を認識できない
- 食事の仕方がわからない
- 食べ物が上手く飲み込めない
- 入れ歯が合っていない
- 食事の環境がととのっていない
例えば、私たちは食事を視覚や嗅覚で食事と認識して食べています。しかし、認知症の方には目の前のものが食べ物と認識することができない失認の症状があります。食べ物と認識していないものを無理矢理口に運ばれたら嫌がるのは当たり前ではないでしょうか。
食事を嫌がることなく食べてもらうには、食事の盛り付けや食器を工夫する必要があります。
2.入浴
認知症の方で入浴を嫌がる方は非常に多くいらっしゃいます。
嫌がる理由として以下があげられます。
- 記憶が曖昧になるため
- 衣類を脱ぐのに抵抗があるため
- 入浴が面倒くさいため
- 入浴に悪いイメージがあるため
入浴を嫌がる理由の1つの「記憶が曖昧になるため入浴を嫌がる」とは、認知症の症状である記憶障害が関係しています。認知症の方は記憶障害によりいつ入浴したかといった時間的な感覚が曖昧になります。実際は1週間お風呂に入っていなくても、記憶障害によりついさっきお風呂に入ったばかりと思っている認知症の方に「さあ、今からお風呂に入りましょう」と声をかけても、「さっき入ったばっかりだから嫌だ」となってしまうでしょう。
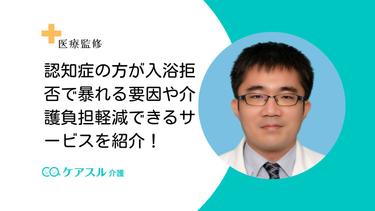
3.服薬
認知症の方は服薬を嫌がることがあります。
服薬を嫌がるのは以下の理由です。
- 必要性を感じていない
- 服薬のタイミングが悪い
- 副作用が出ている
- 上手く飲み込めない
例えば服薬の必要性を感じていない場合は、認知症の方自身が病気である自覚や診察された記憶がない場合に多くあります。「病気でもないのになぜ薬を飲まなければならないのか」との思いが服薬を嫌がることに繋がります。服薬を介助する方は認知症の方が納得するような工夫が必要です。
また、絶対に飲まなければならない薬だからと無理矢理飲ませようとすると嫌な記憶が残り、それ以降服薬の拒否がさらに激しくなってしまう可能性があります。
認知症の方の「不快感」「不安」を取り除く3つの方法
認知症の方は不快感や不安をとても感じやすいため、日々の生活の中で不快感や不安を取り除く必要があります。不快感や不安を取り除く3つの方法をご紹介します。
- 興味の対象を他に移す
- 不安にならないように声がけをする
- 言い方を変えて「特別感」を演出する
不快感や不安を取り除くことは、認知症の方がポジティブに過ごすために大切なことです。
不快感や不安を取り除く方法を具体的に解説していきます。
1.興味の対象を他に移す
認知症の方が一つのことに囚われている場合は、興味の対象を他に移すことが有効です。お風呂に入るように声をかけた際に、「お風呂に入りたくない」との気持ちに囚われている場合、本人の興味あるものやグッズなどをお風呂の中に用意してみましょう。お風呂に対する不快な気持ちや不安な気持ちを、興味のあるものに向けることで気持ちが切り替わることがあります。スムーズな入浴につながり、「楽しい」「うれしい」といった認識に段々と変わっていくかもしれません。
なお、機械類をお風呂に持っていくのは危険です。防水のものや機械以外のものを持っていくようにしましょう。
2.不安にならないように声かけをする
認知症の方が不安にならないような声かけを心がけましょう。認知症の方は不安を抱えている方が多くいらっしゃいます。今まで出来ていたことが出来なくなったり、忘れてしまったりする不安から頑張りすぎてしまうことがあります。認知症の方が不安にならないように安心できる声かけを意識する必要があります。
「大丈夫」「私も行くよ」「私が代わりに覚えておくから安心してね」といった声かけを受けることで、認知症の方も安心して過ごせるのではないでしょうか。
3.言い方を変えて「特別感」を演出する
認知症の方と日々過ごす中で特別感を演出してみましょう。
ただお話しするよりも「今日はゴロゴロしながらあの話しをしよう」と誘うと、特別感が演出できますね。特別感をあじわうことで認知症の方も「嬉しい」「楽しい」といったプラスの感情がうまれます。
プラスの感情は認知症の方にとても良い影響をあたえます。普段の何気ないことに特別感を演出してください。
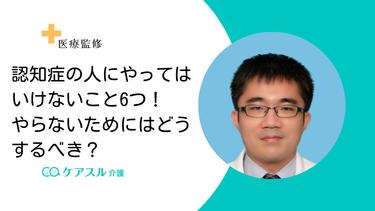
認知症の方とはいえ親の気持ちを考えてみると対応できる
「認知症の方」との見方を変えて、「自分の親」と改めて認識してみた場合、自分の親が「怖い」「不安」といった気持ちを抱えていたときは寄り添うのではないでしょうか。また、「強制しないでほしい」「さっき〇〇したばっかりだから嫌」との意思表示を見せたら強制したりせず、意志を尊重するはずです。
認知症の方はただ理由もなく拒否をするのではありません。一人の人間として拒否することで意思表示をしています。拒否をすることには何かしら理由があるのです。
「認知症」のレッテルを貼るのではなく、「一人の人間」「親」として接していくことも大切なのではないでしょうか。
まとめ:認知症で寝ない親に限界と感じるなら「施設の利用」を検討してみて
認知症で寝ない親の介護に限界を感じたら施設の利用を検討してみましょう。親を施設に預けることに罪悪感があり、無理を続ける必要はありません。
認知症の方が利用できる施設は以下のものがあります。
| 特別養護老人ホーム | 入所条件:原則65歳以上/要介護3以上 |
| 介護老人保健施設 | 入所条件:原則65歳以上/要介護1以上
※自宅に戻ることが前提 |
| 介護付き有料老人ホーム | 入居条件:自立~要介護
※施設によってさまざま |
| グループホーム | 入居条件:65歳以上/要支援2以上/認知症の診断/グループホーム所在地に住民票がある |
介助者が自分の限界を感じてしまった時には、介護施設などを利用して積極的に介助者自身の負担も軽減していきましょう。
昼夜逆転しないように日中の活動量を増やしたり、寝室の環境を整えたりするのがおすすめです。ほかにも、アルコールやニコチンの摂取を控えるようにする、気持ちに寄り添ってあげるのもよいでしょう。それでも解決しない場合は、医療機関へ相談することも視野に入れてみてください。詳しくはこちらをご覧ください。
他に興味の対象を移す、不安にならないように声掛けをする、言い方を変えて「特別感」を演出するなどがおすすめです。詳しくはこちらをご覧ください。








