要介護2は、日常生活の動作全般に見守りや介護が必要な状態です。
介護に必要な時間も増えるため、ご家族の方は疲労やストレスが溜まってしまい、体調が悪化してしまうことも少なくありません。
そういった状況で利用したいのが、介護保険サービスです。介護保険サービスは利用者の心身機能の維持・回復はもちろんですが、ご家族の方の負担を減らすことも目的としています。
しかし、要介護2ではどんな内容のサービスが受けられるのか分からないという方もいるのではないでしょうか。
本記事では、要介護2で受けられるサービスやその内容、利用方法、実際の利用例について紹介します。
参考になれば幸いです。

要介護2で受けられるサービス一覧
要介護認定を受けた方であれば、介護保険サービスを受けることができます。
要介護2の方であれば、自宅で介護を受けることができる「訪問型」、施設に通いサービスを受ける「通所型」、1日から30日という短期間施設に入所しサービスを受ける「短期入所型」、それらのサービスを組み合わせて利用する「複合型」、施設に入所し生活する「施設型」などのサービスを受けることが可能です。
要介護2で受けられる介護保険サービスは、以下の通りです。
| サービスの種類 | サービス内容 | |
|---|---|---|
| 訪問サービス | 訪問介護 | 訪問介護員が自宅を訪問し、食事・排せつ・入浴などの介護や掃除・洗濯・買い物などの生活支援を行う |
| 訪問入浴 | 介護・看護職員が自宅を訪問し、持参した浴槽で入浴の介護を行う | |
| 夜間対応型訪問介護 | 24時間安心して過ごせるよう、夜間帯にも対応している訪問介護サービス。 安否確認や排せつの介助等を行う「定期巡回型」と、転倒した際や急な体調不良等の有事の際に介護をする「随時対応型」の2つに分かれている。 |
|
| 訪問看護 | 看護職員が疾患のある利用者の自宅を訪問し、主治医の指示に基づいた療養上の世話や診察の援助を行う | |
| 定期巡回・随時対応型訪問 介護看護 |
「定期巡回型」と「随時対応型」の両方に対応しており、訪問介護だけでなく訪問看護も組み込まれているサービス | |
| 訪問リハビリ | 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等の専門スタッフが自宅を訪問し、心身機能の維持・回復や日常生活の自立に向けたリハビリを行う | |
| 居宅療養管理指導 | 医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士等の専門家が自宅を訪問し、療養上の管理・指導を行う | |
| 通所サービス | 通所介護(デイサービス) | 介護施設に通い、介護・生活援助・機能訓練等のサービスを受けることができる日帰りのサービス。自宅と施設までは送迎してくれる。 |
| 通所リハビリ(デイケア) | 病院・老健・診療所等に通い、専門スタッフによる機能訓練・日常生活動作等のリハビリを受けることができる。食事や入浴といった生活援助の提供もある。 | |
| 認知症対応型通所介護 | 認知症の方を対象とした通所介護サービス。 | |
| 地域密着型通所介護 | 定員18人以下の施設で、入浴や食事などの介護や機能訓練等のサービスを受けることができる。定員が少ないため、一人ひとりに寄り添った対応が可能。 | |
| 療養通所介護 | 常に看護師による観察が必要な難病、認知症、脳血管疾患後遺症等の重度要介護者又はがん末期患者を対象にしたサービス。医師や訪問看護ステーションと連携して食事・入浴などの日常生活支援、機能訓練が提供される。 | |
| 短期入所サービス | 短期入所生活介護 (ショートステイ) |
介護施設に短期間入所し、介護・生活援助・機能訓練等のサービスを受けることができる。1度で最大30日までの利用が可能。 |
| 短期入所療養介護 (医療型ショートステイ) |
老健や介護医療院といった医療体制が整っている施設に短期間入所し、介護・生活援助に加え、医療処置や看護等の医療サービスを受けることができる。1度で最大30日までの利用が可能。 | |
| 複合型サービス | 小規模多機能型居宅介護 | 施設への通いを中心として、訪問・宿泊サービスを組み合わせ、介護・生活援助・機能訓練等のサービスを受けることができる。 |
| 看護小規模多機能型 居宅介護 |
小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせたサービス。 | |
| 施設サービス | 老健(介護老人保健施設) | 利用者の在宅復帰を目的とした施設。介護・看護・生活援助・リハビリ等のサービスを受けることができるが、原則3~6か月で退所しなければならない。 |
| ケアハウス | 自立した生活が難しい高齢者の方を対象とした、少ない費用で介護・生活援助等のサービスが受けられる施設。 | |
| 介護療養型医療施設 | 比較的重度の要介護者を対象とした、充実した医療処置・リハビリ等のサービスが受けられる施設。 | |
| 介護医療院 | 介護療養型医療施設で受けられるサービスに加え、介護や生活援助にも力を入れている施設。 | |
| 有料老人ホーム | 食事・介護・生活援助・健康管理のうち1つ以上を提供している施設。24時間介護サービスを受けることができる「介護型」、生活援助を中心に受けることができる「住宅型」、食事等の生活援助のサービスを提供する「健康型」等の種類がある。 | |
| サ高住(サービス付き高齢者向け住宅) | 「安否確認」「生活相談」等のサービスを受けることができるバリアフリー対応の施設。 | |
| グループホーム | 認知症の方を対象とした、少人数での共同住宅の形態でサービスを受けることができる施設。 | |
| 福祉用具の 利用サービス |
福祉用具の貸与 | 車いすや介護ベッド等の福祉用具をレンタルすることができるサービス。 |
| 福祉用具の販売 | 簡易浴槽や入浴補助用具等の福祉用具を購入することができるサービス。 | |
以下では、それぞれのサービスについて簡単に触れていきます。
施設への入所を検討しているという方は、ケアスル介護がおすすめです。ケアスル介護なら、入居相談員にその場で条件に合った施設を教えてもらうことができるためご希望に沿った施設探しが可能です。
「プロに相談したい」という方は、ご気軽に無料相談を活用ください。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
要介護2で受けられるサービス①訪問型サービス
訪問サービスとは、文字通り、訪問介護員や看護師が利用者の自宅に訪問し、リハビリや生活援助、医療ケア等のサービスを提供するというものです。
担当の職員や看護師が利用者の自宅へ訪問しサービスを提供してくれるため、利用者は自宅から移動する必要がなく、利用者本人にかかる負担が少ないのが特徴と言えるでしょう。
以下では、訪問型サービスに該当するサービスを詳しく紹介します。
訪問介護
訪問介護とは、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅に訪問し、自宅で身体介護や生活援助等のサービスを受けられるサービスとなります。
具体的なサービス内容としては、以下の通りです。
- 身体介護:入浴・食事・排せつの介助や着替えの援助、身体の清拭、体位変換など
- 生活援助:掃除・洗濯・調理のような家事や衣服の整理、買い物代行、薬の受け取りなど
訪問介護は、自宅に居ながら利用できるため、身体的にも・精神的にも負担がかかりづらく、利用する方が多いサービスとなっています。
訪問入浴
訪問入浴とは、専門の事業者が、寝たきり等の理由で自宅の浴槽では入浴が困難な被介護者に対して、専用の介護浴槽を自宅に持ち込み入浴の介護を行うサービスとなります。
入浴の前後には血圧や体温のチェックが行われるため、入浴は危険だと判断された場合には、足浴や清拭に変更されることがあります。
自宅での浴槽では入浴が難しいという場合は、利用を検討してみるといいでしょう。
夜間対応型訪問介護
夜間対応型訪問介護とは、通常訪問介護が提供されていない夜間帯に利用できる訪問介護となります。
夜間対応型訪問介護は、以下の2つのサービスに分かれています。
- 定期巡回サービス
- 随時対応型サービス
定期巡回サービス
定期巡回サービスとは、18時から翌朝8時までの間に定期的に自宅に訪問し、排せつの介助や安否の確認を提供するサービスとなります。
1回の訪問当たり30分程度の介助を受けることができます。また、頻度については作成されたケアプランに基づいて行われます。
ただし、あくまでも訪問介護であり、医療行為等のサービスは受けることができないため、注意が必要です。
夜間にも身体介助が必要な方は、利用を検討してみるといいでしょう。
随時対応サービス
随時対応サービスは、緊急時に連絡することで、訪問介護員が自宅へ訪問し対応してくれるサービスとなります。
緊急時の例としては、「急な体調の変化」「転倒し動けない」「トイレで失敗してしまった」などが挙げられ、状況に応じて身体介助を行ってくれたり、場合によっては救急車を手配するなど、適切な対応を取ってくれるため、いざという時にも安心です。
事業者への連絡手段ですが、事業者から借り受けた専用の通報装置を用いて通報することになります。ナースコールのようなものを意識すると分かりやすいのではないでしょうか。
一人暮らしをしている方や、万が一の事態を不安に感じる方は、利用を検討してみるといいでしょう。
訪問看護
訪問看護とは、主治医の指示に基づき、看護師等の職員が利用者の自宅を訪問し、病状の確認や点滴、痰の吸引などの必要な医療行為を提供するサービスとなります。
訪問看護で受けることができる医療行為としては、以下のものが挙げられます。
- 体温・血圧チェック
- 床ずれの処置やその予防
- • 在宅酸素、カテーテルやドレーンチューブの管理
- 点滴
また、24時間のサービス提供に対応している事業者もあるため、24時間体制の医療行為が必要な方でも安心です。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは、前述の定期巡回・随時対応ともに対応しており、また介護だけでなく訪問看護のサービス内容も含まれているサービスとなります。
前述の定期巡回や随時対応サービスでは、医療行為を受けることができませんでしたが、こちらのサービスでは利用することができるという特徴があります。
訪問リハビリ
訪問リハビリは、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などの専門家が利用者の自宅に訪問し、在宅でリハビリを行ってくれるサービスです。
現在の生活機能の維持・回復や社会参加が主な目的であり、利用者が可能な限り自立した生活を送れるよう、リハビリのサポートを行ってくれます。
リハビリの内容としては、以下のものが挙げられます。
- 歩行・寝返り・起き上がり・立ち上がるなどの機能訓練
- 入浴・排せつ・食事・着替えなどの生活動作訓練
訪問リハビリは、在宅で行うことができるため、「実際の生活環境に沿った訓練が可能」「利用者本人がリラックスして取り組める」といったメリットがあります。
居宅療養管理指導
居宅療養管理指導とは、医師や看護職員が、利用者の自宅に訪問し療養上の管理および指導を行うサービスとなります。
主に服薬管理や栄養管理、嚥下機能に関する管理指導等のサービスを受けることが可能です。
通院が困難な方は利用を検討してみるといいでしょう。
要介護2で受けられるサービス②通所型サービス
通所サービスは、利用者本人がサービスを提供している施設に通いサービスを受ける形態のことを指します。
訪問型と異なり、利用者本人が自宅から移動する必要があるため多少負担はかかりますが、他の方との交流の場になるなど、自宅では得られない効果もあるため、必要に応じて利用するといいでしょう。
なお、通所型サービスは日帰りでのサービスになっており、宿泊はできないため注意が必要です。
以下では、通所型サービスに該当するサービスを詳しく紹介します。
通所介護(デイサービス)
通所介護は、日帰りで介護施設(利用定員19人以上のデイサービスセンターなど)に通い、施設にて食事・排せつ・入浴などの介護や機能訓練などのサービスを受けることができるというものです。それらのサービスに加え、施設側が送迎も行ってくれるため、利用しやすいのもポイントです。
通所介護は、利用者が可能な限り自立した生活を送れるよう、心身機能の維持・回復だけでなく、自宅に籠りがちの利用者の孤立感の解消も目的としています。
施設では、施設スタッフだけでなく他の高齢者との交流もあるため、自宅に籠りがちで気分が落ち込んでしまうという方は積極的に利用してみるといいかもしれません。
通所リハビリ(デイケア)
通所リハビリは、日帰りで老健・病院・診療所などの施設に通い、施設にて、生活機能向上のための訓練や食事・排せつ・入浴などの介護を受けることができるサービスです。
通所介護と違う点として、通い先の施設やサービス内容が挙げられます。
通所リハビリでは、老健や病院のような医療ケアに秀でた施設に通うことになります。入所する施設の特性から、通所介護と比べてリハビリや医療ケアに特化したサービスを受けることができます。
「介護」と「機能訓練をはじめとした医療ケア」どちらに重きを置くかで適したサービスが異なるため、よく検討してから利用することをおすすめします。
認知症対応型通所介護
認知症対応型通所介護は、認知症の症状が見られる方に向けたサービスであり、施設に通うことで、施設にて食事・排せつ・入浴などの介護や機能訓練を受けることができます。
通所介護では、認知症患者に対応しきれていないケースもありますが、認知症対応型通所介護であれば、認知症の専門的なケアを受けることが可能です。
サービス内容も、利用者本人が楽しく通うことができるという点に重きが置かれているため、認知症の症状が見られる方でも安心して通うことができます。
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護は、介護施設(利用定員19人未満のデイサービスセンターなど)に通い、施設にて食事・排せつ・入浴などの介護や機能訓練などのサービスを受けることができるというものです。
通所介護と異なる点としては、通い先の施設の利用者定員が少ないため、利用者1人に対してより柔軟な対応をすることが可能な点があります。
手厚いサービスを受けたいという方は、地域密着型通所介護の利用を検討してみるといいでしょう。
療養通所介護
療養通所介護は、常に看護師による観察を必要とする難病・認知症等の重度要介護者の方に向けたサービスであり、施設に通うことで、施設にて食事・排せつ・入浴などの介護や機能訓練を受けることができます。
通所介護では、医療的処置が必要な方は利用が制限されてしまいますが、療養通所介護であれば、医療体制が整っているため、看護師の観察が必要な方も利用することができます。
慢性的に医療的処置が必要な方は、療養通所介護の利用を検討するといいでしょう。
要介護2で受けられるサービス③短期入所型サービス
短期入所サービスとは、文字通り短期間だけ施設に入所し生活するというものです。
一般的にはショートステイと呼ばれており、やむを得ない理由で介護ができない場合やご家族がリフレッシュしたい際に利用されることが多いサービスとなっています。
短期入所サービスは、1日から利用することができ最大30日間宿泊することが可能です。
以下では、短期入所型サービスに該当するサービスについて詳しく紹介します。
短期入所生活介護(ショートステイ)
短期入所生活介護は、特養のような介護施設に短期間入所し、入浴・排せつ・食事等の介助や機能訓練等のサービスを受けることができるというものになります。
施設に入所できる期間は1日~30日までとなっており、30日を超えると超過分は全額自己負担となるため注意が必要です。
ご家族の方の介護の負担軽減や自宅に籠りきりになってしまっている被介護者の方の孤立感の解消などの目的で利用されることが多いサービスとなっています。
短期入所療養介護
短期入所療養介護は、老健や介護医療院等の医療機関に短期間入所し、看護および医学的管理の下で介護や生活援助、医療ケア、機能訓練等のサービスを受けることができるというものになります。
短期入所生活介護と異なる点としては、入所先の施設やサービスの違いが挙げられます。
短期入所療養介護では、老健や介護医療院の医療機関に入所することになります。短期入所生活介護と異なり、医療機関へ入所するためサービス内容も異なっており、「投薬」「リハビリ」などのより医療的専門性の高いサービスを受けることができます。
入所期間は、短期入所生活介護と同じく1日~30日となっており、30日を超過した分は全額自己負担となるため注意が必要です。
短期入所型サービスを利用する際は、違いを踏まえたうえで適切な方を選択するようにしましょう。
要介護2で受けられるサービス④複合型サービス
複合型サービスは、「通い」「宿泊」「訪問介護」「訪問看護」等のサービスを組み合わせて利用することができるサービスです。
前述の4つのサービスを1つの事業所が提供しているため、利用者の状況により柔軟に対応可能という特徴があります。
また、利用手続きが1回で済むというメリットもあります。
以下では、複合型サービスに該当するサービスを詳しく紹介します。
小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護は、利用者の選択に応じて「訪問」「通所」「宿泊」の3つを組み合わせて利用できるサービスとなります。
利用者が可能な限り自立した生活を送れることを目的としており、家庭的な環境や地域住民との交流のもと、日常生活の支援や機能訓練を行うという特徴があります。
訪問・通所・宿泊の3つのサービスを同じスタッフが担当することから、連続性のあるケアを受けることができるため、安心感を得られやすいサービスとなっています。
また、自宅で生活しながら利用できるサービスであるため、「自宅は離れたくないけど介護が必要という方」や「一人暮らしをしていてご家族からの支援を受けるのが難しいという方」におすすめのサービスです。
看護小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護とは、前述の小規模多機能型居宅介護と訪問介護を組み合わせたサービスになります。
訪問看護のサービスを利用することができるため、自宅でも医療行為を受けられるようにしたいという方は、看護小規模多機能型居宅介護の方が適していると言えるでしょう。
複合型サービスの利用を検討する際は、医療行為の有無を十分に考慮したうえで、適したサービスを選ぶようにしましょう。
要介護2で受けられるサービス⑤施設サービス
施設サービスは、老健、介護医療院等の施設に入所して受けるサービスを指します。
施設へ入所すれば、専用の設備を用いた介護やリハビリなどのサービスを高い頻度で受けることができるため、自宅に比べて安心して生活することができるでしょう。
施設の特徴により異なりますが、介護・生活援助・機能訓練等のサービスを受けることができます。
以下では、要介護2の方が入所可能な施設について詳しく紹介します。
老健(介護保険施設)
老健は、入院などで医療ケアを受けていた高齢者が在宅復帰を目指す施設であり、そのためのリハビリや身体介護を提供しています。
在宅復帰を目的とした施設であるため、リハビリや医療体制が充実している、また、公的な介護施設であるため、民間団体が運営する介護施設に比べ費用が安いという特徴を持ちます。
ただし、あくまでも在宅復帰を目的とした介護施設であるため、ずっと入所することはできず、原則3~6か月で退所審査が行われ、「自宅復帰が可能な状態」と判断された場合は、退所する必要があります。
在宅での暮らしを目標としている方は、老健への入所を検討してみるといいかもしれません。
ケアハウス
介護型のケアハウスは、食事・排せつ・入浴等の介護や掃除・洗濯などの生活援助サービスを受けることができる施設です。
介護型であれば、要介護1以上の比較的介護を必要とする場面が多い方でも入所することができ、また他の施設に比べ安い費用で入所することができるため、人気のある施設になります。
ただし、介護型のケアハウスは施設数の少なさから入所希望者が集中するため、入所待ち期間が発生する場合が少なくありません。
すぐに施設に入所したいという方には、向かない可能性があるため注意が必要です。
介護療養型医療施設
介護医療型医療施設は、食事・排せつ・入浴等の介護をはじめ、充実した医療ケアやリハビリを提供する施設となります。
入所条件は、医学的管理が必要な要介護1以上の高齢者とされており限定的ではありますが、看護師の人員配置が他の施設より手厚く、「インスリン注射」「痰の吸引」「経管栄養」などの医療ケアを受けることができるため、医療ケアが原因で介護施設へ入居できない方は、入所を検討してみるといいかもしれません。
なお、介護療養型医療院は2017年に廃止が決定し、「介護医療院」という施設に置き換わったことを把握しておきましょう。
介護医療院
介護医療院は、廃止が決定した介護療養型医療施設に代わり、新たに法定化された施設です。
介護療養型医療施設と大きな違いはなく、介護をはじめ、医療ケアやリハビリ等のサービスを受けることが可能です。ただし、介護療養型医療施設と異なる点として、介護医療院では、地域のボランティアの方がレクリエーションを担当することがあるなど、地域の人との交流や生活の場であることが重視されているという一面があります。
2018年に新設されたばかりの施設であるため認知度はあまり高くありませんが、今後は介護療養型医療施設は介護医療院に置き換わるため、把握しておきましょう。
有料老人ホーム
有料老人ホームとは、「介護(入浴・排せつ・食事の提供)」「洗濯・掃除等の家事の供与」「健康管理」のうちいずれかひとつ以上をサービスとして提供している施設を指します。
有料老人ホームは、特養などの社会福祉団体や自治体が運営する施設に比べ費用が高くなる傾向にあるため、特徴をしっかりと把握しておきましょう。
有料老人ホームは、施設の特性によって「介護付き」「住宅型」「健康型」の3つに分類されます。
なお、健康型は自立の方を対象とした施設であるため、紹介は省きます。
介護付き有料老人ホーム
介護付き有料老人ホームは、24時間介護スタッフが常駐し入浴や排せつ、食事等の生活介助から掃除や洗濯等の家事サービス等を提供している有料老人ホームを指します。
介護サービスが充実している点が特徴の施設ですが、通常の介護費用に加えて上乗せ介護費用が発生する場合があるなど、費用が高くなる傾向にあります。入居を検討する場合は事前に確認しておきましょう。
住宅型有料老人ホーム
住宅型有料老人ホームは、主に自立・要支援、要介護度が低い方を対象とした老人ホームになりますが、施設によっては要介護5まで受け入れている施設もあります。
介護付き有料老人ホームと異なる点としては、介護サービスがサービス内容に含まれていない点が挙げられます。
住宅型有料老人ホームのサービスは食事の提供や掃除・洗濯等の家事サービス、見守り等が中心であり、介護サービスを受けたい場合は、外部の訪問介護事業所や併設の介護事業所と契約をして介護サービスを受けることになります。
外部の介護サービスの料金は、外部の介護サービスの料金は、介護保険を利用することができますが、介護度が高く利用回数が多くなると介護保険の支給上限額を超えてしまいます。 超えた分の費用は、すべてが自己負担となります。介護サービス利用が少ない方は、介護型に比べ費用が安く済むというメリットがあります。
サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)
サ高住とは、バリアフリーに対応した高齢者向けの賃貸住宅であり、「安否確認」「生活相談」等のサービスを受けることが可能です。
サ高住によっては介護サービスの提供がない施設もあるため、介護サービスを利用したい場合には、介護サービスを提供している介護型のサ高住に入居するか、外部の介護サービスを利用する必要があります。
サ高住は、介護施設ではなく賃貸住宅という形になるため、施設のように決められたタイムスケジュールで動く必要がなく、比較的自由度の高い生活を送ることができます。
グループホーム
グループホームとは、認知症の症状が見られる方を対象とした、5~9人の少人数からなる共同住宅の形態(ユニット)でケアサービスを提供する施設となっています。
認知症の進行を抑えること、また生活機能の維持を目的とした施設であり、入居者同士の関りが深く慣れ親しんだ環境を作りやすいことから、認知症の改善につながる可能性が期待されています。
グループホームでは、「食事・排せつ・入浴等の介護」「その他の日常生活上の援助」「リハビリ」等のサービスを受けることができます。認知症ケアはもちろん、日常生活を送るうえで必要なサービスも受けることができるため、安心して入居できる施設と言えるでしょう。
認知症の症状が見られることが多く、専門的な認知症ケアを受けたいという方は入居を検討してみるといいかもしれません。
関連記事
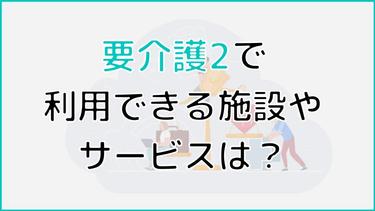 要介護2で入れる施設は?カテゴリ:要介護2更新日:2024-06-14
要介護2で入れる施設は?カテゴリ:要介護2更新日:2024-06-14関連記事
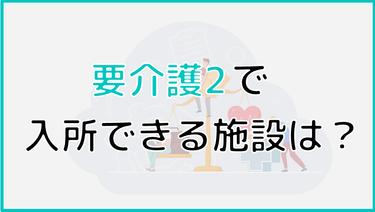 要介護2で入所できる施設は?費用相場と施設選びのポイントも解説カテゴリ:要介護2更新日:2024-06-14
要介護2で入所できる施設は?費用相場と施設選びのポイントも解説カテゴリ:要介護2更新日:2024-06-14
施設への入所を検討しているという方は、ケアスル介護がおすすめです。ケアスル介護なら、見学予約から日程調整まで無料で代行しているためスムーズな施設探しが可能です。
「まずは相談したい」という方は、ご気軽に無料相談を活用ください。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
要介護2で受けられるサービス⑥福祉用具のレンタル・購入

要介護認定を受けた方は、要介護度に応じた福祉用具のレンタル・購入が可能です。
要介護2の認定を受けた方がレンタルすることができる福祉用具は以下の通りです。
| 福祉用具の種類 | 詳細 |
|---|---|
| 車いす | 自力での移動が困難な方のための、移動補助用具。 自走式と介助式の2つがあり、自走式はハンドリムを回すことで自力で移動できるが、介助式は押してもらうことでのみ移動できる。 |
| 車いす付属品 | 車いすに取り付けが可能な付属品。 杖入れやシートベルト、転倒防止バー等の種類がある。 |
| 特殊寝台 | 一般的には介護ベッドと呼ばれることが多い。 背上げや高さ調節の機能を持ったベッドであるため、被介護者の暮らしやすさの改善、介護者の介護にかかる負担の軽減が可能。 |
| 特殊寝台付属品 | 手すりやサイドレールなど、特殊寝台に取り付けが可能な付属品。 起居動作の支えや転落防止などの効果がある。 |
| 床ずれ防止用具 | 床ずれを防止するためのマットレス。 1か所にかかる負担を分散させることで、床ずれの防止に効果的。 |
| 体位変換機 | 寝返りなどの体位変換をサポートをする福祉用具。 クッションタイプやシートタイプのものがあり、体位変換を行いやすくすることで床ずれなどの防止が見込める。 |
| 手すり | 工事を伴わない、設置型の手すり。 起居動作や歩行が安定しない高齢者の方の生活のサポートが可能。 |
| スロープ | 工事を伴わない、設置型のスロープ。 段差部分に設置することで、生活環境の改善や事故防止等の効果が見込める。 |
| 歩行器 | 転倒しやすい状態にある高齢者の方の歩行を補助する福祉用具。 両腕で体重を支えることができるため、脚にかかる負担や痛みを軽減する等の効果がある。 |
| 歩行補助杖 | 歩行が安定しない状態にある高齢者の方の歩行を支える福祉用具。 歩行器同様、脚にかかる負担を軽減することが可能。 |
| 認知症老人徘徊感知機器 | 認知症に見られる徘徊の初期動作を感知するための機器。 ベッドの周りに置くことで、「ベッドから降りる」「部屋から出る」といった徘徊の兆候を感知することができるため、徘徊や転倒などを事前に防ぐ等の効果が見込める。 |
| 移動用リフト | 自力で起き上がることが困難な方の起き上がりや車いすへの移乗をサポートする福祉用具。 被介護者の身体を持ち上げることができるため、介護者にかかる身体的負担の軽減も可能。 |
| 自動排せつ処理装置 | 自力でトイレまで歩くのが困難な方の排せつをサポートする福祉用具。 レシーバー部分に排尿することで、レシーバーとつながっている本体に尿が吸引される。 |
また、購入可能な福祉用具は以下の通りです。
| 福祉用具 | 用途 |
|---|---|
| 腰かけ便座 | 和式のトイレや、洋式のトイレに設置する福祉用具。 座位や起居動作の安定などの効果が見込める。 |
| 自動排せつ処理装置の 交換可能部品 |
前述の自動排せつ処理装置の交換可能部分の部品。 尿タンクやホース、レシーバーなどが該当する。 |
| 入浴補助用具 | 自宅の浴室に設置する手すりやすのこなどの福祉用具。 設置することで、入浴時の動作の安定や転倒の防止などの効果が見込める。 |
| 簡易浴槽 | 居室などで簡単に入浴ができるための福祉用具。 居室に設置可能であるため、自宅の浴室までの移動が困難な方の入浴をサポート可能。 |
| 移動用リフトの吊り具部分 | 前述の移動用リフトの吊り具部分。 脚分離型やシート型などの種類があり、トイレや入浴など用途に分けて取り換えることが可能。 |
このように、要介護2の方であれば多くの福祉用具をレンタル・購入することができます。
要介護者本人の身体状況を考慮したうえで適切な福祉用具をレンタル・購入し、介護の負担を軽減しましょう。
要介護2で利用できるサービスを理解し、適切に利用しよう
ここまで、要介護2で受けられるサービスやその内容、利用方法等を紹介してきました。
介護保険サービスを適切に利用することで、要介護者本人の生活を支えるだけでなく、ご家族の負担も軽減することができます。
適切な介護保険サービスを利用するには、サービスについて知っておくことが何よりも重要です。
利用可能なサービスやその内容を理解したうえで、要介護者本人の希望や介護状況、またご家族の方の身体的・精神的負担を考慮し、必要なサービスを利用しましょう。
介護保険サービスを適切に利用することで、要介護者本人の生活を支えるだけでなく、ご家族の負担も軽減することができます。





