老人ホームでは集団で生活することが多いため、感染症が蔓延するリスクがあります。
実際、老人ホームでは、どのような感染症が流行りやすいのか、どのような予防・対策があるのか気になるところですよね。もし家族を老人ホームに預けるとなると、感染症対策がしっかりした老人ホームでないと預けるのが不安でしょう。
そこでこの記事では、老人ホームで気を付けるべき感染症の基本的情報と予防、対策について解説します。感染症対策が万全な老人ホームを見分けられるよう、ぜひ役立ててください。
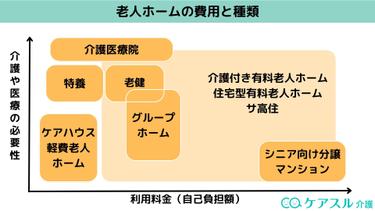
老人ホームで気をつけるべき感染症について
老人ホームで広がりやすい感染症はいくつかありますが、代表例として以下の感染症があります。
〇感染力が高く集団感染する感染症
新型コロナウィルス、インフルエンザ、ノロウィルス、結核など
〇健康的な人に感染しにくい感染症
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、緑膿菌感染症など
〇血液・体液から感染する感染症
肝炎(B型、C型)、HIVなど
感染症対策がしっかりとしている老人ホームを探しているという方はケアスル 介護で探すのがおすすめです。入居相談員にその場で条件に合った施設を提案してもらえるので、初めての施設探しでもスムーズに探すことが出来ます。
幅広い選択肢から自分に合った老人ホームを探したいという方はぜひ利用してみてください。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
老人ホームでの感染症は感染経路に注意が必要
感染症の感染経路は「接触感染」「飛沫感染」「空気感染」「血液媒介感染」と大きく4つに分類できます。それぞれ、経路と予防対策を解説するので、老人ホームを検討する際に役立てましょう。
物を介する接触感染
接触感染とは、ウィルスや細菌がついている物に直接触れたり、触れた物を通して自分自身に付着することを指します。
生活の中で気をつけるべき点として、他人とタオルを共有しないこと、コップや机に置いてある物を確認せず安易に使用したり、不用意に手で触れないことが大切です。
接触感染をしやすい代表的な感染症は「水虫」。スリッパやタオルの共有から感染しやすい感染症です。対策としては、周りの物に安易に触れないことだけでなく、消毒してあるかどうかの確認がポイントとなります。
咳やくしゃみが原因の飛沫感染
飛沫感染とは感染症を持っている人が咳やくしゃみなどでウィルスや細菌を外に飛ばし、それが他者の体内に入って感染することを指します。
代表的な感染症に、インフルエンザや肺炎が挙げられます。
食事やイベントなどの際には人が集まるので、どれだけ気をつけようが飛沫を浴びる危険性は消えません。
感染症を患っている人は咳やくしゃみの頻度が多いので、適度な距離を保つことが大切です。場合によっては人が集まる場所にできる限り集まらないことも必要でしょう。
密閉した空間での空気感染
空気感染はウイルスや細菌の水分が蒸発して細かい微粒子となり、空気中に漂い、そのウイルスや細菌を体に吸い込んでしまうことを指します。
密閉した空間だと空気中のウイルスや細菌を吸い込んでしまうリスクは高くなります。またマスクを着用していようがウイルスと細菌はマスクを通り抜けるので、あまり効果を見込めないでしょう。
空気感染を予防するための高機能なマスクも存在しますが、一般的な施設で取り入れられていることは少ないです。空気感染の予防はマスクの着用も大切ですが、定期的な部屋の換気が大切です。
他者の血液が感染源となる血液媒介感染
血液媒介感染症は血液に含まれる感染源が他者の体内に入ることで感染する感染症です。B型肝炎やC型肝炎、そしてHIVが代表例として挙げられます。
基本的に輸血や針の使用が感染原因になるので、介護施設では発生頻度が低いと考えられています。
しかし、施設によっては、採血や血糖値測定を行う場合もあるので、清潔な機材で対応してくれているのかが大切です。
老人ホームでできる感染症予防とは
老人ホームでできる感染症予防には何があるのでしょうか。感染症を予防するためのポイントを解説します。
基本的な感染症対策
日常生活に取り入れられる効果が高い感染症対策は、「しっかりとした手洗い」と「日常的にマスク着用」です。
ウイルスや細菌は知らないうちに手に付着していることが多いです。定期的に手を洗う、もしくはアルコール消毒することで感染リスクを大幅に抑えられるでしょう。
また手洗いのタイミングは重要です。一つの指標として食事前、排泄後は欠かさず手洗いを行うことをおすすめします。
そのほか、集団の中で過ごすのであれば他人へ感染させないと言う意味合いでもマスクの着用が効果的です。特に飛沫感染を抑える意味ではマスク着用は効果が高い予防となるでしょう。
大勢の人が集まる場所では、人との距離を取ることも大切ですが、飛沫が体の中に入らないようにマスクでの予防も大切です。
マスクの効果を期待し過ぎるのも危険ですが、日常的なマスクの着用は予防策になるでしょう。
健康管理と免疫力の向上
感染症対策には健康管理や予防接種も大切です。日々の健康管理や免疫力を高めて予防するポイントについて解説します。
日常生活での体調管理
感染症対策はウイルスや細菌が体に入らないように気をつけることが大切ですが、健康な体作りも大切です。
免疫力が落ちていると、すぐに感染症を発症してしまうので、日常的に健康な体づくり、栄養の摂取、そして睡眠をしっかり摂るようにしましょう。
免疫向上のための予防接種
免疫を高める方法として予防接種も効果的です。どうしても健康的な体作りだけでは予防できないこともあるので、上手に予防接種を利用することもおすすめします。
代表的な予防接種としてはインフルエンザが挙げられます。
老人ホームにおける感染症対策事例
それでは老人ホームにおける感染症の予防対策事例をピックアップして解説します。どのような対策を実施すれば感染症を予防できるのか参考にしてください。
事例①「入館時の消毒、手洗い、検温」
施設の入館時には手洗い検温を実施し、外部から細菌やウイルスを持ち込まないように注意する方法の採用が感染症対策として効果的です。
入居者や介護者はもちろん、面会に来たご家族の方や、施設に立ち寄る業者などにも義務化。
施設内だけを清潔にしていても感染症は抑えられないので、細かな徹底を行うことで、入居者の健康を守っている施設もあります。
事例②「接触場所の消毒」
施設内の人が接触するであろう部分の定期的な消毒が感染症対策として効果的です。例えばテーブル、ドアノブ、トイレ、エレベーターのスイッチなどが挙げられます。
接触感染の予防対策を狙いとしている対策事例です。
事例③「排泄物と嘔吐物の処置」
感染症の中でも胃腸炎は、人の排泄物や嘔吐物から感染が広がります。それゆえに迅速、適切な処置が必要です。
処置する際には手袋、エプロンなどの着用はもちろん消毒を欠かさないようにする必要があるでしょう。
排泄物や嘔吐物の処置一つで感染対策の高い効果が得られるので重要なポイントです。
事例④「換気や湿度管理」
ウイルスや細菌は知らないうちに部屋に広がることがあるので定期的な換気が必要です。またウイルスや細菌が好む湿度の状態を保たないように湿度管理をすることで感染拡大を避けられるでしょう。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
国が定める感染症対策マニュアルを解説
厚生労働省は介護施設における「感染症対策ガイドライン」を用意しており、基本的な対策についてまとめています。
介護施設はこのマニュアルに沿って対策を遂行する必要があるので、その内容を知れば介護施設での感染症対策を理解できますよ。
正しい手洗い方法
「感染症対策ガイドライン」で推奨されている手洗い方法について解説します。ガイドラインで推奨される方法を押さえることで感染症予防に効果の高い「手洗い」ができるようになります。しっかりと内容を理解しましょう。
◆正しい手洗い
- 初めに水で手を濡らし、石けんを手に取ります。
- 石けんをよく泡立てながら、手のひらを洗います。
- 手の甲を伸ばすように洗います。
- 指先・爪の間を念入りに洗います。
- 指の間を洗います。
- 親指をねじりながら洗います。
- 手首を洗います。
- 流水で石けんと汚れを洗い流します。
- ペーパータオルでしっかりと、水分を拭き取ります。
咳エチケット
咳エチケットの基本としてマスクを着用する必要があります。またティッシュ・ハンカチ等で口や鼻を覆ったり、こまめなうがいや手洗いを行うことも大切でしょう。
日常生活での咳エチケットに気を付けることで飛沫感染の防止につながるので感染症対策として効果的です。
◆咳エチケットの基本
- マスクを着用する
- ティッシュ・ハンカチ等で口や鼻を覆う
- こまめなうがいや手洗いを行う
インフルエンザ対策
インフルエンザ対策はできる限りワクチン接種をすることが望ましいです。感染したかどうかの指標として、急な発熱・悪寒、全身症状(頭痛、腰痛、筋肉痛など)、鼻水・咳、腹痛・嘔吐などがある場合、インフルエンザの疑いがあります。仮に疑いがある場合、個室対応などの検討が必要になります。
またワクチン接種することで、最悪インフルエンザを発症したとしても軽症で済むので安心できるでしょう。
◆平常時の予防
- 入居者と職員に必要性や有効性、副反応について十分説明したうえでワクチン接種が受けられるよう配慮する
- 入居者や面会者で咳をしている人にはマスクを着用してもらい、咳エチケットを守ってもらう
- 休養・バランスの良い食事とこまめな水分補給
ノロウィルス対策
ノロウイルスの疑うべき症状として、噴射するような激しい嘔吐、下痢、吐き気などが挙げられます。施設内でノロウイルスの疑いがある場合は、嘔吐物、排泄物の処理に注意するとともに換気なども忘れず行う必要があります。それではノロウイルス対策のポイントについて解説します。
◆平常時の予防
- 職員は配膳前、食事介助全での手洗いを行う
- 施設内で手に触れる場所(手すり、ドアノブ、テーブル等)の清拭をこころがける
日常生活において食事前の手洗い、施設内での清掃など基本的な活動が行き届くことで効果の高い感染症予防に繋がるでしょう。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
感染症対策がとられた安心できる老人ホームを探そう
今回は、老人ホームにおいて気を付けるべき感染症について解説しました。感染症はウイルスや細菌が体内に入ることで発症します。
予防対策として、病原体を施設内に運び込まないこと、そして施設内で感染拡大させないための消毒や定期的な換気が必要です。
厚生労働省が勧める感染マニュアルを真面目に取り組む老人ホームであれば、家族を安心して任せられるので、老人ホーム探しの際は、施設がどのような対策を取っているのかをヒアリングするのも良いかもしれませんね。
老人ホームで発生しやすい感染症としてはインフルエンザや肺炎などが挙げられます。空気感染、飛沫感染、接触感染での感染経路のリスクが高いので、それらに対する対策をいかに取っているかがポイントとなります。詳しくはこちらをご覧ください。
老人ホームで感染症が蔓延した場合には、ガイドラインでしっかりと対応がまとめられています。まずは発生状況の把握をした上、感染拡大の防止に努めます。そして医療処置、行政への報告という流れになります。対処が困難な場合は保健所や医療機関などの強力も仰げます。詳しくはこちらをご覧ください。





