老人ホームを探している方の中には、施設内でいじめが発生したニュースなどをご覧になった方もいるかと思われます。
老人ホームに限らず、人が集団で生活していくため、いじめや人間関係のトラブルはどうしても発生してしまいます。
そのため、老人ホームを選ぶ際には入居者や介護職員の人間関係が良好である施設から探すことが大切です。
本記事では、老人ホームで起こったいじめの事例を紹介したうえで、人間関係の面で見学時に確認しておくべきポイントについて解説します。
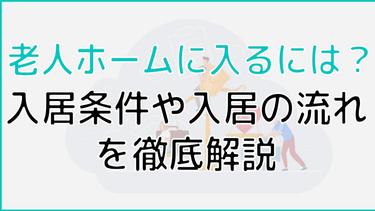
老人ホームで起こるいじめの事例
老人ホームで起こるいじめやトラブルとして、大きく分けて2つのケースが想定されます。
- 入居者同士のいじめ
- 介護職員によるいじめ
老人ホームに限らず、集団生活を送る場では、価値観や相性の違いにより、人間関係のトラブルに発展してしまうことがあります。事例とともに解説していきます。
入居者同士のいじめ
少しでも楽しい話ができたらと思いましたが、いきなり「入居されたばかりよね、それならAさんとBさんには気をつけてね。悪口言いふらすから。あと、Cさんはセクハラしてくるわよ」と次から次へと、入居者の陰口のオンパレード。(”幻冬舎ゴールドオンライン”より抜粋)
老人ホームにおける老人のいじめを予防するための要因を調査した「老人病院と特別養護老人ホームにおけるいじめの実態」によると、特別養護老人ホームにおけるいじめられ意識の経験は29.4%と報告しています。
老人ホーム内で起こった入居者同士のいじめとして、ののしりや暴力、物を盗まれたなどの被害があったとされています。
このようないじめは老人ホームだから起きるわけではありません。他人と集団行動を送るといった「ストレスの多い環境」では、不満やストレスのはけ口として他者へ攻撃してしまうことが多いです。
学校でのいじめと異なり、ご高齢の方同士でのいじめなどは社会問題として取り上げられていないため、予防対策や相談先も少ないという実態があります。
介護職員によるいじめ
女性は同ホームに入所していた2019年12月から20年1月までの間、介護職員だった男女4人から、車椅子をぶつけられたり、首と腕をつかんでベッドに移動させられたりする暴行を計7回受けたとされる。(”朝日新聞 2021年7月10日の記事”より抜粋)
厚生労働省の調査報告書によると、2021年における養介護施設従事者等による高齢者虐待に関する相談件数は2,390件あったと発表しています。
ニュースなどでご覧になった方もいると思われますが、残念ながら介護職員からいじめやトラブルが絶対に起こらないとは言い難いです。
一方で、養護者(高齢者の介護を行う家族や親族)による高齢者虐待に関する相談件数も36,378件あると報告しています。
在宅介護に限界を迎えてしまい、暴力や介護放棄などにつながるケースもまた多いのも事実です。介護はそれほど大変なものという認識を持っていただき、安心して預けられる施設を選ぶことが大切です。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
なぜ老人ホームでいじめは起きてしまうのか?
入居者同士のいじめは、入居者の孤立感や孤独感が大きな原因とされています。
老人ホームで家族と離れて生活している、面会になかなか来てくれないなど、本人のさびしさや辛さが他の入居者へのいじめにつながっていることが多いです。
つまり、老人ホームでいじめを起こさないためにも、利用者の家族の協力が不可欠です。度々面会に訪れる、介護職員の人柄や仕事の様子を見ておくことで、トラブルを回避できるかもしれません。
また、施設内の人間関係が良好であるか、施設見学や体験入居を通じて把握することも大切です。設備が整っているなど短絡的に決めてしまうと入居後に後悔してしまう恐れがあります。
次章では、施設見学時に確認しておくべきポイントについて解説していきます。
「老人ホームを探しているけれども、見学時に何を見たらいいかわからない…」という方は、ケアスル介護に相談してみることがおすすめです。
ケアスル介護では、入居相談員が施設ごとに実施するサービスやアクセス情報などをしっかりと把握した上で、ご本人様に最適な施設をご紹介しています。
「身体状況に最適なサービスを受けながら、安心して暮らせる施設を選びたい」という方は、まずは無料相談からご利用ください。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
後悔しないために施設見学時に確認すべきポイント
老人ホームに入居後にトラブルやいじめを避けるためにも、施設見学時には以下の点を確認しておきましょう。
- 入居者や介護職員の様子
- 入居者同士のトラブル事例
- 施設外とかかわり
- 施設内の監視カメラの有無
- ユニットケアは人間関係が濃い
施設見学時に入居者や施設職員の人間関係が良好であるか把握することで、入居後の後悔を防ぐことにつながります。上記について詳しく解説していきます。
入居者や介護職員の様子
施設見学時は入居者や介護職員の様子を重点的に確認することが大切です。
利用者にとって、毎日顔を合わせることになる入居者や介護職員が親しみやすい人であるかは、入居後の生活に大きく影響を与えます。ケアスル介護が行ったアンケートにおいても、スタッフや入居者の雰囲気を決め手に施設を選んだ人は多いです。
入居者や介護職員の様子はホームページや資料のみで判断することが難しいです。見学時は食事の時間やレクリエーションの様子など、なるべく人が集まる時間帯を見学することで入居後のミスマッチを防ぐことができるでしょう。
なお、施設見学時は普段よりも丁寧な対応をしている可能性も考慮しましょう。老人ホームとしても空室率を下げるために、施設見学時にはより丁寧に対応してもらえるケースも少なくありません。
可能であれば、体験入居などで長期間入居してみて、施設の雰囲気や生活イメージ、他の入居者の様子などを把握することをおすすめします。
入居者同士のトラブル事例
過去に入居者同士でトラブルが起こっていないか、施設職員に確認しましょう。
過去にトラブルが一度もないという施設は、新築でもない限り怪しいです。トラブルがあったことを隠そうとしたり、うまく答えられないとなると、入居者同士のいじめなどへの関心が薄い可能性があります。
具体的な事例と対処方法、また再発防止のための対策などを職員から伺うことができれば、入居者に対する見守りは勿論、施設内で情報共有もしっかりしていると判断できます。
施設外とかかわり
外部との関りの少ない閉鎖的な老人ホームだと、いじめが発生しても気づかれにくい場合があります。
例えば、外部と連絡が取りずらい(携帯電話の持ち込みを過度に制限している、公衆電話の有無)、外出が気軽にしずらいなど、施設が閉鎖的であるほどいじめなどが発生しやすい傾向にあります。
一方で、地域の住民と積極的に交流している、家族懇親会などが頻繁に行われているなど、外部や入居者家族と積極的に関わっている施設であれば、いじめなどが起きる可能性は低いです。
見学時に他の入居者を見せない、見学時間が過度に限られているなど、何か違和を感じることがあれば、施設職員に直接聞いてみたり、ネットの口コミなどを確認してみるのも良いでしょう。
施設内の監視カメラの有無
施設内に監視カメラなどが設置されていれば、トラブルやいじめを予防する抑止力になり得ます。
2016年に起きた老人ホームでの事件以降、厚生労働省は施設内に防犯・監視カメラを設置することを推奨しています。入居者同士のトラブルや事故防止の役割も果たすため、施設内にカメラを設置している老人ホームならば安心して過ごすことができます。
ただし、プライバシーの問題もあるため、全ての施設や個室内に監視カメラがあるわけではありません。基本的には防犯を目的として設置していますが、施設内でのトラブル防止の役割もあると覚えておきましょう。
参照:厚生労働省「社会福祉施設等における防犯に係る安全の確保について(通知)」
ユニットケアは人間関係が濃い
一般的な老人ホームと異なり、ユニットケアを採択している施設は人間関係が濃いという特徴があります。
ユニットケアとは、入居者一人ひとりが自分らしい生活を送るために、5~9人程度の少人数で共同生活を送ります。施設内は個室とリビングやキッチンなどの共有スペースに分かれ、家事などを分担しながら生活していきます。
少人数体制を取っているため入居者同士でコミュニケーションが取りやすい反面、入居者同士でトラブルが起きてしまうと気まずい思いをしなければなりません。場合によっては他のユニットに転居することもあります。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
老人ホームを選ぶときは必ず施設を見学しよう
本記事では、老人ホームでおきたいじめについて解説していきました。
残念ながら老人ホーム内では、入居者同士や介護職員によるいじめが全くないとは言い切れません。しかし、それだけ介護が大変なことであるのも事実です。
入居に関して家族にどれくらい関わることができるかが大切です。親を安心して任せることができる施設であるかしっかり確認しましょう。また、入居後も施設職員に任せっきりにせず、頻繁に面会に訪れて顔を見せに行きましょう。
実際にトラブルがあれば、まずは施設職員やケアマネジャーに相談しましょう。改善が見られなければ、自治体の介護保険課の相談窓口や、都道府県の国民健康保険団体連合会に相談しましょう。詳しくはこちらをご覧ください。
高齢者への虐待防止や保護を目的に「高齢者虐待防止法」が2005年に制定されました。この法律では、虐待を受けていると疑われる高齢者を発見した際に、市区町村への相談を義務化しています。詳しくはこちらをご覧ください。




