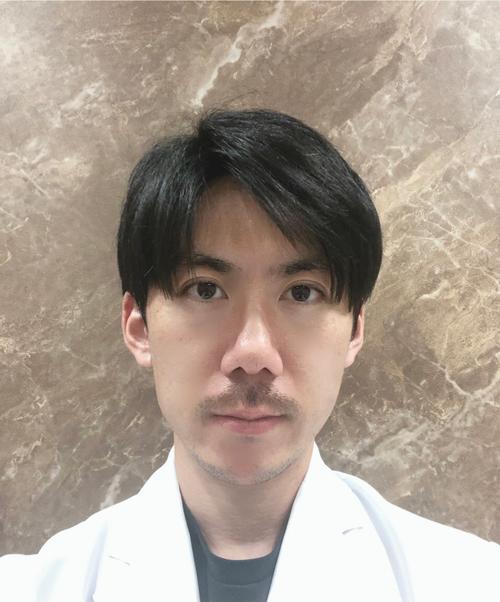「介護中の高齢者が毎日眠ったように過ごしているので、もしかしたら傾眠かもしれない…」とお悩みの方は多いのではないでしょうか。
ここでは、傾眠の症状や主な原因・要因、傾眠による問題点などについて詳しくご紹介していきます。
傾眠傾向にある高齢者の介護にお悩みの方は、この記事を最後までお読みいただき、傾眠に関する理解と適切な対処法を日々の生活の中でお役立てください。
傾眠傾向とはどのような症状?
日中に目を閉じて、眠ったように過ごしている高齢者は多いです。しかし、単なる居眠りではなく、傾眠によるものかもしれません。
そこで、傾眠とはどのような症状なのか詳しく解説するので、確認してみましょう。
傾眠傾向は高齢者に多い!軽度の意識障害
傾眠とは一見すると眠っているように見えますが、声を掛けたり、肩を叩いたりすると意識を取り戻すのが特徴です。
ただし、せっかく覚醒させても外部からの刺激がなければ、再度傾眠に陥ってしまうので注意してください。
また、傾眠は意識障害の一つであり、最も軽度です。進行するにつれて、段々外部からの刺激に対して反応が鈍くなります。
傾眠傾向と居眠りは違うので注意
傾眠は寝不足による居眠りとは異なるものです。しかし、目を閉じて過ごしている姿を見ても、外見上で判断するのは簡単ではありません。
そこで、それぞれを見分ける方法として、意識を取り戻した後の状態を観察しましょう。傾眠の場合、以下のような特徴があります。
- 自分のいる場所や時間、起きる前に何をしていたのかなど記憶がない
- 注意力にかけて無気力になる
傾眠の症状が現れているにもかかわらず、放置してしまうと、症状が重くなる可能性があるので注意してください。
傾眠傾向と終末期の関係
多くの終末期の方は、亡くなる数週間の間に意識レベルが徐々に低下していきます。
眠って過ごすことで無駄な体力を使わずに済み、生命期間が延長するだけでなく、終末期における苦痛が和らぎます。
しかし、介護中の高齢者が日中に目を閉じて過ごしているからといって、終末期による傾眠であるとは限りません。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
傾眠傾向に陥る主な8つの原因・要因
高齢者が傾眠に陥る主な原因としては以下の8つが挙げられます。
- 認知症による昼夜逆転
- 加齢にともなう体力の低下
- 脱水症状
- 内科的疾患による発熱
- 頭部打撲などによって生じる慢性硬膜下血腫
- 抗てんかん薬など薬の副作用
- 食後に起こりやすい食事性低血圧
それぞれについて詳しく解説して行きます。
認知症による昼夜逆転
認知症によって生活習慣が乱れてしまい、昼夜逆転生活に陥ってしまう方は少なくありません。
夜間の睡眠が不足すると昼間に眠気が強まり、外部からの刺激への反応が鈍くなります。夜間にぐっすりと眠れるように、昼間の活動量を増やすように促しましょう。
また、認知症の初期症状の一つにアパシー(無気力状態)があります。アパシーの方は、身の回りのできごとに対して意欲を失い、外部からの刺激に脳が興奮しにくくなります。
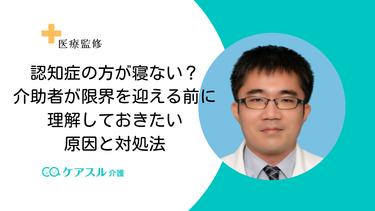
加齢にともなう体力の低下
加齢にともない体力が低下すると、神経伝達機能が低下します。
外部からの刺激が脳までスムーズに伝えられず、刺激に対して反応が鈍くなるため、意識障害として傾眠が起こります。
日中に、うつらうつらする時間や頻度が増えた程度であれば、大きな問題とはならない場合が多いでしょう。
しかし、眠ったように過ごす時間が明らかに増えた場合、ほかの要因も考えられます。安易に考えず、注意深く観察することが大切です。
脱水症状
脱水症状は意識が朦朧として、傾眠として症状が現れる可能性があります。
特に高齢者は、喉の渇きを感じにくいうえに、体の中に充分に水分をため込んでおく機能が低下しがちです。脱水症状は夏場によく起こると思われがちですが、実際は冬場も少なくありません。
暖房器具で室温が上がっているだけでなく、季節感が失われて衣類を重ねて着こんでいる高齢者は多く、脱水に陥りやすくなります。
高齢者を介護している家族は、意識してこまめに水分を摂るようにしましょう。
内科的疾患による発熱
肝臓や腎臓といった代謝に関わる臓器に何かしらの異常が生じている場合も、傾眠が起こりやすくなります。
人間は体内で炎症や発熱が起こると、体を休めようとする働きがあるためです。
元々肝臓や腎臓の機能が低下している方が傾眠に陥った場合、疾患が原因で発熱しているおそれがあるので、普段から体温や脈拍、血圧などの健康管理に気をつけましょう。
頭部打撲などによって生じる慢性硬膜下血腫
硬膜下血腫とは、ベッドや車いすからのずり落ち、転倒などの際に頭を打ち、硬膜と脳の間に血種ができてしまう疾患です。
高齢者は血管が脆くなっており、軽く頭をぶつけた程度でも出血を起こしやすいので注意しましょう。
中でも硬膜下血腫は、時間をかけて血種が大きくなるため、頭を打って1〜2か月程度経過してから、さまざまな症状が現れます。
血種が大きくなるにつれて傾眠が現れ始め、次第に頭痛や歩行障害といった症状まで発展するケースが多いです。
早い段階での外科手術が必要となるため、傾眠以外の症状も現れていないか、注意深く観察しましょう。
抗てんかん薬など薬の副作用
薬の中には、副作用として傾眠を引き起こしやすいものがあるので、使用する前に医師や薬剤師に副作用について確認しておきましょう。
副作用として傾眠を起こしやすい薬は以下の通りです。
- 認知症の薬
- 抗てんかん薬
- 抗ヒスタミン薬が含まれている市販の風邪薬や花粉症の薬
風邪やアレルギーの症状が出た際は、抗ヒスタミン薬の入っていないものを選ぶとよいでしょう。
食後に起こりやすい食事性低血圧
食事性低血圧とは、食事がきっかけとなって血圧が低下する状態のことです。食後に眠気や怠さを感じるようであれば、傾眠の原因は食事性低血圧かもしれません。
特に食事性低血圧が起こりやすい疾患があるので、注意しましょう。
- パーキンソン病
- アルツハイマー病
- 高血圧や糖尿病
また、降圧薬や利尿薬には血圧が下がる効能があるため、食後に薬を内服することで血圧が下がり、傾眠に陥る可能性があります。
食事と傾眠に関係はないか、日中の様子について気を付けてみましょう。
睡眠障害やうつによる過眠症
傾眠とよく似た症状に、「過眠症」と呼ばれる睡眠障害があるので注意しましょう。中枢神経系の機能異常が原因とされています。
過眠症とは夜間充分な睡眠をとっているにもかかわらず、日中強い眠気に襲われる疾患です。
食事中や歩行中、発作的に強い眠気に襲われて眠ってしまう「ナルコレプシー」も過眠症の一つとされています。
また、うつ病と診断された方の中には、日中傾眠が強まる方がいます。うつ病の治療薬である「抗うつ薬」や「抗不安薬」などの服用によって、傾眠に陥る場合もあります。
傾眠傾向が続くとどうなる?傾眠による問題点
介護中の高齢者が傾眠に陥ると、介護者の負担が目に見えて増えるわけではないので、そのまま放置してしまう場合があります。
しかし、傾眠を改善せずにいると、高齢者の健康にさまざまな問題点を生じます。
そこで、傾眠が続くとどうなるのか、傾眠による問題点について詳しく解説していくので確認してみましょう。
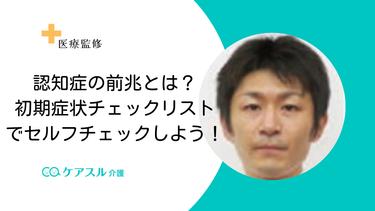
食事中に誤嚥を起こしやすい
傾眠の高齢者で注意したいのは、誤嚥性肺炎のリスクです。意識がはっきりしていない状態で食事を摂ると、しっかり噛まずに飲み込もうとしてしまいます。
特に、さらっとしたとろみのない汁物などは、誤って肺や気管の方へ流れ込む誤嚥を起こしやすいので注意してください。
誤嚥性肺炎を繰り返すと、口から食べ物を摂るのが難しくなり、胃ろうの造設や静脈栄養といった医療的ケアの導入を検討しなければなりません。
車いすからの転落や歩行時の転倒などの事故
車いすに腰かけている際に傾眠に陥ると、姿勢が崩れ、車いすからずり落ちてしまうケースは少なくありません。
突然目を覚ましてバランスが崩れてしまい、車いすから転落する可能性もあります。
車いすに座っている最中は目を離さないように気を付け、体のバランスが崩れている場合は体の向きや姿勢を整えましょう。
また、傾眠時は横になって休んでもらうと安心です。ただし、歩行中に突然倒れこむ危険性があるので、移動介助はしっかり覚醒した状態で行ってください。
食欲の低下による栄養失調や体重低下
傾眠の高齢者は、意欲と共に食欲も低下し、食事の摂取量が少なくなります。栄養失調や体重減少といった健康リスクが生じる可能性があるので注意してください。
栄養失調や体重減少は筋力が低下し、さらに意欲や活動量が減少する原因です。
意識がはっきりしていない状態での食事は誤嚥性肺炎のリスクが高まるため、意識がはっきりとしている状態で食事を摂るように促しましょう。
錯覚や妄想などのせん妄
せん妄とは、認知症の周辺症状の一つで、時間や場所が分からない見当識障害や、妄想、幻覚、幻聴といった症状のことです。
傾眠の進行にともない、せん妄のような症状を起こす場合があります。せん妄の症状が現れることで、ショックを受けてしまう家族もいますが、冷静に対処しましょう。
傾眠がちだった高齢者に妄想や幻聴といった症状が現れたら、かかりつけの医療機関を受診し、医師の診断を仰いでください。
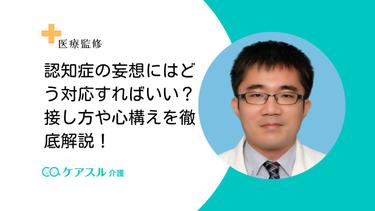
傾眠傾向の適切な対策とは?おすすめの対処法
介護中の高齢者に傾眠がみられたら、症状が進行してさまざまな健康リスクが生じる前に、適切な対処法が必要となります。
そこで、傾眠の適切な対策として、ぜひ取り入れたい対処法を詳しくご紹介していきます。どのように対処すればよいのか、お悩みの方は参考にしてください。
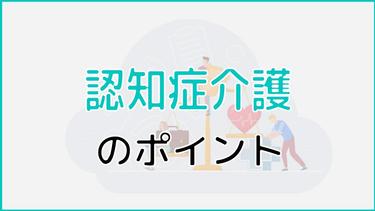
話しかけてコミュニケーションをとる
傾眠がちの高齢者には、日中できるだけ話しかけてコミュニケーションを摂るように心がけてください。会話の機会を増やすと、外部からの刺激によって傾眠に陥りにくくなります。
また、積極的にコミュニケーションをとることで、脳の働きが活発になり、意識もはっきりしやすくなります。
なかなか会話が続かず、再度目を閉じて傾眠に入ってしまう場合、昔の思い出話や趣味の話など、本人が興味を持てそうな話題を選ぶとよいでしょう。
日中は散歩などで身体を動かす
天気のよい日は、ウォーキングや散歩に誘ってみましょう。積極的に体を動かすことで多くの刺激が得られ、傾眠を防ぐ以外にも、さまざまな健康効果を期待できます。
- 外部からの刺激によって意識をはっきりと覚醒しやすくなる
- 風の匂いや植物などから季節の変化を感じられ、気分転換になる
- 体を動かすことで全身の血行が促され、脳の活性化につながる
また、活動量が増えることで筋力や体力の維持にも役立ちます。心地よい疲労感によって夜間の睡眠の質の向上し、日中の覚醒にもつながります。
こまめに水分を補給する
適切な水分補給は、脱水による傾眠の対策として有効です。ただし、一度に大量の水を飲んでも大部分が尿として排出されてしまいます。
こまめに少量ずつ摂取し、起床時や入浴前後など、水分を補給するタイミングをあらかじめ決めておくとよいでしょう。
高齢者は喉が渇いている自覚がなく、容易に脱水に陥りやすくなります。水分補給は本人任せにせず、周囲が声をかけて水分摂取を促すと安心です。
薬の量を調整してもらう
薬の副作用による傾眠が疑われる場合、医師に相談して薬の量の調整や、内容の見直しについて相談しましょう。
しかし、分かりやすい伝え方を心がけなければ、傾眠は高齢者によくあるものだとして、医師に見落とされてしまう可能性もあります。
傾眠と薬の因果関係について、「服用後〇時間後に傾眠の症状がみられた」と具体的な記録を残しておくことが大切です。
また、明らかにこれまでとは異なる症状の傾向がみられた場合、医師以外に薬剤師にも相談してセカンドオピニオンを仰いでください。
昼寝は短時間で済ませて生活リズムを整える
生活リズムの昼夜逆転が傾眠の原因となっている場合、睡眠の覚醒のリズムを整えることで、日中の覚醒につなげられます。
どうしても日中の眠気がひどく傾眠がちになる場合、思いきって決まった時間に昼寝を摂るのもよいでしょう。
1日30分程度の昼寝は日中の覚醒を高め、夜間の睡眠には影響を及ぼしにくいとされています。
ただし、長時間の昼寝や遅い時間帯の昼寝は、夜間の睡眠の質を悪くさせ、日中の傾眠が改善されにくくなるため、注意してください。
誤嚥予防のため食事の内容を見直す
意識状態がはっきりとしていない状態での食事は、誤嚥性肺炎のリスクを高めます。長時間の食事は、想像している以上に高齢者にとって疲労をともなうものです。
少量でも満足度の高い食事に切り替えたり、分食にして無理なく食事を摂れるように工夫しましょう。
また、食事性低血圧によって傾眠に陥っている高齢者は、食事前後での血圧の変動を抑えることが大切です。炭水化物を減らし、ゆっくり食事を摂るように心がけましょう。
安心して日常生活を送れるようにサポートする
高齢者本人に傾眠の自覚や認識がなく、「ただ居眠りしているだけ」と捉えている場合があります。
周囲の心配に対して「大げさだ」として、受診を拒否するケースも少なくありません。受診を無理強いしても、関係性がこじれてしまう可能性も考えられます。
介護中の高齢者の傾眠は、加齢にともなう変化の一つとして捉え、家族にできる適切なケアを行いながら見守るのも対処法の一つです。
高齢者が安心して日常生活を送れるように、家族ができる範囲でサポートしましょう。
傾眠傾向が改善されない場合は医療機関を受診する
1日中傾眠に陥っていたり、対策を講じても改善されなかったりした場合、医療機関の受診を検討してください。
認知症の疑いや疾患が原因である可能性もあるため、できるだけ早いタイミングで医師に診察してもらうことが大切です。
受診をきっかけに食事や睡眠といった生活習慣の改善につながるケースもあります。まずはかかりつけ医に相談し、必要に応じて専門の病院やクリニックを紹介してもらいましょう。
高齢者に多い傾眠傾向は生活習慣や食事習慣の見直しで対策しよう
高齢者に多い傾眠は、認知症にともなう昼夜逆転生活や加齢にともなう体力の低下などが原因とされています。
生活習慣や食事習慣を見直すことで、生活リズムが整い、傾眠の対策として役立つでしょう。
ただし、適切な対策をしているにもかかわらず、なかなか傾眠が改善されない場合、思いがけない疾患や原因によって傾眠が起きている可能性もあります。
中には早めに治療を開始した方がよい疾患もあるため、異変を感じたら医療機関の受診も検討してください。
傾眠によって日中の活動量が低下してしまうと、筋力や認知機能が低下する原因です。昼寝は1日15~30分程度にとどめ、できるだけ起きていてもらい、活動量を増やしましょう。日中の活動量が増えることで、睡眠の質が向上し、夜間ぐっすり眠れるようになります。詳しくはこちらをご覧ください。
あらかじめデイサービスの職員に傾眠の状態や、日中の過ごし方について情報を共有しておくと、積極的にレクリエーションに誘ってもらえたり、お昼寝の時間を考慮してもらえたりします。対応やサービスに要望があれば、遠慮せずに率直に伝えましょう。詳しくはこちらをご覧ください。