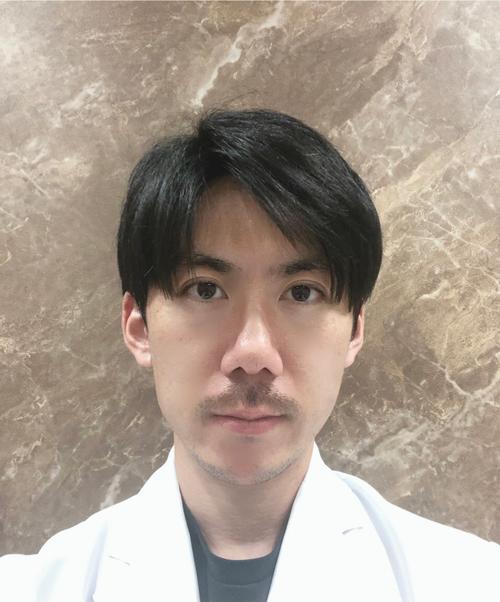自分の両親などが10分おきにトイレに行く場合は、認知症が原因かもしれません。
頻尿はさまざまな要因から引き起こされます。そのため、なぜトイレが頻回なのかの原因を理解することで、適切な対処法がわかります。
この記事では、認知症の主な症状や頻尿の原因、認知症患者の頻尿への対処法をまとめました。認知症かも?と感じた方は、かかりつけ医へ相談しましょう。認知症は早期発見・早期治療が大切です。
もし、頻回なトイレ介助で疲れてしまった場合は、介護施設や訪問介護の利用を検討してみるのも方法の一つです。
認知症患者の現状
認知症とは、脳の病気や障害などのさまざまな原因によって認知機能が低下し、日常生活に支障をきたす状態のことです。
厚生労働省のデータによると、全国の65歳以上における認知症患者の割合は、2012年時点で約462万人であり、今後も増加傾向にあります。
さらに高齢化が進んでいる背景から、今後は5人に1人の割合で認知症患者が増えることが推定されています。
10分おきのトイレは認知症かも?認知症の種類と症状
泌尿器疾患がないにもかかわらず、高齢者が10分おきにトイレに行く行動がみられる場合は、認知症の可能性も考えられます。
ここでは、認知症の種類と症状を解説します。頻尿以外にも当てはまる症状があるか、確認してみましょう。
アルツハイマー型認知症
アルツハイマー型認知症は、認知症のなかで最も多い種類です。
脳の神経細胞に、分解しきれなかった異常なタンパク質が蓄積し、細胞を破壊してしまうことが原因と考えられています。それによって脳が萎縮し、記憶障害などの症状を引き起こします。
昔のことはよく覚えているが最近のことを忘れてしまう、短期記憶障害が特徴的な症状です。徐々に場所や時間の認識が鈍くなり、進行すると徘徊や失禁など、日常生活に支障を及ぼす可能性もあります。
脳血管性認知症
アルツハイマー型認知症に次いで多いのが、脳血管性認知症です。
脳梗塞や脳出血などの病気によって、脳細胞がダメージを受けることで発症します。高血圧や糖尿病などの生活習慣病が原因と考えられています。
症状は、脳細胞がダメージを受けた場所によって異なりますが、多く現れるのは、歩行障害や排尿障害、言葉の出づらさなどです。また、症状にムラがあるのがこの認知症の特徴です。
レビー小体型認知症
レビー小体型認知症とは、レビー小体という特殊なたんぱく質のかたまりが脳内にたまり、脳の神経細胞を破壊することで引き起こされる認知症です。原因ははっきりと解明されていません。
実際には目に見えないものが見える幻視や、気分や態度が変わりやすくなるといった症状が主に現れます。さらに、手足の震えや身体のこわばりが起こり、歩行障害を引き起こすこともあるため、転倒に注意が必要です。
前頭側頭葉型認知症
前頭側頭葉型認知症は、前頭葉や側頭葉の神経細胞が減少し、脳が委縮して起こる認知症で、進行がゆっくりなのが特徴です。
感情の起伏が激しく、突然怒り出したり、性格が変わったりするのが主な症状です。また、社会のルールが守れず、万引きなどの反社会的行動がみられることもあります。病状が進行するにつれて、記憶障害や言語障害が現れます。
認知症と頻尿の関係性
認知症になると、トイレが頻回になったり尿失禁したりすることがあります。これは認知症の症状に大きく関係しています。例えば、排尿や尿失禁に関して無関心になることや、トイレにいつ行ったのかを覚えていないなどが、原因として考えられるでしょう。
さらに、認知症にて歩行障害が出現している場合は、トイレに間に合わない、トイレの場所がわからないなどといった行動につながります。
認知症による頻尿は、さまざまな要因から引き起こされます。何が原因となっているのかを把握することで、正しい対処法がわかるでしょう。
10分おきにトイレに行くのは頻尿?
頻尿はトイレが近く、尿の回数が多い状態のことを指します。具体的には朝起きてから寝るまでの間に、排尿回数が8回以上の場合が頻尿と定義されています。
しかし、人によって排尿間隔は異なるため、一概に回数で評価するのは難しいかもしれません。普段の排尿ペースに比べて回数が多いと感じる場合は、頻尿といえるでしょう。
認知症患者が頻尿を引き起こす原因
頻尿になりうる原因はいくつかあります。
ここでは、認知症患者が頻尿を引き起こす原因を解説します。原因を知ることで、とるべき対処法がわかるでしょう。
泌尿器疾患
頻尿は、膀胱や尿道の病気によって引き起こされることがあります。
考えられる病気は以下の通りです。
- 尿路感染:膀胱炎や前立腺炎などの炎症が原因。ほかにも、排尿時痛や下腹部痛、発熱や血尿などがみられる。
- 前立腺肥大症:男性における頻尿の原因の1つで、加齢とともになりやすくなる。ほかにも、尿の出しにくさ、残尿感などの症状が特徴。
- 過活動膀胱:膀胱に尿が十分にたまっていないにもかかわらず、排尿筋が収縮して尿意を催す病気。急に強い尿意を感じ、トイレまで間に合わないことも。
これらの病気によって頻尿を引き起こしているケースもあります。頻尿以外にも気になる症状がある場合は、病院で一度診察してもらいましょう。
夜間頻尿
認知症によって見当識障害などの症状がある場合、時間の感覚が鈍くなったり、昼夜逆転したりすることが原因で、夜間の睡眠が浅くなる傾向があります。そうすることで、目が覚めるたびにトイレが気になり夜間頻尿となることも。
しかし夜間頻尿は、認知症が原因だけではありません。
もともと高齢者は中途覚醒が多く、眠りが浅い傾向にあります。そのため認知症でなくても、夜間頻尿を気にする高齢者は少なくありません。
記憶障害
認知症の主な症状の1つである記憶障害が原因で、トイレの回数が多くなることがあります。
これは、トイレに行ったこと自体を忘れてしまい、いつトイレに行ったかわからない不安から引き起こされると考えられています。そのため、尿意を感じていなくても、トイレに頻回に行くのが特徴的です。
認知症患者の頻尿が引き起こす問題点
ここでは、認知症患者が頻回にトイレに行くことで生じる問題点を解説します。
起こりうる問題を事前に把握し対策することで、事故やトラブルなどを未然に防げるでしょう。
夜間のトイレでの転倒リスク
夜間のトイレは、暗く足元がよく見えないことや、焦ってトイレに行くことなどが原因となり、転倒するリスクが高まります。
特に認知症患者で歩行障害を有している場合は、介助が必要にもかかわらず、自分一人でトイレに行こうとして転倒してしまうケースも少なくありません。
転倒リスクに対して正しく理解し、おむつの着用など適切な対処法を考えることが大切です。また、頻尿そのものを治療することで、夜間頻尿の回数が減ることもあります。
まずは頻尿の原因を把握し、医師と相談しながら治療法を検討しましょう。
介助者の負担の増加
認知症患者が何度もトイレにいく場合、介助者の負担が増えてしまいます。特に歩行障害があると、付き添いやトイレ介助など介助量も多いでしょう。さらに夜間のトイレが頻回であれば、その都度起きて介助する必要があるかもしれません。
また、トイレに行ったことを説明しても理解してもらえなかったり、本人が怒ってしまったりすると、精神的負担も大きくなることが考えられます。この状況が長い期間続くと、介助者の負担は大きくなりストレスとなります。
その場合は、介護施設の入所の検討や、訪問介護サービスの利用なども手段の一つとして考えておくとよいでしょう。
本人の精神的負担
認知症患者は自分の状況を理解できず、まわりからの言葉にショックを受けてしまうことや、伝わらないイライラから怒りの感情が芽生えるなど、精神的負担を感じているケースも少なくありません。
認知症患者は、以下の心理的特徴があるといわれています。
- 不安感
- 焦燥感や怒り
- 混乱
- 意欲の低下
- 不信感や不快感
認知症の症状や程度によっても異なりますが、これらの心理状態であることを理解して関わり方を考えましょう。
10分おきにトイレに行く認知症患者への対応
認知症患者の頻回のトイレは、介護者の大きな負担です。症状や状況によって対応は異なるため、まずは頻尿になる原因を把握しましょう。
まずは泌尿器科などの病院を受診し、病気によるものなのか、認知症によるものなのかをはっきりさせることが大切です。原因によっては、薬剤などの治療で効果が期待できることもあります。トイレの回数が減れば介助の負担は大きく減るでしょう。
しかし、病的な理由ではなく認知症によるものであれば、根気よく付き合っていく必要があります。普段の行動を確認し、何が必要なのか、どのように対処すればよいのかを考えてみましょう。
認知症患者の頻尿への対策方法
ここでは、認知症患者の頻尿への具体的な対策をご紹介します。
これらの方法を実践することで、トイレの回数を減らしたり、介助量の軽減に効果が期待できます。
オムツを使用する
突然強い尿意を感じる場合や、トイレに間に合わず漏らしてしまう場合は、オムツの使用が効果的です。予防的にオムツを着用しておくことで、万が一漏れてしまってもベッドや洋服を汚さずに済みます。
オムツには「パンツ型」「テープ型」や「夜用」などさまざまな種類があるため、本人の好みや使う場面に合わせて選びましょう。また、併せて防水シーツなどを使用すると、さらに効果的です。
しかしなかには、オムツの着用を拒否する方やもいらっしゃるでしょう。特に認知症患者の場合は、自分の状況を把握できず、オムツの必要性を理解できない可能性があります。
そのような時には、むりやり意見を押し付けるのではなく、冷静に本人へ必要性を説明してみましょう。ここで感情的になってしまったり、強い口調で押し付けたりしてしまうと、自尊心を傷つけかねないため注意が必要です。
カフェインの含まれる飲料を避ける
緑茶やコーヒー、アルコールなどのカフェインを多く含む飲み物を、避けるようにしましょう。
カフェインには利尿効果があるため、飲み過ぎることで頻尿を引き起こす原因となります。特に就寝前の摂取はやめましょう。水分を摂る際は、水や麦茶がおすすめです。
どうしても好きで飲みたがる場合は、飲む時間帯や量を調整することが大切です。認知症患者は、上手く飲水量をコントロールできない可能性があるため、家族が飲水量のチェックや飲み物を管理する必要があるでしょう。
排尿日誌を記録する
排尿日誌を記録すると、排尿に関する状況を把握でき対策しやすくなります。
排尿日誌には以下の内容を記載しましょう。
- トイレに行った時間
- 排尿の量
- 水分を摂った時間
- 飲水量
- 尿失禁の有無
これらを3日ほど記録すると、1日の水分バランスや排尿状況がわかります。尿量に対して飲んでいる量が多ければ、飲水量をコントロールしましょう。
また、記録しておくことで本人がいつトイレに行ったのかを確認できます。口頭で伝えるよりもわかりやすく信頼性も高いため、認知症患者でも受け入れやすくなるでしょう。
薬剤で治療する
トイレの回数が気になる場合は病院を受診し、医師へ頻尿について相談してみましょう。薬での治療が可能かもしれません。
原因によって治療法が異なるため、まずは検査する必要があります。薬にて原因が解消できれば、頻尿が改善される可能性もあります。
認知症患者が利用できる施設やサービス
認知症患者の介護は、介助者の負担が大きいでしょう。疲れを感じたら、介護施設の入所や訪問介護などのサービスを検討するのも方法の1つです。
最後に、認知症患者が利用できる施設やサービスをご紹介します。
介護施設
介護施設でも、認知症患者の入所は可能です。
入所できる介護施設は以下の種類があります。
- グループホーム
- 特養(特別養護老人ホーム)
- 有料老人ホーム
- サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)
施設によって特徴や費用、入居条件が異なります。本人や家族の希望に合わせて選びましょう。
また、入所待ちや待機期間が必要な施設もあるため、早めに準備を進めることが大切です。万が一待機期間が長くなる場合は、一度訪問介護などのサービスを利用するとよいかもしれません。
訪問介護
自宅で過ごす場合は、訪問介護を利用することで介助の負担を減らせるでしょう。訪問介護を利用するには要介護認定を受ける必要があり、要支援・要介護度によって利用できる時間や日数が異なります。
訪問介護では、以下のサービスを受けられます。
- 入浴や食事・排泄介助などの身体介護
- 掃除や洗濯・食事の準備などの生活援助
- 認知症ケアや介護に関する相談
訪問介護を依頼することで、その間自分の身体を休められます。また、介助での悩みや困りごとを介護士などに相談できるため、不安や疑問を解消でき、精神的負担の軽減にもつながるでしょう。
認知症による頻尿は原因によって対処することが大切
両親などのトイレが10分おきなど頻回になったら、まずは原因を把握することが重要です。原因によってとるべき対応が異なります。気になる症状がある場合は、一度病院を受診するとよいでしょう。
また、頻回なトイレ介助で身体的・精神的負担を感じている場合は、介護施設への入所や訪問介護のサービスを検討しましょう。早めに対応することが大切です。
認知症は早期発見・早期治療が大切です。そのため、認知症かも?と感じたら、早めにかかりつけ医へ相談しましょう。詳しくはこちらをご覧ください。
認知症の方への声掛けのポイントは、簡潔にわかりやすくし、ゆっくりと話すことです。理解してもらえないからといって感情的になることは避けましょう。落ち着いて、冷静に話しかけることが重要です。また、介助を拒否された場合は、時間を空けたり人を変えてみたりすると効果的です。詳しくはこちらをご覧ください。