若年層でも施設の利用が必要になった場合、入所できるのか不安に感じるかもしれません。
介護施設の利用は若年層でも可能です。また、介護保険の内容によって受けられるサービスなどもあります。
この記事では、若年層で介護施設に入居ができる理由を中心に利用できるサービスなどを解説します。介護施設に抵抗がある方でも、利用できる施設があるので検討してください。
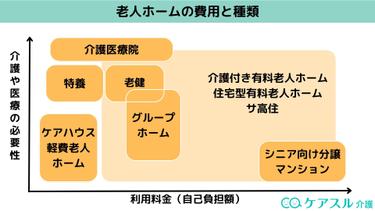
若年層は介護施設に入所できる?
介護施設は、高齢者が使う施設だと思うのが一般的かもしれませんが、若年層と呼ばれる40代からでも入所ができます。
多くの施設では、「60歳以上」の条件を定めている場合がありますが、その中には入居条件が自分に合う施設もあります。
すぐに行動に移せるように、希望条件をあらかじめ整理しておくと、そのあとがスムーズです。
入所を検討するときは、どういう条件があるのか予め調べるようにしましょう。
介護保険の対象は「65歳」から?
介護保険は、40歳から加入し毎月保険料を納めます。しかしながら、特別な理由がない限り介護保険サービスを利用できる対象は65歳以上の方(第1号被保険者)です。以下の表を参考にしてください。
介護保険の被保険者
| 被保険者 | 第1号被保険者 | 第2号被保険者 |
| 対象 | 65歳以上の方 | 40~64歳の方
(医療保険加入者) |
| 受給要件 | 要介護状態
要支援状態 |
要介護状態
要支援状態 (末期がんや加齢起因による疾病が原因の場合) |
| 保険料負担 | 市町村が徴収
(原則、年金から天引き) |
医療保険者が医療保険の保険料
一括徴収 |
ただし例外もあります。表のように40〜64歳(第2被保険者)の方でも、突然の事故や病気などによって介護が必要となるケースでは、若年層であっても介護保険の利用が可能です。
若年層の介護保険サービスについては次章から詳しくみていきましょう。
(参考:介護保険制度の概要)
介護保険対象となる方の定義
若年層での介護保険対象者は、40〜64歳の方です。65歳以上の方と同様に、要介護認定を受けていれば、介護サービスを利用できます。
ただし、以下のような特定疾病に該当しないと利用ができないため注意が必要です。
特定疾病
- 末期がん(致死性があり、余命が6ヵ月程度と診断された)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨粗鬆症(骨折をともなう)
- 初老期における認知症(失語、失行、失認、実行機能)
- パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病)
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症(老化が実年齢よりも早く生じた疾患の総称)
- 多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形をともなう変形性関節症
上記の疾病に該当する場合、「要介護認定」を申請すると介護サービスを受けられます。市区町村にある介護保険担当の窓口へ出向いて申請をするか、地域包括支援センターや介護保険施設、居宅介護支援事業者などを利用しましょう。
(参考:介護保険制度の概要)
介護保険対象外となる方の定義
介護保険の対象外だったとしても、介護が必要な場合があります。そのような時は、障害福祉サービスの利用が可能です。
平成25年に障害者総合支援法が施行され、必要な福祉サービスを受けられるように障害者に対する支援内容が一元化されました。
具体的には主に、2つの支援があります。
- 自立支援給付:身の回りの世話やショートステイなどの支援
- 地域生活支援:社会復帰や自立した生活を目指す支援
合わせて、車いすの利用や義足などの費用を補助してもらえる支援や医療費の支援サービスもあります。
(参考:障害福祉サービスの利用について)
(参考:障害者総合支援法が施行されました)
障害福祉サービスを受けるには?
障害福祉サービスを受けるためには、次の手順を踏む必要があります。
障害福祉サービスを受ける手順
- 市区町村の窓口へ申請
- 障害支援区分の認定を受ける
- サービス等利用計画案を提出(指定特定相談支援事業者が作成)
- 計画案などを元に市区町村で支給の決定をする
- 指定特定相談支援事業者は、サービス会議を行う
- 連絡調整等を行ったうえで、実際に利用する「サービス等利用計画」を作成
- 障害福祉サービスの利用がスタート
障害福祉サービスを受けると、生活に関する支援に加えて、お金に関する問題なども含め精神的にも支えになるので、積極的に利用を検討しましょう。
(参考:障害福祉サービスの利用について)
若年層でも入居できる施設が知りたいという方は、ケアスル 介護がおすすめです。ケアスル 介護なら、入居相談員にその場で条件に合った施設を教えてもらうことができるためご希望に沿った施設探しが可能です。
「プロに相談したい」という方は、ご気軽に無料相談を活用ください。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
若年層が介護施設への入所を考えるケースとは
若年層が介護施設の入所を考えるタイミングとしては、次のようなケースが考えられます。
入所に至るケース
- 難病を抱えていた
- 生活習慣病を患った
- 在宅だと厳しくなってきた
ご自身の状況に当てはめながら見ていくと、参考になる部分もあるでしょう。それぞれのケースについて解説します。
入所に至るケース1:難病を抱えていた
10〜20代などの若い世代から、持病として難病を抱えている場合があります。
家族の手を借りて生活できていたものの、年齢を重ね、社会的に自立をしていった結果、身体の不自由を感じてしまうケースもあります。
また、ずっと介護をしてもらえていたとしても、タイミングによっては一人で生活する状況になる場合もあるでしょう。
一人ではどうしても生活すべてを自分だけでこなすのは難しく、結果として、介護施設の利用を検討する流れとなります。
入所に至るケース2:生活習慣病を患った
若い頃から元気であったものの、不摂生な食生活や生活リズムの乱れにより、生活習慣病を患った時、利用を検討する場合もあるでしょう。
生活習慣病は、今まで生活していた習慣によって患う病のため、突然、脳梗塞になってしまったり、くも膜下出血になってしまったりするのです。
自覚症状がないまま進行してしまい、症状が出たときには重い病として降り掛かってくるのが怖いところです。
日頃から、正しい生活を送れていればリスクは少ないですが、100%避けられるわけではありません。重症化してしまうと、体が不自由となってしまい、介護施設の利用を検討するようになります。
入所に至るケース3:在宅だと厳しくなってきた
介護施設への入所をせず、在宅で介護を受けていたものの、さまざまな状況で厳しくなるケースも考えられます。
介護をしてもらっている間の双方の精神的負担や体力的な厳しさなども、年を重ねていくと出てきてしまうでしょう。
また、仕事環境の変化で介護を続けるのが難しくなってしまった場合、支援を受ける必要があります。結果として、介護施設への入所を余儀なくされるかもしれません。
若年層が介護施設に入所するメリット
若年層が介護施設へ入所するメリットは、以下の3点です。
メリット
- 介助してもらえる
- 生活に関わるリスクが減る
- 一般的な住宅と変わらない生活が送れる
それぞれの内容について解説します。
メリット1:介助してもらえる
若年層で介護が必要となったとしても、自分でできる部分もあるでしょう。
しかしながら、これまでできていた動作ができなくなったり、時として手助けが必要になったりする場面も生じます。
介護施設では、プロの介護士に介助してもらえるので、安心して生活できる点がメリットです。介助をしてもらえる分、転倒などのリスクが減るだけでなく、今までよりも快適に過ごせます。
自分でできる物事については、自分で行うスタイルも可能なため、介護施設を利用の際には、ぜひ相談しましょう。
メリット2:生活に関わるリスクが減る
介護施設に入所すると、日常生活で考えられるリスク(転倒による怪我など)が減らせます。
若年層とはいえ、加齢による肉体的な負担が増えてきます。自宅の生活で転んで怪我をしたり、階段の上り下りが辛く感じたりする場合もあるでしょう。
そのようなトラブルが一人のときに起きてしまうと、助けを呼ぶのが困難です。
施設の中であれば、そのような生活に関わる負担や怪我などのリスクも減り、安心した日々を過ごせます。
メリット3:一般的な住宅と変わらない生活が送れる
介護施設は高齢者向け住宅ですが、実際の生活環境は一般的な住宅と大きく変わりません。とはいえ、介護と名前に付くため、一般的な住宅のイメージはつきにくいでしょう。また、閉鎖的な空間のイメージもあるかもしれません。
近年の介護施設は、設備面や環境面が充実してきており、一般住宅と変わらないような、快適な生活が過ごせます。自宅とは違い、バリアフリー設計になっている点を含めると、より安心して普段と変わらない生活が送れるかもしれません。
気になる施設が見つかった場合は、事前に連絡をして見学するのも一つの手です。
若年層が介護施設に入所するときの注意点
若年層が介護施設を利用するときに注意するべきポイントにはどのようなものがあるでしょうか。
主に注意するべきポイントは、次の2点です。
注意するポイント
- 一部条件が必要となる
- 資金が割高
それぞれについて解説します。
注意点1:一部条件が必要となる
若年層が、介護施設を利用するときに一部の条件が必要となる場合があります。
必要な条件は、「要介護認定」を受けている点です。要介護認定を受けていると、第2号被保険者に分類されているため、施設側も入所を想定できます。
なお、施設に介護者側が必要としているサービスがあるかは分からないため、事前に外部の事業者と契約する必要があるかもしれません。
そのため、事前にどのようなサービスが必要なのか洗い出しておくとよいでしょう。
注意点2:資金が割高
若年層が介護施設を利用するときに、料金が割高となる可能性があります。
その理由として、高齢者と比較すると入居期間が長くなると想定されるためです。厚生労働省によると、介護老人福祉施設の平均在所日数は1,285日、介護老人保健施設は300日、介護療養型医療施設は492日となっていますので、目安にするとよいでしょう。
利用期間が長くなると、必然的に料金が割高となる可能性はあるため、注意が必要です。また、入居予定の介護施設によって費用は異なるので、予め複数社を比較し、自分に合った施設を探すようにしましょう。
(参考:厚生労働省資料「介護老人福祉施設」)
予算内に収まる施設が知りたいという方は、ケアスル 介護がおすすめです。ケアスル 介護は、約5万件の施設情報を掲載しているため幅広い選択肢から検討することが可能です。
「納得いく施設を探したい」という方は、ご気軽に活用ください。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
若年層なら介護施設や高齢者賃貸の検討しましょう
若年層であれば、利用できる施設の視野を広げてみるのはいかがでしょうか。
介護施設以外にも、若年層でも利用できるのは「高齢者賃貸」です。高齢者賃貸は、高齢者が快適に生活が送れるように作られた賃貸で、若年層でも利用ができます。
仮に、介護施設の利用が難しかったとしても、高齢者賃貸の選択肢が増えるだけで、「若年層」の壁が低くなります。
高齢者賃貸がどういう施設なのか、また、どういったメリットがあるのか解説します。
高齢者賃貸とは
高齢者賃貸は、民間が管理している場合が多い賃貸契約の施設です。
若年層で介護が必要な方でも利用しやすい点がメリットです。また、親子で同居が叶う点や民間との賃貸契約により、融通が効きやすい可能性があります。
一般的な賃貸よりも、介護が必要な方や高齢者向けの建物になっているので、さまざまな設備が整っているため安心して生活を送れます。
高齢者賃貸のメリットは次の点です。
- 自由度が増す
- 快適に過ごせる
それぞれについて解説します。
メリット1:自由度が増す
高齢者賃貸は、自由な生活が送れる点がメリットです。
閉鎖的な環境ではなく、自由度が高く仕事や趣味などを好きに楽しめます。また、コンシェルジュや相談員など、入居者をサポートしてくれるので安心して生活が送れます。
高齢者賃貸で生活している方も、仕事をしたり、買い物を楽しんだり、より豊かな生活が送れるようになる点が大きなメリットです。住み慣れた家を離れる点だけでも、さまざまな思いを抱えるかもしれませんが、より素敵な生活が送れるので検討はいかがでしょうか。
メリット2:快適に過ごせる
介護が必要となった場合、自宅をリフォームしなくてはならないケースがあります。
その場合、まとまった資金が必要となったり、専門家に相談したりする必要があるので、多少負担に感じてしまうかもしれません。
ただし、高齢者賃貸の場合、高齢者が豊かに生活を送れる工夫が施されているため、安心して快適に過ごせる点が魅力です。今までの生活でも十分だった方でも、より豊かな生活が送れます。
選んだ賃貸によっては、設備が充実している場合もあるので、ホテルで過ごしているような経験を味わえる場合もあります。
若年層でも介護施設を利用して穏やかな日々を送ろう!
介護施設は、若年層にあたる65歳未満の方でも利用できます。生活習慣病などにより、自宅での生活が困難となった時に利用すると、日常生活でのリスクを避けられる点がメリットです。
また、生活環境も一般的な住居と変わらないほど充実しており、その中で介護が受けられるため安心感があります。
ただし、利用の際には、一部条件が必要となる場合もあり、ハードルが高く感じてしまうかもしれません。
一度、利用する前に専門家へ相談しながら、より豊かな生活を送れるように検討しましょう。
特定疾病を患っている場合、若年層であっても入居可能なケースがあります。詳しくはこちらをご覧ください。
「入居条件が厳しい」「費用が割高になる可能性がある」の2点が挙げられます。詳しくはこちらをご覧ください。





