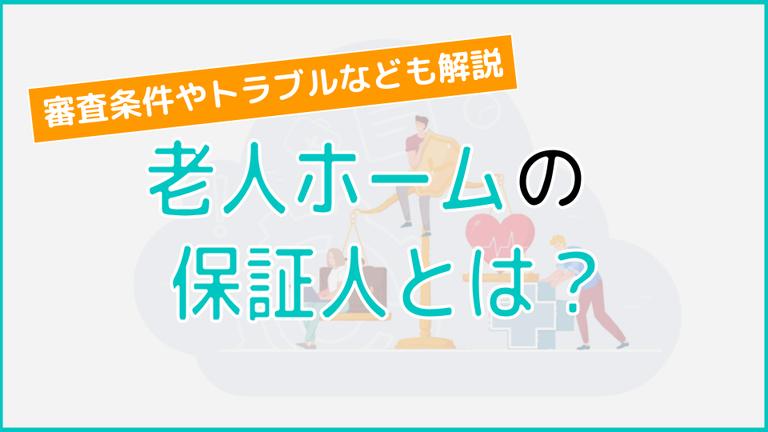老人ホームでは、施設側が高齢者の生活におけるリスクを避けるため、入居の契約を行う際に保証人を立てる必要のあるケースがあります。
しかし、保証人を検討する中でトラブルが発生したり、親族が誰も保証人を引き受けたくなかったりすることも少なくないため、事前に対処法を知っておくことが大切です。
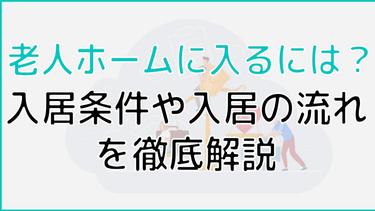
老人ホームの保証人とは?
| 保証人 | 身元保証(手続き・意思決定) |
| 連帯保証(金銭) | |
| 身元引受人(逝去後対応) |
老人ホームの保証人には、「保証人」と「身元引受人」の両者の意味合いが含まれることが多いです。
「保証人」は、生活上で必要な手続きや判断などの意思決定を代理で行う、または利用者間トラブルなどの保証をする身元保証、支払い債務などの金銭的な保証をする連帯保証の二つの役割があります。
また、「身元引受人」は、入居者が亡くなった後の対応を行い、身元を引き取る役割があります。
基本的に保証人は緊急連絡先となり、容体が急変してしまったとき、施設でトラブルを起こしてしまったときなどに対応が求められる場合があります。
老人ホームの入居時に保証人が必要になる施設は多いですが、施設の種類や運営主体によって保証人の必要性や求められる内容に差があることがあります。
特に有料老人ホームなどの民間が運営している施設に関しては、ほぼすべての施設で保証人が必要になると思っていて良いでしょう。逆にケアハウスなどの公的な社会福祉法人が運営している施設に関しては、保証人を不要または形式的な書類のみで済ませる場合もあります。
老人ホームの保証人に必要な条件
ではこの「保証人」は誰でもなることができるのかというと、実はそうではありません。
大前提、保証人は「入居者の代わりに責任を負える人」である必要があります。それは金銭面でも管理面でもそうです。よって、収入や年齢、入居者との関係性などをより慎重に審査をする必要があるのです。
子供でも保証人になれる?
老人ホームの保証人は子供でもなることは可能です。
ただし、老人ホームの保証人の条件として、書類等で資産や収入を証明できることを求める施設が多いため、成人しており、かつ、経済的に安定していることが求められるでしょう。
無職でも保証人になれる?
老人ホームの保証人は、無職の場合は難しいことが多いですが、無職であっても保証人になることが不可能というわけではありません。
預貯金や資産が十分にあり、預貯金通帳の写しや資産証明書の提出を以て経済的に安定していることが証明できれば、無職であっても保証人の条件に該当する可能性があります。
また、自身だけでは保証人になることが難しかったとしても、収入が安定している親族がいれば、その方と連帯して保証人になることが認められるケースもあります。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
老人ホームの保証人が立てられない場合の対処法
老人ホームの保証人になりたくない、あるいは保証人を辞めたい場合には、成年後見制度を利用する、身元保証会社を利用するという2つの方法があります。
①成年後見制度を利用する
成年後見制度とは、認知症などにより判断能力が低下した方の財産の管理、身上監護(介護福祉サービスの利用契約、施設入所、入院時の契約締結など)を後見人が本人に代わって行う仕組みです。
成年後見制度を利用するには、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。
家庭裁判所によって後見人が選任されると、本人に代わって老人ホームの入居契約や利用料の支払い、行政・金融機関の手続きなどの役割を任せることができるため、保証人にならずに老人ホームに入居することができます。
②身元保証会社を利用する
身元保証会社のサービスの一つとして、身元保証サービスがあります。
これは、老人ホームの入居にあたり、入居者の支払いに関わる連帯責任の保証や、緊急時の駆け付けといった身元引受の役割を担うサービスとなります。
費用としては、事務管理費(費用)50万と身元保証料(預託金)30万円、総額で80万円ほどです。
身元保証サービスは、終身を前提とした契約となるため、老人ホーム入居時の身元保証を終身に渡ってサポートしてもらうことができるというメリットがありますが、その分費用もかかってくるため、慎重に検討しましょう。
老人ホームの保証人になるリスクやトラブルは?
老人ホームの保証人になることのリスクや実際にあったトラブルには、以下のようなものが挙げられます。
- 高齢のため、判断能力の低下や金銭面も問題で責任を負えないだろうと判断され、保証人になることができない
- 無職などの場合で、一定の収入がないと判断され、保証人になることができない
- 親族が海外に住んでいて日本におらず、施設側とのやりとりが難しいと判断され、保証人になることができない
- 親族がおらず、保証人を立てることができない
- 話し合いを行わず、勝手に保証人にされてしまう
- 保証人が自己破産したり、職を失ったりして、保証人を変更しないといけなくなる
これらのトラブルを起こさないために、まずは保証人になるための条件を入居先の施設にしっかり確認し、保証人になる当人の認識にもズレが無いようにすることがとても重要です。そのためには家族同士の話し合いや、施設との相談、場合によっては保証会社などの検討なども視野に入れて、全員が納得する形で手続きを進めていきましょう。
まとめ|老人ホームの保証人は「入居者の代わりに責任が負える人」
老人ホームでは、月額利用料などの支払いが滞った場合に債務を負うことや、生活上で必要な各種手続き・判断・意思決定を本人に代わって行うことなどを目的に、保証人が必要となるケースが多いです。
しかし、保証人になるには一定の条件を満たす必要があったり、保証人になることによるリスクも存在するため、保証人なるかどうかは慎重に検討するひつようがあります。
また、保証人を立てられない場合や保証人になりたくない場合については、成年後見制度や身元保証会社の利用も検討するようにしましょう。