老人ホームの入所の際は、住民票を移すべきかどうか判断に困るのではないでしょうか。また、メリットやデメリットも気になるところです。住民票を移す際の流れや注意点を知りたい方もいるでしょう。
この記事では、老人ホームの入所時に住民票を移すメリット・デメリットから手続きの流れまでをご紹介します。
ほかにも介護費用の負担を大きくしない制度も紹介し、老人ホームの入居時の住民票や関連事項について網羅的に取り上げました。老人ホーム入居時の手続きをスムーズに進めたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
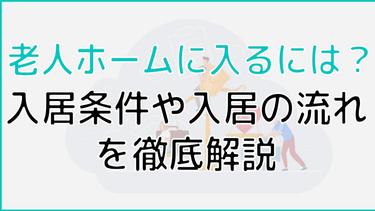
老人ホーム入居時は基本的に住民票を移す
老人ホームに入居をする際に、自治体に対して施設に住民票を移す届出は義務付けられていません。しかし、基本的には老人ホームへの入所が決まったら、住民票を移すほうがいいでしょう。
なぜなら、施設によっては住民票を移すことを入居条件としている場合もあるからです。現住所とは異なる市区町村の老人ホームに入居する場合は、住民票を移す前提で施設選びなどに取り組んでください。
施設への入居を検討しているという方は、ケアスル介護がおすすめです。ケアスル介護なら、入居相談員にその場で条件に合った施設を教えてもらうことができるためご希望に沿った施設探しが可能です。
「プロに相談したい」という方は、ご気軽に無料相談を活用ください。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
老人ホーム入居時は住民票だけではなく「転居・転送サービス」の利用申請もする
老人ホームの入居時に住民票を移すだけでは、入居者の郵便物が施設に届かない可能性があります。老人ホームへの入居が決まったら、「転居・転送サービス」を利用するようにしましょう。
「転居・転送サービス」は最寄りの郵便局か、インターネットから申請ができます。申請すると1年間は旧住所あての郵便物が新住所(施設)に無料で転送されるようになります。
ただし、転送期間は1年間と決められているため、1年を過ぎる場合は再申請が必要です。家族などによる代理申請も可能となっています。
老人ホーム入居時に住民票を移すメリット
老人ホーム入居時に「住民票を移すメリットがなければ手続きなどが面倒」と思う方もいるでしょう。老人ホーム入居時に住民票を移すメリットを知れば、入居後に活かせます。
ここでは主な3つのメリットについて解説します。
施設に郵便物が届き対応してくれる
老人ホーム入居時に住民票を移せば、郵便物は施設に届くようになります。特に自治体からの書類は重要度が高く、旧住所に郵送されても対応が遅れては困る場合もあるでしょう。
特に介護関係の書類であれば、速やかに家族へ連絡が取れるなどの滞りのない対応も期待できます。このように郵便物が施設に届くことで、書類内容への対応がしやすくなります。
費用の負担が基本的に変わらない
住所地特例の方は、引き続き住所変更前の自治体の被保険者ですので、介護保険料も引き続き前住所地の自治体へ納付します。さらに場合によっては、提供される介護保険サービスの単価が低い地域だと、介護サービス費が安くなる
こともあります。
また、介護保険料だけではなく国民健康保険料も、自治体によって異なります。しかし、住所地特例の方は引き続き住所変更前の自治体の被保険者のままです。国民健康保険料も引前住所地の自治体へ納付します。
地域密着型サービスは住所地特例の対象外
各自治体の介護保険サービスの中には、高齢者が住み慣れた場所で暮らし続けられるよう地域密着型のサービスを提供しているところもあります。
介護保険施設は住所地特例の対象ですが、 認知症GHや地域密着型特定施設、地域密着型特養といった地域密着型サービスは住所地特例の対象外です。
住民票を移すことで、地域密着型サービスやその自治体の独自に行う補助や現物支給のサービスなどを受けられたりと、多くのメリットがあります。
より満足度が得られる介護保険サービスを受けられる地域密着型の施設を見つけたときは、住民票を移しましょう。
老人ホーム入居時に住民票を移すデメリット
老人ホームの入居時に住民票を移す際は、メリットだけではなくデメリットも把握する必要があります。デメリットを把握することで、住民票を移す際の注意点や適切な対策が打てるようになりますため、施設選びの参考にしてください。
おもなデメリットとして下記の3点を紹介します。
入居者の個人情報(プライバシー)の問題
まずは入居者の個人情報やプライバシーの問題があげられます。住民票を移し、さらに転居・転送サービスを申請すると、ほとんどの郵便物が施設に届きます。この点はメリットである一方で、デメリットとなるのです。
具体的には入居者の友人・知人からの手紙、生命保険など業者関係からの書類などが施設に届き、交友関係や各種契約が知られる可能性があります。そこで、入居者の個人情報を守るために施設側と郵便物の取り扱いに関するルールを決めるようにしましょう。
「自治体からの書類は開封後、内容を確認して家族に連絡をする」「自治体以外からの郵便物は差出人だけを確認して家族に連絡後、取りに来てもらう」など、施設入居時に決めておけば、プライバシーに関する余計な心配をせずにすみます。
引っ越し前の自治体の各種サービスを受けられない
老人ホーム入居時に住民票を移すと、旧住所には住んでいないものとみなされます。そのため、旧住所の自治体が独自に提供してくれていた補助や衛生用品等の現物支給サービスは受けられなくなります。
特にきめ細やかな介護サービスを受けていた場合は、新住所の自治体でも同様のサービスがあるかを確認する必要があります。施設を選ぶ際は施設の特徴、各自治体の保険料や介護保険サービスなど、総合的な視点での検討が大事です。
不明点が多い場合は、各自治体の「地域包括支援センター」などにご相談のうえ悩みを解決しましょう。
老人ホーム入居時に住民票を移す流れ
老人ホームの入居時に住民票を移す場合は、期日を守って必要な書類を提出します。ここでは住民票を移す流れについて紹介します。下記の手順に従って滞りなく進めましょう。入居者の代理で申請する方法も紹介しますので、ご確認ください。
1.引っ越す14日前までに転出届を出す
老人ホームへの入居が決まったら、現住所の自治体の窓口で「転出届(住所異動届)」を提出します。提出期限は引っ越す14日前までとなっています。しかし、自治体によっては期限を過ぎても取り扱ってもらえる場合もあるため、事前に確認しておきましょう。
なお、転出届を提出する際に必要となる主な書類は、下記をご覧ください。
- マイナンバーカード(保有している場合)
- 窓口で申請する方の本人確認書類(運転免許証など)
- 国民健康被保険者証
- 介護保険被保険者証 など
※必要書類は各自治体によって異なる場合があるため再確認してください。
※上記はいずれも住民票を移す本人のものが対象です。
家族などが代理申請をする際は、上記に加えて委任状や代理人の本人確認書類などが必要です。自治体によっては郵送による手続きやコンビニなどで必要書類の取得が可能であるため、期日に間に合うように計画的に利用しましょう。
また、転出届と同時に「転居・転送サービス」を申請すると、入居後にスムーズに郵便物が届きます。
2.引っ越したら14日以内に転入届を出す
老人ホームに入居後は、14日以内に施設がある自治体の窓口で「転入届」を提出します。自治体によっては期限内に提出しないと過料処分を課す場合があるため、ご注意ください。
転入届を提出する際は下記の書類が必要です。
- 転出証明書(転出届を提出した自治体から発行される)
- マイナンバーカード(保有している場合)
- 窓口で申請する方の本人確認書類(運転免許証など)
- 国民健康被保険者証
- 介護保険被保険者証 など
※必要書類は各自治体によって異なる場合があるため再確認してください。
※上記はいずれも住民票を移す本人のものが対象です。
上記のとおり、転出届と同様の書類が必要です。ただし、「転出証明書」は旧住所の自治体で手続きした際に発行されるため、紛失しないように保管しておきましょう。入居者の代理人が手続きをする際は、委任状と代理人の本人確認書類なども用意してください。
同一自治体内の引っ越しは転居届を出す
同一自治体内で住所が変わる際(A市B町→A市C町に引っ越す)は、「転居届」を提出してください。転居届の場合も新たな住所に住み始めてから14日以内に手続きをする必要があります。
転居届の手続きの際に必要な書類は下記のとおりです。
- 住所異動届書
- 本人確認書類(運転免許証など)
- マイナンバーカード(保有している場合)
- 国民健康被保険者証
- 介護保険被保険者証 など
※必要書類は各自治体によって異なる場合があるため再確認してください。
※上記はいずれも住民票を移す本人のものが対象です。
上記のように転出届や転入届の手続きの際と大きく変わりません。代理人が申請する場合も委任状や代理人の本人確認書類などを用意します。
介護保険料の負担が変わらない「住所地特例制度」
現住所の自治体から別の自治体に住民票を移す際に、介護保険料の負担で不利益が起きないようにするための「住所地特例制度」があります。そこで、同制度の概要や特徴などを一通りご紹介します。制度の内容をご理解のうえ、手続きを進めてください。
住所を移しても旧自治体の被保険者となる
「住所地特例制度」は、住民票を移しても新住所の自治体の被保険者にならず、旧住所の自治体の被保険者になる制度です。よって、新住所に住民票を移しても介護費用などの負担は変わりません。
そのため「この施設に入居したいが費用負担が高くなる」と悩んでいる場合でも、費用面の不安が解消されます。ただし、「住所地特例制度」を利用する際は、後述するさまざまな条件があります。どのような場合においても利用できる制度ではないため、内容をしっかりとご確認ください。
利用対象者
「住所地特例制度」の利用対象者は下記をご覧ください。
- 65歳以上の方
- 40歳以上65歳未満の医療保険加入者の方
※いずれも住所地特例対象施設に入居した方が対象。
- 要介護認定がなくても住所地特例施設に入居した方
(参考:美里町「介護保険における住所地特例について」)
上記の条件を満たす方は、同制度が利用可能です。ここで「制度を利用するにあたり住民票を移動する必要があるか?」と疑問に思う方もいるでしょう。
同制度は自宅から離れた施設に入所したあとも費用負担が変わらない制度(保険者が変わらない)であるため、住民票移動が必須ではありません。
対象施設
「住所地特例制度」の対象となる施設の種類は下記の通りです。
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設、介護医療院
- 特定施設(有料老人ホーム、軽費老人ホーム、ケアハウス、養護老人ホーム)
- サービス付き高齢者向け住宅のうち有料老人ホームに該当するもの
※グループホームなどの地域密着型サービス事業所は対象外になる場合があります。
(参考:横浜市「住所地特例制度のご案内」)
(参考:美里町「介護保険における住所地特例について」)
幅広い種類の老人ホームが対象となりますが、定員など細かな部分で条件は異なります。具体的な対象施設は各自治体のホームページなどで公開されているので、併せてご確認ください。
手続きは自治体窓口と施設の両方で必要
「住所地特例制度」を利用する際は、現住所の自治体窓口で「住所地特例適用届」などの提出が求められます。ただし、「自宅から市外の施設に入居」「元の施設から市内の施設に入居」など、状況に応じて手続きの流れが異なります。
また、入居する施設から「施設入所連絡票」を旧住所の自治体に送付してもらう必要があります。その後、新たな住所の自治体から旧住所の自治体に「住所地特例者連絡票」が送られると、手続きが完了します。
地域密着型施設の利用時は住民票の異動が必須
地域密着型サービスの施設で「住所地特例制度」を利用するには、施設がある自治体に住民票を移す必要があります。地域密着型施設は下記の通りです。
- 小規模多機能型居宅介護
- 夜間対応型訪問介護
- 認知症対応型通所介護
- 認知症対応型共同生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 地域密着型通所介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 看護小規模多機能型居宅介護(旧複合型サービス)
また、自治体によっては住民票を移してから一定期間、サービスが受けられない場合があります。施設を選ぶ際に確認しておきましょう。
まとめ:老人ホーム入居時の住民票の異動は期間に余裕をもとう
今回は老人ホームに入居する際に住民票を移すべきかどうかについて解説しました。基本的に現住所から別の自治体の施設に入居する際は、住民票を移した方がよいでしょう。なぜなら、郵便物の管理や介護保険料の負担などの面でメリットがあるからです。
しかし、施設へのこだわりなどから、結果的に介護費用の負担が大きくなる場合があります。その際は、住所地特例制度を利用して、費用の負担増を抑えましょう。
また、住所地特例制度の手続き、施設への入居準備、住民票の異動手続きなど、さまざまな項目を滞りなくこなすために、期間に余裕を持って取り組んでいきましょう。
必ずしも必須ではありません。ただし、入居を希望する施設から住民票を移すことをもとめられる場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。
特にデメリットはありませんが、対象施設以外(一般住宅など)への引っ越しの際は制度の利用対象外です。詳しくはこちらをご覧ください。





