車椅子を利用している高齢者や寝たきりで移動が困難な方にとって助かる介護保険サービスに介護タクシーがあります。
自宅から病院までの移動や施設までの移動で利用する方が少なくない介護タクシーですが、家族の同乗が断られることも少なくありません。
そこで本記事では、介護タクシーに家族は同乗できるのか、同乗が認められるケースはどのようなケースなのかについて解説していきます。
介護タクシーに家族同乗はできる?
介護タクシーへの家族の同乗は断られるのが一般的です。というのも、介護タクシーは正式には「通院等乗降介助」と言われており、訪問介護事務所が要介護者の車の乗降介助のみに適用される介護保険サービスなので、家族を介護保険サービスの範疇でサポートすることはできないからです。
本章では家族が同乗できない理由などについて詳しく解説していきます。
家族の同乗が認められない理由
介護タクシーに家族の同乗が認められない理由として最も大きな理由は、介護タクシーと呼ばれているサービスは訪問介護事務所が提供している要介護者の乗降介助のみに適用される介護保険サービスだからです。
もう少し詳しく解説すると、そもそも「介護タクシー」という名称の介護保険サービスは存在せず、厳密には訪問介護事務所が主として通院などの際に福祉タクシーやヘルパー等の自家用車を利用して、ヘルパー等の運転者が送迎を行う際に乗降介助を行うサービスです。
したがって、移送すること自体をパッケージとしている介護保険サービスではないので、乗降介助の対象とならない家族は同乗してはならないと言われることがあるのです。
ちなみに似ているサービスとして「福祉タクシー」がありますが、福祉タクシーとは福祉輸送事業限定事業とも呼ばれており車椅子を利用する方や寝たきりを利用する方を対象とした民間企業によるサービスなので全額自己負担で利用する介護保険外サービスとなります。そのため、利用している(したい)サービスが全額自己負担の福祉タクシーなのであればもちろん家族も同乗することが出来るのです。
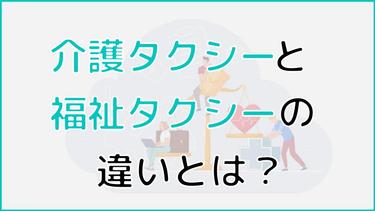
法律上禁止する規定はない
介護タクシーへの家族の同乗が認められていない一方で、厳密には家族の同乗を禁止する法律上の規定はありません。
法律上禁止する規定がない一方で事業者側が家族の同乗を禁止している理由としては、そもそも同乗する家族がいるのであれば介護タクシーを利用せず自分で移送すればよいという理屈や乗降介助の対象ではない家族が乗っているならそれは一般的なタクシーと変わらないという理屈があるからです。
また、安易に家族の同乗を認めると本来の乗降介助という目的から逸れる可能性があり、介護以外の目的で介護タクシーを利用するケースも考えられるので、法律上禁止する規定がなくとも介護タクシーへの家族の同乗は認められていないものだと考えられます。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
介護タクシーに家族同乗ができるケース
介護タクシーへの家族の同乗は原則として禁止されていますが、一方で要介護者が一定の条件を満たしている場合には家族が同乗することも認められています。
例えば、大阪府堺市の場合では以下のようなケースで家族同乗が認められています。
- 認知症または精神疾患があり、家族がいないと精神的に不安定になるために、輸送の安
全を保つことが難しい利用者 - 痰の吸引が必要な利用者
- 認知症、精神疾患、失語症等が原因で、病状を医師に伝えることができないために、本
人だけでは通院の目的が果たせない利用者
(出典:大阪府堺市「訪問介護サービス内容について(通知) 」)
したがって、基本的には介護タクシーへの家族同乗は認められていませんが、例えば認知症で医療器具を自分で外してしまう可能性がある場合や痰の吸引が必要な要介護者、また医師に本人の病状を伝えることが出来ない場合などにおいては特例的に家族同乗が認められると言えるでしょう。
介護タクシーに家族同乗を認めてもらうには?
介護タクシーに家族同乗を認めてもらうには居宅介護支援事務所の代表者から保険者に問い合わせてもらうほか、地域包括支援センター、またケアマネージャー等に対して特例的に家族同乗が必要であることを伝える必要があります。
というのも、上記の堺市の例において上の要件に当てはまっているかどうかに関して「主治医の意見書や診断書の保存等は必要ない」との記述もあるため、主治医の意見書などが無くても本人からの申し出などによって認められると推察できるからです。
確かに介護タクシー乗降介助を対象とした介護保険サービスなので家族同乗は基本的には認められないケースが少なくありませんが、要介護者の状況によっては認めてもらうことも可能なので出来るだけ関係者に掛け合ってみましょう。
介護タクシー以外で家族同乗できるものはある?
介護タクシー以外で家族同乗が出来るものとしては、介護保険が適用されない福祉タクシーが考えられます。
福祉タクシーとは、社会福祉を目的に公共交通機関を利用しての移動が困難な方を対象にサービス提供されているものです。
あくまでも民間の事業者が提供しているサービスなので、福祉タクシーのドライバーは介護資格が不要で乗り降りのサポート等は法律上してはならないという決まりがあります。したがって、介護度が重く自立して乗り降りができない方は利用が難しいサービスとなっています。
また、福祉タクシーはあくまでも民間事業者が社会福祉という切り口で提供しているサービスとなるので、移動先は病院などの必要最低限の場所である必要はなく、旅行やレジャーなどでも利用することが出来ます。
自治体によっては、地域による助成を受けることが出来る場合もあるのが特徴で、神奈川県相模原市であれば身体障碍者手帳の1級・2級などの市が認定した方に対して1枚500円の利用券を1カ月に6枚交付しています。(参考:神奈川県相模原市「福祉タクシー利用助成」)
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
介護タクシーに家族同乗を認めてもらうように働きかけよう
ここまで介護タクシーに家族同乗が出来るかどうかについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
介護タクシーはあくまでも乗降介助のサポートをする介護保険サービスなので通常は家族同乗は認められませんが、特殊な事情がある場合は家族同乗が出来ることが自治体からも認められています。
そのため、介護タクシーに同情する必要がある場合は居宅介護支援事務所や地域包括支援センター、ケアマネージャーに掛け合ってみましょう。
介護タクシーへの家族の同乗は断られるのが一般的です。と言うのも、介護タクシーは訪問介護事務所が要介護者の車の乗降介助のみに適用される介護保険サービスなので、家族を介護保険サービスの範疇でサポートすることはできないからです。詳しくはこちらをご覧ください。
家族がいない際に精神的に不安定な状態になるケース、何らかの原因で医師に病状を伝えることができないために、本人だけでは通院の目的が果たせないケースなどでは、同乗が認められることがあります。詳しくはこちらをご覧ください。




