高齢者の方や高齢の親と離れて暮らしている方にとって、一人暮らしや介護の不安に対するさまざまな悩みや相談ごとを聞いてくれるところがあればと思われる方もいるかもしれません。
その地域に住む高齢者の方に対し、介護や保健、福祉などさまざまな疑問や悩みにトータルで対応している相談窓口が全国にあります。それが地域包括支援センターです。
地域包括支援センターの活用によって、高齢者本人および家族等の関係者の介護に対する不安の軽減につながる可能性があります。
本記事では具体的な仕事内容や実際の事例を解説します。高齢者の一人暮らしや介護に対する不安を軽減したいと考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。
包括支援センターは高齢者のよろず相談窓口
地域に暮らしている高齢者の生活支援を目的として、地域包括支援センターは介護保健法改正時の2005年に作られました。
公的な相談窓口であり、要介護度の有無にかかわらず、65歳以上の高齢者および関係者が利用可能です。
全国すべての市町村に、およそ5,300カ所に設置されている相談窓口の地域包括支援センターについて解説します。
2005年に設立された
地域包括支援センターは、2005年6月の介護保険法改定により誕生しました。
地域に住む高齢者が安心して生活できるよう、保健や医療の向上、福祉のさらなる充実に向けた支援をトータルで行うことを目的としています。
介護ケアマネジメント(居宅要支援被保険者に係るものを除く)および包括的支援事業、その他厚生労働省令で定める事業を実施するものとされています。
地域に住む高齢者が利用できる医療、保険、福祉の充実を図る機関
利用可能なのは、地域に住んでいる65歳以上の高齢者および関係者です。要介護認定を受けていない、自立しているお年寄りも利用できます。
地域包括支援センターの目的は、地域包括ケアシステムの構築・実現です。
団塊の世代が75歳以上となる2025年を目途に、要介護度が重度化したとしても、慣れ親しんだエリアで住まいや医療、介護、予防および生活支援をトータルで提供できる地域作りを目指しています。
約5,300カ所、全国の市町村に設置
2021年時点で、全国の市町村およそ5,300カ所に設置されています。
運営形態として、市町村直営が20.5%、委託型が79.5%で、委託型が増加傾向となっています。
【地域包括支援センターの設置数(2021年4月末現在)】
| 地域包括支援センター | 5351カ所 |
| ブランチ設置数 | 1688カ所 |
| サブセンター設置数 | 347カ所 |
| センター、ブランチ、サブセンター合計 | 7386カ所 |
(参照:厚生労働省「地域包括ケアシステム」より作表)
【委託先法人の構成割合(2021年4月末現在)】
| 委託先法人 | 設置数(割合) |
| 社会福祉法人 | 2262カ所(54%) |
| 社会福祉協議会 | 754カ所(18%) |
| 医療法人等 | 751カ所(18%) |
| その他 | 423カ所(10%) |
(参照:厚生労働省「地域包括ケアシステム」より作表)
設置数の目安としては、人口2〜3万人に1ヵ所、おおむね30分以内に必要なサービスが提供される日常生活範囲内、具体的には中学校区を単位として想定されています。
居宅介護支援事業所との相違点とは?
介護に関して耳にする施設に居宅介護支援事務所があります。
居宅介護支援事業所とは、要介護認定を受けている高齢者が介護サービスを活用し、自立した生活を送れるようサポートする事業所をいいます。
主なサポート内容は、介護支援専門員(ケアマネジャー)によるケアプラン(介護サービス計画書)の作成です。
ケアマネジャーは本人及び家族の心身の状況や生活環境、希望などをヒアリングし、その内容をもとにケアプランを作成します。
また、もしも老人ホーム・介護施設をお探しの場合には、ケアスル介護で相談してみることがおすすめです。
ケアスル介護では全国約5万もの施設から、入居相談員がご本人様のニーズに合った施設をご紹介しています。
「納得のいく施設選びをしたい」という方は、まずはぜひ無料相談をご利用ください。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
地域包括支援センターで扱う業務とは?
地域包括支援センターで扱う業務は主に次の4点です。
- 包括的および継続的な高齢者の生活支援
- 高齢者の相談窓口
- 金銭トラブルや虐待から高齢者を守る
- 要支援認定者の介護予防ケアプランの作成
それぞれについて解説します。
包括的および継続的な高齢者の生活支援
高齢者に住み慣れた地域で安心して生活を送ってもらうために、医療や介護、福祉についてトータルかつ継続して支援することはとても重要です。
地域包括支援センターの主な役割は、地域単位で住民と医療、保健、福祉に関する専門家との連携をスムーズに推し進めることです。具体的な事業内容として次のようなものがあります。
- 「地域ケア会議(包括支援センターまたは市町村が主催する会議)」等を通じた自立支援型ケアマネジメントの支援
- ケアマネジャーへの日常的個別指導や相談
- 支援が困難な事例等への指導および助言による改善
高齢者の相談窓口
認知症や身体機能の低下など、高齢者本人のみならず、ご家族も将来への不安を抱くことがあるでしょう。
高齢者本人および家族が抱える悩みを相談する窓口として役割を果たすのが、地域包括支援センターです。
関係各所との連携を密にして、高齢者が暮らしやすい生活を送れるよう務めています。
例えば、各自治体で行っているサービスの提案や、介護サービスを受けられるよう介護保険申請手続きの実施などを行い、地域高齢者の安心安全な生活をサポートしています。
金銭トラブルや虐待から高齢者を守る
地域包括支援センターは金銭トラブルや虐待などから地域の高齢者を守る役割も担っており、権利擁護義務とも呼ばれています。
高齢者を狙った振り込め詐欺や言葉巧みに商品を売り込む悪徳商法から高齢者を守ること、虐待被害の対応、予防、早期発見などに取り組んでいます。
例えば、金銭管理などにおける判断能力が以前より後退している、あるいは近い将来不十分になる恐れがあると判断される場合には、成年後見制度の活用をサポートすることで、裁判所から選任された方が本人に代わってお金を管理することが可能となり、金銭面でのトラブルから高齢者を守っています。
また、家庭内虐待や金銭搾取、ネグレクトについても、近所からの通報などで早期発見、予防、対応に努めています。
要支援認定者の介護予防ケアプラン作成
介護予防ケアマネジメントも重要な業務の一つです。
地域包括支援センターにはケアマネジャーが在籍しており、要支援認定者を支援するために作成するのが「介護予防ケアプラン」です。
要介護状態になってしまう可能性のある要支援認定者のケアプランを作成し、身体機能の維持・向上を目指すとともに、食生活の見直しなど栄養面のチェックなどのサービスも行います。
高齢者自身が自覚をもち、要支援状態から自立に向かえるよう、生活の向上を図ることはいうまでもありません。
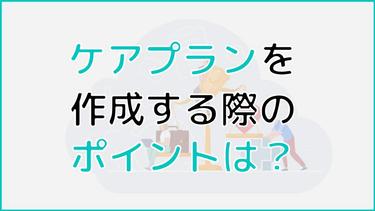
地域包括支援センターに在籍する専門職
地域包括支援センターの人員配置基準として、次の3種類の専門資格を有する方の配置が義務付けられています。
- 主任ケアマネジャー(主任介護支援専門員)
- 社会福祉士
- 保健師
第1号被保険者(65歳以上の高齢者)3,000人~6,000人ごとに上記の専門職がそれぞれ最低一人以上配置されることになっており、仮に3職種の配置が難しい場合も資格に準ずる方が必ず配属されています。
それぞれの専門職について詳しく見ていきましょう。
主任ケアマネジャー(主任介護支援専門員)
主任ケアマネジャーは主任介護支援専門員とも呼ばれ、包括的、継続的なケアマネジメント業務に携わります。
主な業務として、ケアプランの作成、地域ケア会議等を通じた自立支援型ケアマネジメントの支援を行います。
主任ケアマネジャーはほかのケアマネジャーを指導しており、地域内ケアマネジャーのリーダー的な存在です。

社会福祉士
社会福祉士は担当エリア内の高齢者が、安心して生活するための相談および虐待や詐欺など、権利擁護にかかわる相談に応じる業務を担っています。
高齢者が安心して生活ができるよう、一人暮らしの世帯を訪問し、安否確認を行っています。
地域の民生委員とも情報交換をし、地域の現状の把握に務め、認知症により徘徊する高齢者を地元警察と連絡を取り合って探すなど、社会福祉士の務めは多岐に渡ります。
金銭トラブルにあわないよう成年後見制度の提案をするのも社会福祉士の役割です。
保健師
病院や診療所、保健所などと連携し、高齢者の医療・介護関連の相談に対応する専門家が保健師です。体調に不安のある高齢者からの相談の場合、面談や直接訪問して体調について確認します。
場合によっては病院や診療所、保健所に連絡を取り、高齢者に対する最善策を講じることもあります。
また、高齢者の健康維持や推進のため、健康に関するセミナーを開催し、高齢者に健康についての啓蒙活動も行っています。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
地域包括支援センターでの相談内容紹介
地域包括支援センターでは、さまざまな相談を受けています。具体的な事例としてどのようなものがあるのでしょうか。
事例1:介護保険申請の提案でデイサービス利用が実現
日々の生活を元気に過ごしていた高齢者Aさんが、外出中に転倒し骨折する事故に遭いました。救急搬送され、手術を受けた後に病院でリハビリに取り組み、退院。
しかしながら、自身が今まで行っていた家事が困難となったAさんは、地域包括支援センターに連絡。これまでの経緯について話し、家事ができない現状をどうすればいいのか、相談しました。
家事が困難である点に加え、継続したリハビリも必要であることから、Aさんに対し訪問介護やリハビリが受けられるデイサービスの利用に向け、介護保険の申請を提案しました。
このように、相談者の現状を踏まえ、今回のような介護保険申請のサポートによって高齢者がストレスなく過ごせるよう提案しています。
事例2:徘徊する認知症高齢者の保護
物忘れの症状が進んだ高齢者Bさんは、帰宅する際に時折、家とは違う方向に進んで歩くことが多くなりました。ある日、家族と一緒だったBさんでしたが、家族の目が離れたほんのわずかな間に行方不明になりました。
連絡を受けた地域包括支援センターは、Bさんの家族および警察など地域の関係各所に連絡、協力を依頼し、捜査活動を実施。当日中にBさんを無事発見できました。
地域の高齢者の行方がわからなくなった情報や連絡があった場合、警察など関係各所と連携を取り、お年寄りの保護に務めます。
また、包括支援センターでは、認知症で物忘れの症状が進み徘徊に不安を感じている方に対し、GPS機能探索機の貸与や紹介を行っています。
高齢者の徘徊に関する悩みを持つ家族同士の交流会を行い、知識や情報の共有などにも尽力しています。
事例3:老人会の紹介による引きこもりからの改善
知人などと仲良く過ごしていた高齢者のCさんは、息子夫婦が住む都市に地方から転居。環境が変わったせいか、Cさんは家に引きこもりがちになり、外に出歩かなくなりました。
息子夫婦はCさんのことを心配し、地域包括支援センターに相談。
地域包括支援センターは、エリア内で行われている趣味の教室や老人会などを紹介しました。その後、Cさんは親しい友達ができ、外出も多くなり、楽しく暮らせるようになりました。
地域の高齢者が転居などにより新しい環境になじめない場合、高齢者の趣味にあった地域の市民講座や老人会などを紹介することで高齢者の地域での生活環境の改善に取り組んでいます。
地域包括支援センターを使うメリット
- 高齢者および関係者が地域包括支援センターを利用する場合、次の3点がメリットとしてあります。介護や医療など高齢者の専門家がワンストップで対応
- 相談は無料
おのおのについて解説します。
介護や医療など高齢者の専門家がワンストップで対応
何か問題が発生した場合、介護や福祉、医療など高齢者対応の専門家がいるため、あらゆるケースで適切な対処が可能です。
認知症の進行や身体機能低下、引きこもり、虐待、詐欺などから、専門家がネットワークを駆使して安心な生活を守るために対処し、ワンストップで解決策まで提案してくれます。
相談は無料
地域内に居住する65歳以上の高齢者であれば、誰でも無料で介護に関する相談が可能です。
また介護施設への入居に関する相談の場合、ケアスル介護を利用してみることがおすすめです。
ケアスル介護では、入居相談員が施設ごとに実施するサービスやアクセス情報などをしっかりと把握した上で、ご本人様に最適な施設をご紹介しています。
「身体状況に最適なサービスを受けながら、安心して暮らせる施設を選びたい」という方は、まずは無料相談からご利用ください。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
まとめ|早期および適切な対応により高齢者を守る
2005年に設立された地域包括支援センターは、65歳以上のすべての高齢者および関係者が利用でき、医療や介護・福祉など高齢者が抱く悩みや疑問の相談窓口として、全国およそ5,300カ所に設置されています。
地域包括支援センターには高齢者の介護や医療、福祉について迅速かつ適切な措置を行ってくれる専門家が常にいますので、安心して相談できます。もしお一人暮らしの不安や介護関連の悩みを抱えている場合は、一人で抱え込まずまずは地域包括支援センターへ気軽に問い合わせてみましょう。
地域包括支援センターの役割は以下の通りです。「高齢者を金銭詐欺および虐待からお年寄りを守る」「包括的および継続的に支援する」「高齢者および関係者の相談窓口として機能する」「ケアプランの作成により要支援認定者の支援を行う」詳しくはこちらをご覧ください。
地域包括支援センターにいる専門職として、主任ケアマネジャー(主任介護支援専門員)、社会福祉士、保健師が配置されています。詳しくはこちらをご覧ください。





