介護を必要とするような高齢期においても、自分らしさをもち、心からの幸せと満足感を維持できるでしょうか。こうした内面的な充実感を、主観的ウェルビーイングと呼びましょう。この概念は、世界保健機構(WHO)が健康の定義に用いるもので、身体的、精神的、社会的に良好な状態を意味しています。高齢者がどのようにして自己表現を通じてウェルビーイングを保っているのか、とりわけ人生の装い物語を通じて、その秘密を解き明かしていきたいと思います。
鹿児島大学 法文学部
博士(文学)
日本社会学会、北海道社会学会、日本福祉社会学会 ほか
北海道大学農学部を卒業後、化粧品会社で2年ほど総合職として勤務。北海道大学大学院教育学研究科では高齢女性の自己表現と装いのあり方について研究。鹿児島大学法文学部に専任講師として赴任後、2005年に博士(北海道大学・文学)を取得。2015年4月から半年間、米国オレゴン州ポートランド州立大学にて客員研究員。2024年4月現在は同大教授。
はじめに
私が1990年代後半に大学院で取り組んだ研究では、衣服や化粧といった装いの側面に注目して、要介護状態かどうかに関係なく、高齢女性の主観的ウェルビーイングを探究しました。装いには、外見的なこだわりや身だしなみも含まれます。高齢女性たちは身体的に老い衰えていく自分のことをどう思っていたのでしょうか。また日常的に衣服を着て装うとき、その自分をどんなふうに認識していたのでしょうか。
このようなことが知りたくて、当時、院生だった私は、幼少期から高齢期までの写真を見せていただきながら、高齢女性に生い立ちを聞き、それぞれの写真に写っている衣服にまつわるストーリーについて、可能な限り話してもらいました。それらのストーリーには、高齢女性の人生の装い物語と自己表現が盛り込まれていました。今回はその当時の研究の一部を紹介しましょう。
さっそく、高齢女性の日常における装いとその背後にある人生の物語を紹介しましょう。これから紹介するのは1990年代後半、自宅暮らしの活動的高齢者Aさんと特養入居の要介護高齢者Zさんによる装い物語の一部です。
第一の物語
戦時中の厳しい生活のなか、農家で育ったAさんは、食べるのには困らないものの、貧しい環境で育ちました。しかし、彼女の家族は、貧しいなかにあっても、おしゃれによる自己表現を重視していました。厳しい母親の下、自らで衣服を作り、個性を表現することの喜びを見出した彼女は、若い頃から洋裁に情熱を注ぎました。
その後、結婚生活は彼女にとって試練の連続でした。姑との関係は険悪で、自分を抑圧する生活を送っていましたが、内面の強さを失うことはありませんでした。自分自身と子どもたちの衣服は、市販のものではなく、彼女が手作りをしました。そして家庭内での困難に立ち向いました。
33歳で始めた保険の営業職は、本来の夢であったデザイン関係の仕事とは異なっていましたが、彼女は自分らしい洋服を着て、仕事での努力を重ねました。自分が納得できるファッションをすることは、彼女が困難に直面した際の精神的な支えとなりました。
年齢を重ねても、彼女の感性とファッションへの情熱は衰えることはありませんでした。彼女にとって、服装は自己表現の手段であり、人生のすべての段階で降りかかってくる辛いことや理不尽なことを乗り越える助けになっていました。
1998年に私がインタビューしたときのAさんは、活動的な60代の女性でした。彼女にとって、装いは自己の一貫性と連続性を表す象徴だったと言えます。彼女の語るストーリーには、幼少期からの衣服への深い愛着、年齢ごとの体型に合わせた衣服選び、社会生活における衣服の役割への洞察が含まれています。インタビュー当時のAさんは「納得できる装い」がしたいと言っていました。その言葉をそのまま聞いてみましょう。
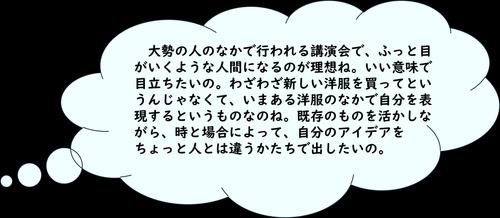
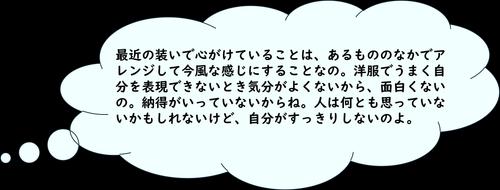
このようにAさんにとっての自分が「納得できる装い」は、人生の途中で出くわす困難を乗り越える支えでした。変わりゆく時代や過酷な社会環境のなかでも、装いは、一貫した自己を保ち続ける手段であり、彼女の人生において自己表現になっていたことがわかります。
続いて、Zさんです。1998年当時の彼女は90歳で、特養ホームで暮らす要介護の女性でした。彼女の装い物語は、内面の強さと宗教への深い信仰が、装いとどのように結びついているかを示しています。
第二の物語
子ども時代のZさんは、酒乱の父と貧しい家庭環境のなかで過ごしました。彼女は、愛情深い母のおかげで、身体が弱かったにもかかわらず、和裁を通じて自己表現の道を見出し、将来の夢を思い描いていました。高等小学校を卒業した後、和裁で生計を立てることを目指して、彼女は自らの衣服を手作りしました。
一方、Zさんは19歳で心臓病を患いました。そのせいで26歳での結婚も短命に終わりました。さらには家族の死という試練にも直面しました。しかし、彼女はその試練を和裁の仕事で乗り越えました。
40代と50代は、和裁のほかに、看護の仕事にも従事しました。Zさん自身も心臓病を患っていたため、彼女は患者の心情を深く理解することができました。また彼女は、S会という信仰と出合い、その信者と深い絆を築きました。日常生活のなかで、彼女は自らの装いに対する情熱をもち続け、好きな服を着ることによって自らの心を強く保っていました。
Zさんは90歳で心臓病が治りました。これには医師も驚いたそうです。特養での生活は、読経、深呼吸、散歩によって心を穏やかに保ちました。また、自分に合うスカートや薄紫色のカーディガンを選んで、自分らしい好きな装いをし続けました。身寄りがないなかでも、彼女は自分自身に満足していました。年齢を重ねるにつれ、目や耳など身体の不調が増えましたが、それでも好きな服を着て、気持ちを明るく保ちました。S会の人々からはいつも若々しいと称賛されました。
インタビュー当時のZさんは「好きな装い」をしていることが健康の秘訣だと言っていました。その言葉をそのまま聞いてみましょう。
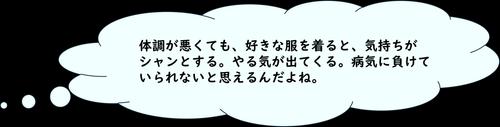
Zさんにとっての装いは、自分らしい「好きな装い」でした。それは身体的な老衰や病気と向き合うなかでの心の支えであり、彼女の信仰と密接に関連していました。彼女の日々の装いの選択は、周囲の人々とのつながりを深め、主観的ウェルビーイングを高める働きをしていました。
装いがもたらす効果
ある研究によれば、装いはただのファッション以上の意味をもちます。それは自己表現の一形態であり、私たちの心の健康に直接的な影響を与える場合もあります。特に高齢になると、健康状態が変化するだけでなく、社会的役割も変化し、自己のアイデンティティを見失いがちです。しかし、なじみの衣服を選び、Aさんのように「納得できる装い」やZさんのように「好きな装い」をすることで、高齢者は日々の生活に喜びを見出し、自分らしさを保ち続けることができるのです。これは装いがもつ心理的な効果と言えるでしょう。
さらに私が大学院で取り組んだ研究では、装いがもつ心理的効果に加えて、その社会的効果も確認できました。衣服が社会的なつながりを強化する手段となっていることも明らかになったからです。
たとえば、Aさんのように「大勢の人のなかで行われる講演会で、ふっと目がいくような人間になるのが理想」という感性は、自己効力感を育むことがあります。自分が他者から承認され、自分の存在を価値あるものと感じさせてくれるからです。Aさんは着るもの一つで人々の眼差しを捉え、内面からの自信をキープしていました。このように、装いは社会的効果をもっているのです。
施設で暮らす入居者にとっても、装いには社会的効果があります。たとえばZさんのように、家族や友人からの「その服、似合っているね」という一言は、単なる褒め言葉以上の効果をもっていました。施設で暮らす要介護高齢者にとって、日々の服装選びは、自分自身を表現する機会となりますし、また、他の入居者や介護職員とのコミュニケーションを生み出すきっかけにもなります。装いを通じて他者とのコミュニケーションが活発になり、他の高齢者や介護職員にも自分から話しかけたりして、孤立感を軽減するだけでなく、意欲や能動性が増えることにもつながっています。自分の選んだ衣服が話題に上がることで社交の機会が増え、日々の生活に彩りが出てきます。介護職員の側も、入居者が選ぶ衣服を糸口にして、ユニットやユニット的な人間関係を通じたよりよい個別ケア(身体介護と生活支援)が可能となるのです。
このように社会学からみた装い物語は、高齢女性が自分のことを社会のなかにどう位置づけるか、または年齢を重ねてきた高齢期の自分自身とどう向き合うかに影響を与えます。高齢者にとっては、それが主観的ウェルビーイング――心からの幸せや満足感の本質を保つ鍵となるのです。
まとめ
私が大学院で取り組んだ研究からは、高齢になっても、そして要介護になっても、自分を表現し、日々の生活に心からの幸せと満足感を得るための秘訣の一つが、装いにもあることが見えてきました。この事実は、自分が身体的な存在だけではなく、社会的存在でもあるということを再確認するものです。服を選ぶという行為は、単なる物理的な行為を超え、精神的な健康、社会とのつながり、そしてQOL(命の質、生活の質、人生の質)を高める行為なのです。
高齢者特有の身体的、精神的ニーズに対する深い理解と、そのニーズを支える社会的サポートが、主観的ウェルビーイングを支える上で極めて重要であることがわかります。装いを選ぶ行為は、その人の人生の物語に深く根差しています。ですから、高齢者の方々も、介護者の方々も、心からの幸せと満足感と人とのつながりを大切にしながら、日々の装いを楽しんでいただけたらと思います。
【参考文献】
- 片桐資津子,2011,「要介護高齢女性における装いの自己認識に関する探索的研究――生活歴から立ち現れる装いに着目して」ソシオロゴス編集委員会編『ソシオロゴス』35: 22-38.
- 片桐資津子,2019,「第8章 高齢女性の主観的ウェルビーイングと装い――人生の危機と自己の再帰的確認」櫻井義秀編著『宗教とウェルビーイング――しあわせの宗教社会学』北海道大学出版会: 269-296.
- 櫻井義秀 編著,2022『ウェルビーイングの社会学』北海道大学出版会.
- Twigg, Julia, 2013, Fashion and Age: Dress, the Body and Later Life, London: Bloomsbury Academic.






