要支援2は、主に足腰に衰えが見られ始めるものの、自立した生活を送ることが可能な状態とされています。
具体的には、歩行や立ち上がりに支えが必要であり、掃除や洗濯、買い物といった負担の大きい動作を伴う家事などに手助けが必要な状態となります。
このように、生活の一部に手助けや見守りが必要になるため、介護保険サービスの利用を検討しているという方もいらっしゃるでしょう。
本記事では、要支援2のケアプラン例や利用できる介護保険サービスについて紹介しますので、それらを参考にサービスの利用頻度や時間などを考えてみるといいでしょう。

要支援2のケアプラン例①在宅介護の場合
在宅介護を受けている要支援2の方のケアプラン例をご紹介します。
娘と同居している要支援2の認定を受けた80歳男性。
ほとんど問題なく生活できるものの、足腰が衰え始め、家事に負担を感じている。
日中は娘が働きに出ているため、サポートが受けられない平日のサービス利用が主になる。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00~9:00 | ご家族からのサポート | ご家族からのサポート | |||||
| 9:00~10:00 | 介護予防通所リハビリ(デイケア) | 介護予防通所リハビリ(デイケア) | |||||
| 10:00~11:00 | |||||||
| 11:00~12:00 | |||||||
| 12:00~13:00 | |||||||
| 13:00~14:00 | 介護予防訪問介護 | 介護予防訪問介護 | |||||
| 14:00~15:00 | |||||||
| 15:00~16:00 | |||||||
| 16:00~17:00 | |||||||
| 17:00~18:00 |
主に、介護予防訪問介護もしくは介護予防通所リハビリ(デイケア)を利用するケアプランになりました。
介護予防訪問介護では、この方が負担に感じている掃除・洗濯・買い物・調理といった家事に関する支援が受けられるため、ご家族からのサポートが受けられない平日の日中の負担を軽減しながら生活できるでしょう。
また、介護予防通所リハビリは、施設に通い、身体機能の維持・回復を目的としたリハビリを受けることができるサービスになります。リハビリ以外に生活支援や見守りなども受けられるため、ご家族のいない日中に利用することで安心して生活することができるでしょう。
サービス利用の料金
上記のケアプラン例の場合、毎月で必要な料金は以下のようになります。
| 利用サービス | 利用頻度 | 利用回数/月 | 金額/回 | 金額/月 |
|---|---|---|---|---|
| 介護予防訪問介護(30分以上1時間未満) | 2/週 | 8/月 | 利用回数に応じた月額制 | 23,490円 |
| 介護予防通所リハビリ(7時間以上8時間未満) | 2/週 | 8/月 | 月額制 | 36,150円 |
| 合計 | 59,640円 | |||
| 自己負担(1割の場合) | 5,964円 | |||
これらの費用はあくまでも一例であり、介護予防訪問介護は市区町村、介護予防通所リハビリは事業所やその規模、所要時間によって費用が異なるため、注意が必要です。
出典:厚生労働省「公表されている介護サービスについて」
出典:杉並区「介護予防・生活支援サービス 訪問型サービス・通所型サービスの基準」
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
要支援2のケアプラン例②一人暮らしの場合
一人暮らしをしている要支援2の方のケアプラン例をご紹介します。
要支援2の認定を受けた75歳女性。
家事などに負担を感じているものの、現状生活を続けることができるため、本人の希望から一人暮らしをしている。
土日はなるべくご家族が家まで通いサポートしているが、距離が離れているため、通えない日もある。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00~9:00 | ご家族からのサポート | ||||||
| 9:00~10:00 | 介護予防通所リハビリ(デイケア) | 介護予防通所リハビリ(デイケア) | |||||
| 10:00~11:00 | |||||||
| 11:00~12:00 | |||||||
| 12:00~13:00 | |||||||
| 13:00~14:00 | 介護予防訪問介護 | 介護予防訪問介護 | 介護予防訪問介護 | ||||
| 14:00~15:00 | |||||||
| 15:00~16:00 | 介護予防居宅療養管理指導 | ||||||
| 16:00~17:00 | |||||||
| 17:00~18:00 |
上記のように、平日を中心にサービス利用をするケアプランになりました。
在宅介護を受けている方のケアプランと比べると、サービスの利用量が増えていることに加え、「介護予防居宅療養管理指導」のサービス利用があります。
介護予防居宅管理指導とは、医師や看護師などが利用者の自宅に訪問し、可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、療養上の管理及び指導をしてくれるサービスになります。
具体的には、服薬指導や栄養管理などを行ってくれるため、周りからのサポートが受けづらい環境にある一人暮らしの方は利用すると安心して生活することができるでしょう。
サービス利用の料金
上記のケアプラン例の場合、毎月で必要な料金は以下のようになります。
| 利用サービス | 利用頻度 | 利用回数/月 | 金額/回 | 金額/月 |
|---|---|---|---|---|
| 介護予防訪問介護(30分以上1時間未満) | 3/週 | 12/月 | 利用回数に応じた月額制 | 37,270円 |
| 介護予防通所リハビリ(7時間以上8時間未満) | 2/週 | 8/月 | 月額制 | 36,150円 |
| 介護予防居宅療養管理指導 | 1/週 | 4/月 | 5,090円 | 20,360円 |
| 合計 | 93,780円 | |||
| 自己負担(1割の場合) | 9,378円 | |||
これらの費用はあくまでも一例であり、介護予防訪問介護は市区町村、介護予防通所リハビリは事業所やその規模、所要時間によって費用が異なるため、注意が必要です。
また、介護予防居宅療養管理指導についても、管理指導者などによって費用が異なるため、把握しておきましょう。
出典:厚生労働省「公表されている介護サービスについて」
出典:杉並区「介護予防・生活支援サービス 訪問型サービス・通所型サービスの基準」
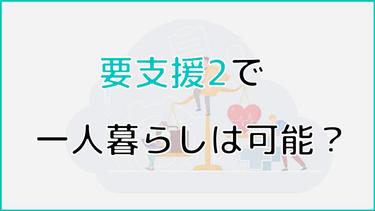
要支援2のケアプラン例③施設入居の場合
施設に入居した要支援2の方のケアプラン例をご紹介します。
数年前に奥さんが亡くなり、現在は一人暮らしをしている要支援2の男性。
身体状態も徐々にであるが悪くなってきているため、今後の生活が心配。
家族も遠方に住んでいるため支援を受けるのが難しい。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00~9:00 | サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)に入居し生活 | ||||||
| 9:00~10:00 | |||||||
| 10:00~11:00 | |||||||
| 11:00~12:00 | |||||||
| 12:00~13:00 | |||||||
| 13:00~14:00 | |||||||
| 14:00~15:00 | |||||||
| 15:00~16:00 | |||||||
| 16:00~17:00 | |||||||
| 17:00~18:00 | |||||||
サ高住に入居するケアプランになりました。
サ高住では、安否確認や生活相談といったサービスが受けられるため、一人暮らしは万が一のことを考えると心配という方に適した施設です。
また、サ高住は高齢者用の賃貸住宅という位置付けにあり、介護施設のように決められたスケジュールで生活する必要がないため、一人暮らしをしていた方なども生活しやすいでしょう。
ただ、サ高住では、入浴や排せつの介助といった介護サービスの提供はなく、介護サービスを利用したい際には外部の事業者と別途契約する必要があるため、その点には注意が必要です。
サービス利用の料金
サ高住の費用は、月額で15~20万円程の金額が目安となります。
また、入居時には、初期費用として敷金や保証金が必要な場合があり、0~50万円程の金額が目安となります。
これらの費用以外にも、日常生活費が必要になるため、毎月20~25万円程の費用を見込んでおくと安心でしょう。
また、介護サービスを利用したい場合には、外部の介護事業者と別途契約する必要があり、上記の費用とは別に費用が必要になるため、注意が必要です。
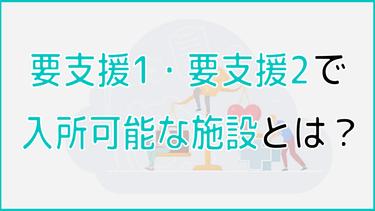
要支援2の状態で入居できる老人ホーム・介護施設をお探しの方は、ケアスル介護で相談してみることがおすすめです。
ケアスル介護では、入居相談員が施設ごとに実施するサービスや予算感などをしっかりと把握した上で、ご本人様に最適な施設をご紹介しています。
「本人に合ったサービスを受けながら、安心して暮らせる施設を選びたい」という方は、まずは無料相談からご利用ください。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
要支援2で利用できる介護保険サービス一覧
本章では、要支援2の方が利用できるサービスを一覧表で紹介します。
利用できるサービスの全体像を知ったうえで、今後利用するサービスを選択しましょう。
| サービス 分類 |
名称 | 概要 |
|---|---|---|
| 訪問型 | 介護予防訪問介護(ホームヘルプ) | 訪問介護員が利用者の自宅に訪問し、利用者が自立して行うことが困難である掃除・洗濯・調理・買い物といった家事の代行などの生活援助を行う |
| 介護予防訪問入浴介護 | 自宅の浴槽での入浴が困難な方向けに、簡易浴槽を積んだ訪問車で利用者の自宅へ訪問し入浴の介助を行う | |
| 介護予防訪問リハビリ | 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などの専門家が利用者の自宅に訪問し、リハビリを行う | |
| 介護予防訪問看護 | 医師の指示に基づき看護師等が利用者の自宅に訪問し、療養上のお世話や診療の補助を行う | |
| 介護予防居宅療養管理指導 | 通院が困難な利用者に対し、医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士などが利用者の自宅を訪問し療養上の管理・指導・助言を行う | |
| 通所型 | 介護予防通所介護(デイサービス) | 施設に日帰りで通い、通い先の施設にて、食事の提供や入浴、生活援助、機能訓練などのサービスを受けることができる |
| 介護予防通所リハビリ(デイケア) | 要介護状態になることを予防するため、老健(介護老人保健施設)・病院・診療所・介護医療院に通い、リハビリを行う | |
| 介護予防認知症対応型通所介護 | 認知症の症状が明らかに見られる方に対し、心身機能の維持回復を目的とした専門的なケアを行う | |
| 短期入所型 | 介護予防短期入所生活介護(ショートステイ) | 老人ホーム等に短期間入所し、入浴・排せつ・食事等の介助や機能訓練等のサービスを受けることができる |
| 介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ) | 老健や介護医療院等の医療機関に短期間入所し、看護および医学的管理の下で介護や生活援助、医療ケア、機能訓練等のサービスを受けることができる | |
| 複合型 | 小規模多機能型居宅介護 | 利用者の選択に応じて「訪問」「通所」「宿泊」の3つを組み合わせて利用できるサービス |
| 施設入居 | グループホーム | 認知症の症状が見られる方を対象とした、5~9人の少人数からなる共同住宅の形態でケアサービスを提供する施設 |
| 有料老人ホーム | 「介護(入浴・排せつ・食事の提供)」「洗濯・掃除等の家事の供与」「健康管理」のうちいずれか1つ以上をサービスとして提供している施設 | |
| ケアハウス(自立型) | 家族からの援助を受けるのが難しく、自立生活に不安がある人に向けた介護施設 | |
| サ高住(サービス付き高齢者向け住宅) | 安否確認や生活相談サービスを受けることができる高齢者専門のバリアフリー賃貸住宅 | |
| その他 | 福祉用具の貸与・販売 | 手すりやスロープ、歩行器、歩行補助杖などの福祉用具のレンタル・購入が可能 (要介護度によって対応している用具が異なる) |
| 住宅改修 | 住み慣れた家で快適に過ごすことを目的に自宅を改修する際の費用に関して、一部支給を受けることができる |
要支援2の方は上記のサービスを利用することができますが、どれを使えばいいか分からないという方もいらっしゃるでしょう。
以下では、よく利用されているサービスについてご紹介しますので、利用するサービスの選択にお役立てください。
よく利用されているサービス
要支援2の方が利用できる介護保険サービスのうち、よく利用されているサービスは以下の通りです。
- 介護予防訪問看護
- 介護予防通所リハビリ
- 福祉用具貸与
それぞれのサービスについて解説します。
介護予防訪問介護
介護予防訪問介護は、看護師などが利用者の自宅に訪問し、療養上のお世話や診療の補助を行うサービスです。
厚生労働省の調査によると、令和3年度の介護予防訪問看護の利用者は約16万人となっており、訪問型のサービスのなかでは利用している人が最も多いサービスとなっています。
介護予防訪問看護では、健康管理や栄養管理といった要介護状態への進行・悪化を防ぐケアを受けることができるため、自立状態への回復が見込める要支援の方は利用が多い傾向にあります。
自宅での介護を検討しているかつ、要介護状態への進行・悪化を防ぎたい場合には、介護予防訪問看護の利用を検討してみるといいでしょう。
出典:厚生労働省「令和3年度介護給付費等実態統計の概況」
介護予防通所リハビリ(デイケア)
介護予防通所リハビリは、日帰りで施設に通い、要介護状態への進行・悪化を防ぐことを目的としたリハビリが受けられるサービスです。
厚生労働省の調査によると、令和3年度の介護予防通所リハビリの利用者は約25万人となっており、通所型の介護保険サービスのなかでは利用している人が最も多いサービスとなっています。
介護予防通所リハビリは、通常の通所型サービスと比べて専門的なリハビリを受けることができるため、自立状態への回復が見込める要支援の方は多く利用している傾向にあります。
要介護状態への進行・悪化予防、または自立状態への回復を目指す方は、介護予防通所リハビリの利用を検討してみるといいでしょう。
出典:厚生労働省「令和3年度介護給付費等実態統計の概況」
福祉用具貸与
福祉用具の貸与は、手すりやスロープ、歩行器をはじめとした福祉用具をレンタルすることができるサービスです。
厚生労働省の調査によると、令和3年度の福祉用具貸与サービスの利用者は約82万人となっており、多くの方が利用しているサービスであることが分かります。
前述のように、福祉用具の貸与では、手すりやスロープ、歩行器をはじめとした日常生活上の負担を軽減するための用具をレンタルすることができ、1か月あたりの費用も低額であることから、在宅介護をしている方の多くは利用しているサービスとなっています。
在宅での介護を検討している方は、手すりやスロープなどの自宅での生活をサポートする福祉用具の貸与サービスを利用してみてもいいのではないでしょうか。
出典:厚生労働省「令和3年度介護給付費等実態統計の概況」
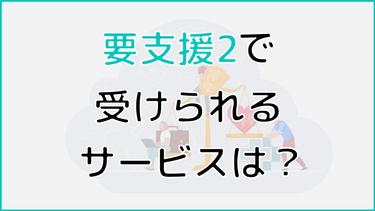
まとめ
本記事では、要支援2の方のケアプラン例をご紹介しました。
ケアプランは、要介護者の身体状況や生活環境などによって大きく異なるため一概には言えませんが、要支援2の方の場合は、介護予防訪問介護や介護予防通所介護を主に利用するケースが多いです。
要支援2で介護サービスの利用を検討する際には、本人の意思や家族のライフスタイルを十分に考慮したうえで、適切なサービスを選ぶことが大切です。
要介護2の方の場合は、介護予防訪問介護や介護予防通所リハビリを主に利用する方が多いと言えます。詳しくはこちらをご覧ください。
おすすめの介護保険サービスとしては、福祉用具の貸与が挙げられます。要支援2の方であれば、介護ベッドや車いすのレンタルも可能であるため、必要に応じて福祉用具のレンタルをするといいでしょう。詳しくはこちらをご覧ください。




