介護に関する悩みがあるけれど「地域包括支援センターの対象者はどんな方だろう?」「何を相談したらいいのかわからない?」という方もいらっしゃると思います。
多くの選択肢から、また特定の高齢者には選択肢が少ないかもしれませんがサービスの内容も知らないまま利用しない手はありません。
地域包括支援センターでは、生活、医療、介護に関するささいな悩みも相談が可能です。住み慣れた地域や場所で暮らしていけるようにアドバイスを受けられます。その内容に応じて関連する機関と連携をとり悩みや課題の解決に向けてどんな支援が出来るのかを具体化してもらえます。
この記事を最後まで読み終えてもらえたら、地域包括センターの利用可能な対象者と相談できる内容がわかります。地域包括支援センターをうまく活用したいと考えている方は、参考にしてください。
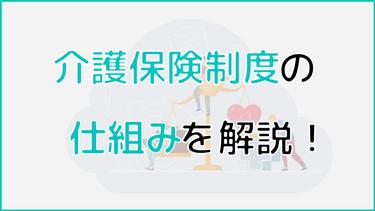
地域包括支援センターの対象者
地域包括支援センターの対象者は、該当地域住民なら65歳以上の高齢者の方、また高齢者の家族や地域の民生委員も対象に含まれます。
これまで、地域包括支援センターの対象者は、地域住民で支援を必要としている方たちとなっていました。
対象者の例
- 高齢者
- 難病患者
- 重症心身障害児者
- 精神障害者
少子高齢化が進む中、2065年には国民の約2.6人に1人が65歳以上になると推計されています。従来からの支援では現実的ではなくなってきているため近年ではその地域にあわせた医療・介護・予防(入浴支援、訪問介護、デイケア)の支援が進められています。
参照:内閣府-(2)将来推計人口でみる令和47(2065)年の日本
高齢者
高齢者は、65歳以上の方を指します。
活発だった母はふさぎ込んでいて薬の飲み忘れや服用の間違いを起こすようになりました。認知症の疑いがあるため要介護認定を受ける方法を知りたくて相談しました。まずは、介護認定検査員の訪問予約を手配してもらい、要介護認定の度合いによってケアプランをご相談とアドバイスを受けました。
独居の高齢者本人から遠方の家族へ「日常生活にてできないことが増えてきた」と連絡がありました。健康や生活の質を維持していくために何が出来るのかを友人に話したところ介護支援が必要じゃないの? それを受けて、家族は高齢者本人が居住する市役所に相談、介護認定調査員による訪問診断を予約しました。
要介護認定が判明したところで、具体的な介護支援の相談ができる「地域包括支援センター」を紹介されました。「地域包括支援センター」から要介護認定者にマッチしたサービスプランを提供できるケアマネージャーにつないでもらいました。
難病患者
難病患者は、発病の仕組みが明らかでなく、治療方法が確立していない希少な疾患にかかった方を指します。さらに、長期にわたり療養を必要とします。
既にお世話になっている支援センターの担当者と連携し地域包括支援センターに相談します。
対象者は以下のすべての要件を満たす必要があります。
- 日常生活に支障があり、介護等のサービスを必要とする者
- 難治性疾患克服研究事業の対象疾患(121疾患)及び関節リウマチの患者
- 医師により在宅療養が可能で安定していると診断されている者
- 老人福祉法、身体障害者福祉法、介護保険法などの施策の対象にならない者
自己で判断が付きにくいため、地域包括支援センターに相談しましょう。
40歳から64歳までの人でも、特定の疾病で要介護認定を受けている方なら入居対象となる介護医療院もあります。自宅でのケアが難しいという方は、ケアスル介護がおすすめ。まずはプロに相談してみませんか。
病気の解説・診断基準・臨床調査個人票の一覧(公益財団法人 難病医学研究財団/難病情報センター)
重症心身障害児者
重症心身障害者は、身体の機能に重度の肢体不自由と重度の知的障害があると認められ、さらに障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)を保持している方を指します。
重症心身障害児者は都道府県に支給申請し医療型障害児施設に入所していても18歳、もしくは最長でも20歳の時点で大人を対象にしたグループホームやケアホームの利用へと切り替わります。
ただ、障害の程度が重度である場合は、18歳を超えても重症心身障害児施設においては利用を可能とされています。65歳の高齢を待たずに該当地域の市区町村や福祉課、もしくは担当福祉士に相談し慌てないように準備しておきましょう。
自宅で療養している方で担当福祉士がいないのであれば早めに地域包括支援センターに相談しましょう。
参照:厚生労働省 障害者手帳
精神障害者
65歳以上の高齢者で精神障害により著しい生活困難を要する方で介護が必要な場合には重度訪問介護が存在します。支援内容は高齢者の介護支援と類似しており、食事、入浴、大切な投薬などの促しを対象者に合わせた介護計画が必要になりました。
既に地域によっては対応可能な地域包括ケアシステムが構築されている場合もありますので、地域包括支援センターへ相談しましょう。その点が不明な場合には普段から信頼しているかかりつけの心療内科で相談してみるのも1つの手段です。
地域包括センターへの相談だけでなく、施設を探している方は「ケアスル」がおすすめです。より幅広い選択肢から情報を得たい方は、まずは無料相談をしてみましょう。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
地域包括支援センターの対象年齢
地域包括支援センターが管轄する、対象地域に住む、65歳以上の高齢者になります。対象の高齢者が認知の問題で判断がご自身で出来ない場合にはご家族や支援者により代理の申請や相談が可能です。
近隣の地域包括支援センターがどこにあるかわからない場合には市区町村に確認してみるか検索して探してみましょう。
地域包括支援センターの役割
高齢者が出来る限り住み慣れた地域で過ごせるよう、包括的および継続的な支援を行うための中心的役割を果たすのが地域包括支援センターです。
高齢者やその家族が抱える高齢者の問題を解決するため、市区町村が設置主体となり相談にのってもらえる窓口です。保健師や看護師、社会福祉士、主任ケアマネージャーなど、専門知識をもった職員が在籍しており連携を取りながら相談に応じます。
では具体的に地域包括支援センターの5つの役割についてごらんください。
1.介護予防ケアマネジメント
要支援認定を受けた高齢者で要支援1と要支援2を受けた方を対象に、介護予防ケアマネジメントのプランを作成します。
介護予防サービス計画及び介護予防ケアプランは居宅介護支援事業所への委託も可能です。比較的介護度が低い高齢者の場合、ご自身の希望を聞きながら介護予防サービスの選択をするのが重要です。コミュニケーションに問題が無い場合にはご家族だけで決めてしまわないようにしましょう。
介護認定の有る無しにかかわらず多くの地域で開催される介護予防教室は、体力の低下が心配な65歳以上を対象としている場合が多いです。体操や自宅で出来るストレッチなどが含まれていますので、自宅にこもりがちだなと感じたらまずは試してみましょう。
2.総合相談・支援
相談窓口業務では、高齢者のあらゆる課題や悩み事の相談が受けられます。高齢者の支援を行うご家族はもちろんご近所の方からの相談も可能です。
例えば入浴時に立位やしゃがみこんだりするのが困難になってきた場合、シャワー椅子の購入についての相談もできます。もちろん介護ベッドや車いすのレンタルなども含まれます。
福祉や医療に関する制度は時として難しく、知っている人だけが恩恵を受けるという現状があります。ささいな悩みでも高齢者が抱える問題を、総合相談・支援窓口で相談すれば必要な制度や、利用可能な支援につないでもらいやすくなります。
それに付随し介護サービスを利用するのに必要な申請や介護保険に関する疑問なども相談してみましょう。
3.権利擁護
地域包括支援センターでは高齢者の判断力の衰えなどを悪用した消費者被害にあわないようにする活動を行っています。独居の高齢者ばかりを狙った契約の取り付け、詐欺の防止や対応も地域包括支援センターで行います。
虐待をしている者の自覚とは無関係に、高齢者の虐待も権利の侵害が生じていると判断されれば、地域包括センターの支援対象です。通報者を特定させるような情報の漏洩はしてはならない(法第8条)とされています。虐待に関しては家族でなくとも発見次第、地域包括支援センターへ通報できます。
なお、判断力の低下により高齢者自身で自分の財産や権利を管理できなくなる兆しが見えたら、成年後見制度(後見人をつける)の活用を検討しましょう。こちらも地域包括支援センターで相談できます。
4.包括的・継続的ケアマネジメント支援
包括的に支援が必要な高齢者は、1つのサービスでは不十分なため複数の支援の組み合わせと各窓口の連携も必要となります。また、継続的な支援が必要な高齢者には介護はもちろん、予防、日常生活支援、医療、住宅においてもすぐに役立てるよう関連機関の連携を呼びかけが行われます。
包括ケアシステムを実現化するために地域ケア会議と呼ばれる会議が開かれ、地域住民や医療、介護にかかわる専門家が出席します。「個別ケースの支援内容の検討」「ネットワークの構築」「地域課題の把握」「資源の開発」「政策形成」などの機能をもっており、いずれも高齢者への支援の充実、それを実現するための社会基盤の整備が目的です。
関連機関への連携呼びかけや、地域の資源・基盤整備を行う事で直接的な介護支援専門員( ケアマネジャー ) に対する支援を行うものです。
5.介護予防支援務業
介護を必要とする高齢者や障害者などの介護の予防に向けた支援をする業務です。
介護予防の定義とは?
- 要介護状態にならないよう支援を行う
- 要介護状態にあってもその進行がすすまないように支援を行う
これには健康の維持はもちろんのこと生活の質の向上への支援、出来る限り地域で自立した日常生活を営めるように支援する業務になります。
| 介護の種別 | 介護の内容 |
|---|---|
| 介護予防訪問入浴介護 | 浴槽を積んだ入浴者で家庭で入浴介護 |
| 介護予防訪問看護 | 主治医の指示のもと看護師などが家庭で看護 |
| 介護予防訪問リハビリテーション | 理学療法士等が家庭を訪問し、機能訓練 |
| 介護予防通所リハビリテーション | 介護老人保健施設や医療機関で、機能訓練等を日帰り |
| 介護予防福祉用具貸与 | 介護予防に資する福祉用具を貸与 |
| 介護予防短期入所生活介護 | 介護老人福祉施設等において、短期間入所された方の介護 |
| 介護予防短期入所療養介護(介護老人保健施設) | 介護老人保健施設等において、短期間入所された方の介護を行う |
出典:居宅介護支援・介護予防支援 – 総費用等における提供サービスの内訳(平成30年度)
地域包括支援センターで相談できる内容とは
高齢者の抱える困りごとからその家族の抱える悩みまで相談が可能です。地域包括支援センターには介護保険のサービス、自治体独自の制度やサービス、民間の団体が提供するサービスなど地域における介護関係の情報が集まっています。介護に直面してから制度や手続きに迷った時も相談するとよいでしょう。
ただ、1つ注意が必要なのは対象となる高齢者の住民票がある自治体が主体になりますので、対象の地域で相談しましょう。
それでは、こんな内容でもいいの?と思える具体的相談事例をご案内します。
1.退院後の支援
元気で一人暮らしのAさん(78歳・男性)、転倒による頭部打撲により救急搬送され入院となり、検査を受けて認知症と診断を受ける。安静を必要とするが、Aさんにその認識のないまま、退院となりました。
退院後、地域包括支援センターと地域の専門医により支援を開始。そのあと、地域包括支援センターが、地域ケア会議を開催し、Aさんを見守る地域での支援ネットワークを構築しました。
Aさんの希望通り自宅で一人暮らしを続けながら、週に1回、健康管理と服薬支援を目的とした訪問看護を開始。通所介護(デイケア)に行く前や看護師、薬剤師が訪問した際は、服薬の促しをしてもらっています。
2.共同生活への悩み支援
76歳になるSさん(女性)は長年、教師を生業として生きてきました。独身のまま定年を期に地方都市に移住をしたため挨拶を交わす程度の付き合いはあれども、心の底から深くかかわる友人もありませんでした。
しかしこの地域のグループホームに見学に行ったけれど他の入所者と折り合いをつけていけるだろうか、共同生活への不安がよぎりました。本格的に介護も必要になる年齢だと察したCさんは自ら地域包括支援センターへ出向きます。
相談員はSさんの経歴と希望を受けて、幼稚園併設の老人ホームの見学を案内しました。
Sさんは現在、幼老ホームへ入るための準備をすすめています。
3.認知症への対応
現在は1人暮らしのTさん(81歳・男性)、以前はゴルフにでかけたり活発に活動してましたが、心筋梗塞を患ってからは自宅まわりを散歩する程度になっていました。
遠方に住む娘が電話をかけても出ないため、どうしたものかと思案していたら本人から電話がかかり「2階に上がれなくなった」と報告を受けました。
慌てて駆けつけるといつの日からか1階の居間で就寝していた様子。まさか認知症だとはまだ思っていなかったのですが、先週病院に行った時に発行され薬の引き換え券が机においてありました。心臓の薬をもらい忘れている事実に疑いが深まり市役所に出向き相談したのです。
介護認定検査員の訪問を受けたところで地域包括支援センターに連絡するよう紹介されました。そこからはケアマネージャから介護サービスの申請をしてもらい、今では毎日介護ヘルパーさんの訪問を受け、食事や薬の管理をお願いしています。体力が回復したあたりでデイサービスにも通えるようになりました。家族だけで頑張らずにお願いして良かったです。
4.虐待の対応
Fさんのお隣のご夫婦(ご主人・82歳、奥様・75歳)は2人で旅行にでかけたり仲が良く、町内会の班長も務めてくれる頼りになるご夫婦でした。奥様の風呂場での転倒が原因で腰の骨折から長く入院されたとはうかがっていた。それにしても最近ご主人の姿もみかけないなと心配していました。
Fさんはご主人が食事などで困っていないかお隣を訪ねてみたところ、玄関はペットボトルが散乱しておりご主人も以前と違い身なりも変わり果てていたためもしかしたらセルフ・ネグレクトかもしれないと思いFさんは地域包括支援センターに相談した。
相談員のすすめで介護サービスを申し込み、週に2回ヘルパーさんに身の回りの世話をお願いしている。
5.運動機能の低下に関する悩み
80歳1人暮らしのHさん(女性)は認知症などの症状はないが、犬との散歩時に足元が不安なので杖を利用している。もともと、体を動かすのが好きだったが年々他者との交流も減り体の衰えが心配になってきた。
地域包括支援センターに相談し、この先、元気に1人暮らしを続けていくには運動や体操などが出来る場所を紹介してほしいと希望。
相談を機に介護認定検査員による訪問診断を受け、要支援 1 の認定を受けた。利用可能なデイケアサービスや介護予防教室をご案内したところ予防教室が楽しかったと喜んでおられます。
地域包括支援センターに相談するときにチェックしたいこと
地域包括支援センターを賢く使いこなすためには、事前にチェックし相談内容を書き出す手間もおしまないでください。
- 無料で相談できる範囲は?
- 地域包括支援センターの場所は?
- 在籍している専門家の職種は?
事前に知っていれば何を相談できて何が相談できないのかを判断できます。
地域包括支援センターは、市区町村直営が20%、委託型が80%(令和4年4月末現在 厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課調べ)のため、一口に地域包括支援センターと言ってもそれぞれの事業所による特色があります。
具体的な質問内容をリストアップし、自分にあったサービスを提供してくれる地域包括支援センターを活用しましょう。
1.相談料金
地域包括センターは、お住まいの地域に設置されており無料で介護の相談ができます。65歳以上の高齢者の悩み事や家族だけでは解決できないささいな内容でも地域包括センター相談窓口をご利用ください。
また、対象地域の方の生活全般、財産、権利などを守る目的で各種専門家によるご相談ができます。ご希望によりご自宅への訪問による相談も受けています。
しかし、紹介された施設やサービスの利用時に費用が発生する場合もあります。費用の負担に関しても介護申請や介護保険サービスにくわしい地域包括センターで相談されるといいでしょう。
出来るだけ費用を抑えて老人ホームに入りたいという方はケアスル介護で探すのがおすすめです。
ケアスル介護では全国で約5万件の施設情報を掲載しているので、自分に合った施設を探すことが出来ます。後悔しない老人ホームがしたいという方はぜひ利用してみてください。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
2.地域包括支援センターのある場所
地域包括センターは全国に5,404か所が設置されています。(令和4年4月末現在 厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課調べ) また、「ブランチ」「サブセンター」を含めると7,409か所となり、その内訳は市町区村直営が20%、委託型が80%となっています。
地域包括センターはすべての市区町村に必ず設置されており、おおむね人口の2~3万人に1か所が目安となります。
名称は地域によって異なる場合があります。
- 「サブセンター」とは地域包括支援センターと一体的に包括的支援事業を実施する支所
- 「ブランチ」とは地域住民により近い所で相談を受付け、センターにつなぐための窓口
| センターの形態 | 設置数 |
|---|---|
| 地域包括支援センター設置数 |
5,404 か所 |
| ブランチ設置数 |
1,647 か所 |
| サブセンター設置数 |
358 か所 |
| 合計 |
7,409 か所 |
出典:令和4年4月末現在 厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課調べ
3.在籍している専門家
地域包括支援センターが円滑に機能できるのは、保健師、(主任ケアマネジャー)主任介護支援専門員、社会福祉士の専門家が在籍しているからです。
それぞれの専門知識を活かし、横のつながりをもって情報を共有し、チームとして業務全体を支えてれる信頼できる相談相手です。
誰に相談すべきかを悩まなくても気軽に相談できるのが地域包括支援センターのよいところです。またその相談によって費用を請求されませんので安心してご相談ください。
| 専門家 | 役割 |
|---|---|
| 保健師(国家資格) | 健康面での相談、保険指導、介護予防ケアプラン作成 |
| 主任介護支援専門員(5年更新) | ケアプランの相談、包括的サービスを提供を目的としたネットワーク構築、ケアマネジャーの指導、ケアシステムの構築 |
| 社会福祉士(国家資格) | 生活相談全般、介護予防ケアマネジメント業務、権利擁護業務、 |
出典:地域包括支援センターについてー厚生労働省(2023年1月27日)
地域包括支援センターを利用するメリット
地域の住民にとって地域包括支援センターは気軽に相談できるところが一番のメリットですが、利用者が経験した、知ってもらいたいメリットを箇条書きにしてみました。
- 無料で相談が受けられる
- 専門家に直接相談ができる
- 複数の問題を一か所で相談できる
- 医療・介護サービスが高齢者の居住地域で受けられる
- 家族の負担が軽減される
- 認知症がはじまった要介護者であっても自宅で暮らしていける
- 高齢者本人だけでなく家族や地域の住民も相談できる
- 対象の高齢者に合わせた支援を受けられる
個々の相談者が専門家をたずね歩く必要がないため、相談者の負担が軽減されます。
1.気軽な相談から本格的なケアができる
地域包括支援センターは高齢者の悩みや介護の相談が無料の窓口です。ほんのささいな相談から対象である高齢者の生活スタイルを聞き取り、ご家族の置かれている状況や体調、介護度の調査までスムーズに行われます。
一度決まった介護計画だとしても、サービスの回数や曜日の入れ替えなど、考えが変われば違ったサービスの検討もしてもらえます。高齢者の介護でこんな問題が解決出来たらいいのにを、遠慮せず気軽に相談してください。
2.高齢者の虐待問題を早く見つけられる
地域包括支援センターでは、高齢者の虐待や権利侵害の疑いがある場合の相談を受け付ける窓口でもあります。
介護者が自分は大丈夫と思っていても、介護疲れや介護ストレスから本人に自覚がなくとも、いつ虐待が発生するかわかりません。高齢者の虐待問題は介護者や、介護が必要な高齢者の扱いに精通しているであろう介護施設の職員の間でも起こり得る深い問題です。
本当はだれかに介護を支援してもらいたい潜在意識がかくれているのではないでしょうか。
虐待者側の要因にあるように、外部サービス利用への抵抗感や「介護は家族がすべき」といった周囲の声、世間体に対するプレッシャーなどから、誰にも話せない方もいるかと思います。そういう方こそ勇気をもって地域包括支援センターへ相談してもらいたいものです。
高齢者の虐待にいたる、複数の要因を取り除けば解決を見る可能性も高くなります。
地域包括支援センターは誰でも相談できます。もし、近隣住民で高齢者の虐待を疑われるような事象を見かけられましたら相談しましょう。
虐待の発生要因(複数回答)虐待者側の要因
| 虐待者側の要因 | 割合(%) |
|---|---|
| 介護疲れ・介護ストレス |
52.4 |
| 被虐待者との虐待発生までの人間関係 |
47.3 |
| 理解力の不足や低下 |
46.3 |
| 知識や情報の不足 |
45.1 |
| 虐待者の介護力の低下や不足 |
43.7 |
| 他者との関係のとりづらさ・資源への繋がりづらさ |
35.6 |
| 孤立・補助介護者の不在等 |
33.3 |
| 虐待者の外部サービス利用への抵抗感 |
22.2 |
| 「介護は家族がすべき」といった周囲の声、世間体に対するストレスやプレッシャー |
10.1 |
虐待の発生要因(複数回答)
| 被虐待者の要因 | 割合(%) |
|---|---|
| 認知症の症状 |
55.0 |
| 身体的自立度の低さ |
42.9 |
| 精神障害(疑いを含む)、高次脳機能障害、知的障害、認知機能の低下 |
31.5 |
| 排泄介助の困難さ |
28.9 |
| 外部サービス利用に抵抗感がある |
15.7 |
出典:令和 3 年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果(添付資料) – 虐待の発生要因(表 38)
3.地域性に合った介護サービスを受けられる
地域に密着した介護サービスを受けられるのが最大のメリットです。
地域の課題を解消するために開かれた地域ケア会議や構築された地域包括ケアシステムより介護サービスが提供されます。高齢者を支援する方に寄り添ったその地域でしか構築できないネットワークと資源を利用できるのも魅力です。
地域包括支援センターが使えない・ひどいといわれる理由とは
地域包括支援センターでは各種専門家をそろえ、介護についての悩みを支援しようと活動しています。
しかし、なんらかの行き違いで「使えない」「ひどい」と不満を持っている方も一定数いるのではないでしょうか。
その理由の一つとして、相談者も窓口になる専門家も人間ですから相性や言葉の使い方1つで信頼関係を失うのも現実です。
考えられる例を挙げてみましょう。
| 不満要因 | 解決方法 |
|---|---|
| マッチするサービスが受けられない | 理由によっては、他のセンターを探す |
| 担当者とうまが合わない | 担当者をかえてもらう |
| 経験豊富な専門家と話したい | 他の専門家を紹介してもらう |
| 相談内容に対応できないと言われた | 相談内容を見直しましょう |
どうしても意思疎通がうまくできない、もっと経験豊富な方に相談したいなどがありましたら無理をせずに担当者を変えてもらうか、可能であれば他の地域包括支援センターをあたってみるのも1つの解決手段です。
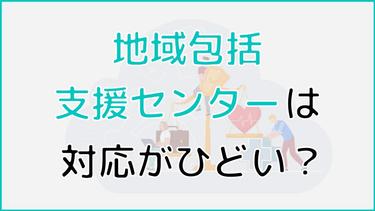
担当者を変えてほしいなんて言い出せない方はケアスル介護で探すのがおすすめです。ケアスル介護では全国で約5万件の施設情報を掲載しているので、自分に合った施設を探すことが出来ます。まずは無料相談をしてみましょう。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
まとめ 地域包括支援センターの対象者であればどのような内容でも相談可能
高齢になった親の悩みがあるけれど誰に相談したらいいか分からないと悩んでいるなら、気軽に地域包括支援センターや市区町村の窓口に相談しましょう。そして、介護は在宅だけでなく外部の施設を利用するなど、無理のない方法も検討しましょう。
介護にかかる費用について心配だという場合にも、公的な制度や支援について相談し申請を手伝ってもらうなども可能です。家族だけで抱え込まないで、さまざまな支援を活用し大切な家族と住み慣れた地域で暮らしていけるように本記事で紹介した内容をもとに相談してみてください。
これまでご紹介してきた内容を一覧にしてまとめてみました。参考にしてください。
| 地域包括支援センター(専門家による相談窓口) | |||
|---|---|---|---|
| 専門家 | 保健師 | 主任介護支援専門員 (主任ケアマネジャー) |
社会福祉士 |
| 相談料金 | 無料 | ||
| 相談方法 | 地域包括支援センター | 家庭へ訪問 | 電話・メール |
| 地域包括支援センターのある場所 | 市区町村に1カ所以上設置されている | ||
| 介護の相談 | 介護保険 | 介護認定 | 申請方法 |
| 健康の相談 | 足腰の弱りの不安 | 独居に起因する不安 | 予防ケア |
| 家族の相談 | 介護の不安 | 遠方に住む親が心配 | 老老介護 |
| 近隣の高齢者の相談 | セルフ・ネグレクト | 声かけ確認 | 虐待 |
| お金や財産の相談 | 管理能力の低下 | 振り込め詐欺被害 | 成年後見制度 |
対象地域に居住し65歳以上の高齢者なら誰でも利用が可能です。高齢者を支援する家族や地域住民、民生委員も対象に含まれます。詳しくはこちらをご覧ください。
「地域包括支援センターの役割とは?」「相談料金は?」「地域包括支援センター場所は?」「在籍している専門家は?」などを、事前に知っていれば何を相談できて何が相談できないのかを判断できます。詳しくはこちらをご覧ください。




