地域包括支援センターを利用している高齢者やご家族の中には、不満を抱えていても苦情をなかなか言いだせない方も多いのではないでしょうか。
お世話になっているという思いから、本音を言い出せず我慢をしていると、さらに不満が募り、不信感や嫌悪感に繋がります。
そこで、今回はどこへ苦情を相談すればいいのか、苦情事例もあわせて紹介します。よりよい関係を作るためのポイントもお伝えしますので、ぜひ参考にしてみてください。
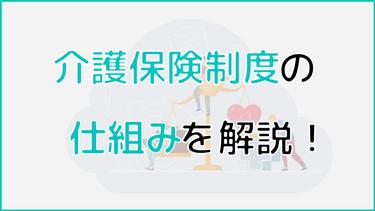
地域包括支援センターに対する苦情はどこへ相談するのか
地域包括支援センターに対する苦情は、各市町村に設置されている苦情相談窓口へ相談してください。また、苦情相談をする場合は、段階的に相談窓口が異なってきます。
主な相談窓口として設置されているのは、次の通りです。
- 利用している施設または事業所
- 各市町村の相談窓口
- 各都道府県の運営適正委員会
- 国民健康保険団体連合会
それぞれについて詳しく解説します。
利用している施設または事業所
利用している施設または事業所の経営者や管理者に相談してみてください。話し合いで解決する場合もありますので、ささいな疑問や不安はため込まず、相談してみることが大切です。
また、地域包括支援センターの職員や専門スタッフとして在籍している保健師、社会福祉士、ケアマネージャなどと直接話し合うことも可能です。
他の施設をご検討されている方にはケアスル介護がおすすめです。ケアスル介護では、約5万件の施設情報が掲載されており、無料でどんなお悩みにも解決できるようにアドバイスしていますので、お気軽にご相談ください。
各市町村の相談窓口
各市町村には、苦情相談窓口が設置されています。第一次の苦情に対応する窓口として介護保険制度の運営基準に記載されており、匿名での相談も可能です。利用している施設や事業者には話しにくいときなどにも利用できます。
施設や事業者に直接苦情を言うと、不都合なことが起こるのではと心配な方や先行きが不安で言い出せないときにも安心して相談できるでしょう。
運営適正委員会
各都道府県で設置が義務付けられている運営適正委員会は、介護サービスの苦情を解決に導くための第三者機関です。各市町村の窓口では解決できなかったトラブルや自力では解決できないときに相談に乗ってくれます。
さまざまな知識を有する委員会が公正かつ中立的な立場で、トラブルを解決するためのサポートや調査をおこないます。ただし、苦情対応は限定されており、対象となるのは次の通りです。
- 訪問介護
- 通所介護
- 短所入所生活介護
- 認知症対応型共同生活介護
- 指定介護老人福祉施設
上記、記載以外の施設に対する苦情の受付は対象となっていません。
国民健康保険団体連合会
各都道府県に設置されているのが国民健康保険団体連合です。各市町村の相談窓口や運営適正委員会で解決できない問題や苦情に対応しており、苦情申立ができる機関です。
苦情申立により施設や事業所に対して調査をおこない、状況に応じて助言や指導をします。どうしても解決できないトラブルの最終的な相談窓口です。
地域包括支援センターに対する苦情を伝える相手
地域包括支援センターに対する苦情を誰に伝えるべきなのかは、利用している施設や事業者によって異なります。居宅サービスを利用している場合と老人ホーム等の施設を利用している場合に分けて解説します。
また、各市町村の相談窓口や国民健康保険団体連合会に苦情申立をする場合についても説明していきます。
居宅サービス
居宅サービスを利用している場合、苦情を伝える相手は次の通りです。
- 事業者や施設の責任者
- 担当のケアマネージャー
ただし、介護サービスに関する相談以外になると、対応が難しい可能性があります。不満や不安に感じていることが、どのサービスに対しての苦情なのかを明白にしておくとよいでしょう。
老人ホームなどの施設
老人ホームなどの施設を利用している場合、苦情を伝える相手は次の通りです。
- ケアマネージャー
- 生活相談員
- 施設などの施設長や責任者
- 老人ホームなどの経営者
どの施設にも利用するときには、仲介役や相談に乗ってくれる方がいますので、何かあれば抱え込まずに相談してください。
自治体や国民康保険団体連合会の場合
居宅サービスや施設など以外に苦情を伝えたい場合は、本人または当事者の家族が自治体や国民康保険団体連合会に相談してください。
苦情相談窓口や国民健康保険団体連合会の連絡先は、契約書や重要事項説明書に記載されています。またホームページでも確認可能です。
地域包括支援センターに対する苦情事例
地域包括支援センターに対して、介護サービスを利用している方からさまざまな苦情が発生します。そこで、職員に対して、また施設に対して寄せられた苦情事例を紹介します。
職員の応対
職員の応対に関しての苦情は、親身になって相談してもらえないなど、利用する際の不満や不安からの問題が多いです。事例には、次のようなものがあります。
苦情事例
| 1 | 介護保険で手すりを付けたいが、地域包括支 援センターの職員の話が分かりづらい上、必要のない話をしてくる。そのため、手すりを取り付けるには何をしてよいか分からない。 |
| 2 | 地域包括支援センターへ相談したところ、家族で解決して欲しいと、話を聞いてくれる感じではなかった。現在要介護認定の新規申請中で あり、要支援になったら当該地域包括支援セン ターが担当となるが、相談しづらい。 |
| 3 | 地域包括支援センターの職員が、親身になっ
て相談にのってくれない。 |
※引用元:東京都国民健康保険団体連合会「行政の対応に関する事例」
施設の応対
職員に対してではなく、施設に対しての苦情です。施設や事業者に対しての不満は、ほんのささいなことも少なくありません。介護サービスを提供している側の少しの工夫で解決できる問題もたくさんあります。施設に従事しているスタッフの質の問題にも関わっています。
苦情事例
| 1 | 認定結果通知の印字が薄くてわかりにくい。 結果通知が全体に薄く文字が読めない。高齢の 方への文書なので、インクは濃くして送付する べきだ。 |
| 2 | 地域包括支援センターの受付窓口が1つしかないため、ゆっくりと相談できない。 また、長時間待っていたが、他の職員が気を効かせて用件を聞きに来るなどの配慮がなかっ たことも気になった。 |
| 3 | 土曜日も窓口が開いているということを知 り、事前に連絡をしてから、家族の介護保険の 認定申請のため地域包括支援センターへ行った。到着し、椅子に腰かけていると、突然職員 から「何だお前は」「そこに座るな」「外で待っ ていろ」等と言われた。 |
※引用元:東京都国民健康保険団体連合会「行政の対応に関する事例」
地域包括支援センターの役割
各市町村が運営している地域包括支援センターでは、高齢者が住み慣れた街で安心して暮らせるようにさまざまなサポートをしています。
また、地域包括支援センターは、全国に約5,000以上もありますが、実際に運営しているのは、各市町村から委託された社会福祉法人や社会福祉協議会がほとんどです。
地域包括支援センターの主な役割としては、次の4項目があげられます。
- 高齢の方の相談窓口
- 権利擁護
- ケアマネジャーのサポート
- 介護予防サポート
それでは、以上4項目について、詳しく解説していきます。
※参考:厚生労働省「地域包括支援センターの業務(参考資料)」
高齢の方の相談窓口
高齢者の方の総合的な相談窓口としての役割を担っています。また、高齢者だけでなく、その家族に対しても心配事や不安・悩みなどの相談を受けつけており、問題解決のサポートをおこなっています。
介護サービスに関することだけでなく、地域全体で総合的に高齢者を支えています。
権利擁護
権利擁護とは、高齢者がもつ権利をさまざまなトラブルや事件に巻き込まれないようにサポートすることです。高齢になると判断力が低下し、虐待被害への対応ができなかったり、詐欺から身を守れなかったりする場合があるので、安心して日常生活を送れるように支援します。
また、万が一認知症を発症し、金銭管理できなくなったときには、成年後見制度の手続きのサポートもしています。
高齢の方が安心して日常生活を送れるように支援し、高齢者のさまざまな権利を守っているのです。
ケアマネジャーのサポート
ケアマネージャーだけでは、たくさんの高齢者をサポートするのには限界があります。そのため、高齢者個人ではなく、幅広く地域社会全体をサポートする役割を担っています。
例をあげると、地域ケア会議の実施や、ケアマネージャに対しての個別相談やアドバイスをするなどです。
また、高齢者だけでなく、地域全体の各専門分野の専門家も含めて、幅広いネットワークづくりにも貢献し、よりよい地域づくりのための活動に力を尽くしています。
介護予防サポート
要支援や要介護の認定を受けた高齢者に対して、状態の悪化を遅らせたり、自立するための支援をしたりして、長く健康を維持できるようサポートします。
介護が必要になる可能性がある高齢者に対しては、次のような介護予防サービスの紹介や参加をすすめて、健康維持できるように支援しているのです。
主な介護予防サービスとして、次のようなセミナー・教室があります。
- 口腔ケアセミナー
- 認知機能低下予防セミナー
- うつ予防セミナー
- 運動機能向上のための教室
- 引きこもり・閉じこもり予防のための教室
なにより、高齢者自ら健康に興味をもってもらい、健康維持に努めてもらえるようにサポートしています。
地域包括支援センターへの苦情の要因
地域包括支援センターへの苦情が発生する要因がどこにあるのか把握することで、根本的な問題の解決に近づける可能性があります。
そこで、ここではなぜ苦情に発展してしまうのかについて解説します。施設によっても業務量や質にも差があるため、一概には言えませんが、一人でも多くの声をあげることが解決の糸口になるかもしれません。
従業員の業務量過多
前述でも説明したように地域包括センターには、さまざまな役割があります。そのため、仕事量が多く、仕事量と人員のバランスがとれていない可能性が高いです。介護サービスを利用するときには、十分なスタッフが在籍しているかも利用する事業所や施設の判断基準にしてください。
直接関わる機会が少ない
地域包括支援センターでは、仲介的な役割も多く、直接・長期的に利用者との関わりがないため、親身になってくれないと感じ、苦情につながることも多いです。
また実際に、地域包括支援センターの存在が知られていなかったり、どういう役割を担っているのか、知らない人が多かったりするのも不満に思われてしまう要因の一つでしょう。
従業員の力量に個人差
前述でも記載した通り、地域包括支援センターとしての役割が多く、業務量が多くなってしまいがちです。そのため、きちんとした教育もできないので、優秀な人材も育ちません。
熟練スタッフだけが充分な対応ができていても、人員不足のため新しいスタッフの教育ができず、仕事の出来不出来は個人差が目立ちます。
人によって提供サービスの個人差が生まれ、対応にも違いが出てくるため、苦情に繋がってしまうのです。
地域包括支援センターに対する苦情をなくすために
地域包括支援センターに対する苦情は、利用する側も極力言いたくないものです。お互いよりよい関係でいるためにも、受け身になるのではなく、小さなことでも相談できる関係性が大切です。
話し合うことで解決することもあるので、苦情に発展する前に相談するとよいでしょう。
信頼関係を築く
介護サービスを利用するにあたり、普段からどんなささいなことも相談できる関係性を築いておくことが大切です。人と人との信頼関係は、簡単に築けるものではありません。
そのため、時間を要するかもしれませんが、親身に相談に乗ってくれる信頼のおけるスタッフを探しておきましょう。
万が一、直接相談しにくい場合は、第3者機関でもかまいませんので、何かトラブルが起きたときにはすぐに相談できるようにしておくと安心です。
苦情を言いやすい環境づくり
何でもいえる環境づくりは、施設や事業所にも対応が必要ですが、利用者側も普段から相談できる環境を作っておくことが大切です。苦情というとマイナスに捉えられがちですが、伝えなければ、何も伝わりません。
そのため、改善策として提案したり、気軽に相談できるように施設や事業所に交渉するのも一つです。
介護施設のご検討されている方にはケアスル介護がおすすめです。ケアスル介護では、入居相談員にその場で条件に合った施設を教えてもらうことができ、無料でどんなお悩みにも相談を受けられるので、お気軽にご相談ください。
地域包括支援センターに対する苦情があるときは
地域包括支援センターに対して苦情があるときは、まずは声をあげることが大切です。関係性が悪くなるかもと心配して何も言えずにいると、ご自身にとっても最良の選択とは言えません。
本音を伝えることで、改善策も考えられる可能性もあるので、まずは、不満や不安は抱え込まずに何事も相談するとよいでしょう。
そのためにも普段から、なんでも相談できる信頼性を築くことが大切です。不安や悩みがあれば、ケアスル介護では無料相談も可能なので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
まずは直接関わりのある施設や事業所に相談してください。万が一、相談しにくい場合は、各市町村の相談窓口に問い合わせるとよいでしょう。それでも問題が解決しないときは、運営適正委員会や国民健康保険団体連合会に相談してください。詳しくはこちらをご覧ください。
まずは身近な関係者に相談してください。普段からコミュニケーションをとり、問題が起こる前に相談できる環境を作っておくことをおすすめします。詳しくはこちらをご覧ください。






