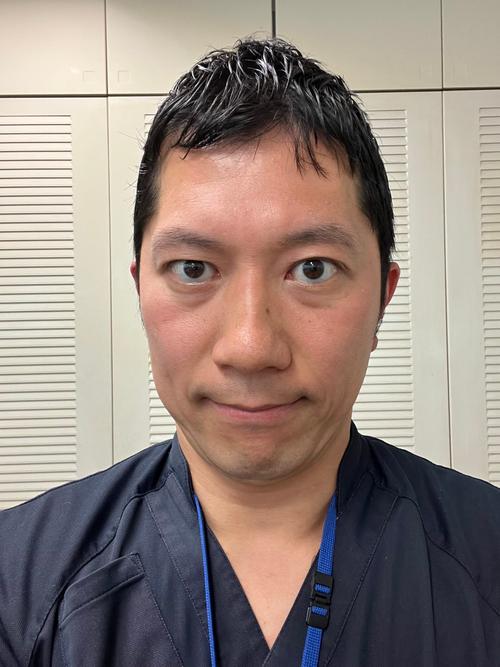「なんで認知症になったら徘徊するの?」「徘徊で安全を守る対策はないの?」などと悩んでいる方は多いでしょう。
認知症の症状の一つである徘徊。徘徊すると、外出先から自宅に戻れなくなったり、目的を忘れてしまいいつまでも歩き回ったりするケースがあり、近年は社会問題化しています。家族の方が認知症となり徘徊したら心配です。
そこでここでは認知症徘徊の原因と安全を確保するための対策についてご紹介します。徘徊を予防するグッズについてもご紹介するので、最後までご覧ください。
認知症徘徊は認知症症状の一つ?
認知症徘徊とはどのようなものなのでしょうか。認知症徘徊とは目的もなく歩き回る動作を指します。ここでは認知症徘徊について以下に分けてご紹介します。
● 安心できる場所を求める行動
● 認知症徘徊の現状とは
● 認知症徘徊が生命の危機になる場合も?
認知症となった方が必ず発症する中心症状とは異なります。それぞれについて具体的にご紹介します。
安心できる場所を求める行動
安心できる場所を求める行動の一つが認知症徘徊です。認知症の症状には大きく分けて以下の2つの症状があります。
● 中核症状
● 周辺症状
中核症状は認知症の方すべてに現れる症状であり記憶障害や見当識障害などです。周辺症状は本人の性格や体調、生活環境などが起因となり現れます。
認知症徘徊は、認知症の周辺症状の一つであり、「何かをしないとストレスを感じる」などの不安や焦燥感などの心理的な要因から、外に出かけて、安心できる場所を求めてしまう行動です。
認知症徘徊の現状とは
認知症徘徊は近年社会問題化しています。警察庁によると「2020年の行方不明者は77,022人。そのうち疾病関係は23,592人で、認知症の方は17,565人。実に行方不明者の2割は認知症による」とされています。
また、認知症徘徊による行方不明者の推移については以下の表の通りです。
| 年 | 行方不明者数 |
| 2016年 | 15,432人 |
| 2017年 | 15,863人 |
| 2018年 | 16,927人 |
| 2019年 | 17,479人 |
(参考URL:警察庁「令和2年における行方不明者の状況」)
2016年に15,432人であった認知症徘徊による行方不明者数が、2019年には17,749人と3年間で約2,000人増加しています。
今後も高齢者社会の進行に伴い認知症の方が増加するため、認知症徘徊による行方不明者数の増加が推測されます。
認知症徘徊が生命の危機になる場合も?
認知症の方が徘徊する理由は、外出する理由と変わりません。歩く能力が低下していない限り、徘徊は誰にでも起こりえます。
認知症徘徊には生命の危険がともなう可能性があるため、注意しなければなりません。以下の状況の際に生命の危険が伴います。
● 交通事故に遭う可能性
● 行方不明者となる可能性
● 熱中症や脱水症状を起こす可能性
● 低体温症となる可能性
それぞれの状況について具体的にご紹介します。
交通事故に遭う可能性
徘徊している際には自分の置かれている状況が分からなくなったり、混乱していたりする状況の中で歩き回っている場合があります。
周囲の状況に注意が払えなくなるため、車や自転車、電車などに気づけません。そのため、交通事故に遭う可能性があります。
行方不明となる可能性
認知症の方が徘徊するには、「買い物に行きたい」「友人の家に行きたい」など何らかの目的があり徘徊しています。
しかし、徘徊している途中でその目的を忘れてしまいます。そのため、自宅に戻れなくなり、そのまま行方不明となる可能性があります。
熱中症や脱水症状を起こす可能
徘徊している際は、混乱している状況の場合が多いため、水分補給したり日陰で涼んだりすることができません。そのため、夏場に徘徊している場合は熱中症や脱水症状を起こす可能性があります。
低体温症となる可能性
認知症の方が外に出ようとするときに、防寒をするなど服装に注意を払えません。また、気温に関わらず歩き回ります。そのため、冬場の徘徊であれば低体温症となる可能性があります。
認知症の方の介護が不安になったら、介護施設への入居を検討してみるという手もあります。
ケアスル介護なら、認知症の度合いや年齢、予算に合わせてあなたに合った介護施設を探すことが可能です。
問い合わせフォームから簡単に相談可能ですので、ぜひ一度相談してみてはいかがでしょうか。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
認知症徘徊の5つの原因と動機とは
認知症徘徊はなぜ起こるのでしょうか。以下の原因と動機が考えられます。
● 道に迷ってしまう
● 自宅がわからなくなってしまう
● なぜここにいるのか忘れてしまう
● 昔していた行動をしようとしてしまう
● 心地よい場所を探そうとしている
ここでは認知症徘徊が起こる5つの原因と動機についてそれぞれ具体的にご紹介します。
道に迷ってしまう
認知症の方には記憶障害や見当識障害がみられます。記憶障害があるとこれまで辿ってきた道順や目標としていた目印を忘れ、見当識障害があると慣れている場所でも道に迷う場合があります。
道に迷うのは屋外でばかり発生するわけではありません。屋内でも迷う場合があります。「トイレに行きたい」「お風呂に入りたい」など目的があるにもかかわらず、場所がわからなくなってしまい、迷い続ける場合があります。
自宅がわからなくなってしまう
見当識障害があると自宅にいるにもかかわらず「自宅はどこ?」と探してしまう場合があります。自宅である認識が持てないのです。
また、記憶障害により若いころの感覚となってしまい、昔暮らしていた場所や家に帰ろうとする場合もあります。しかし、現在と昔では街並みが全く違うため歩き回ると徘徊とされます。
なぜここにいるのか忘れてしまう
出かけたばかりのときは、「病院に行っている」「外食しにお店にきた」などと認識できます。しかし、目的地に向かっている途中や病院の待合室、レストラン内で記憶障害によりなぜここにいるのか、現状を認識できなくなってしまうのです。
現状を理解するために外に出て場所を確認したり、場所を把握するために探索したりしようとした結果、さらに現状がわからなくなってしまう場合があります。
昔していた行動をしようとしてしまう
過去にしていた習慣を同じようにしようとすると、徘徊とされる場合があります。定年退職後に会社へ行こうとしたり、わが子が幼いころに通っていた幼稚園に迎えに行こうとしたりします。
記憶障害により現状を忘れて昔の生活をしているつもりとなり、過去の自分自身の習慣を再現しようとするため徘徊が起こるのです。
心地よい場所を探そうとする
中核機能障害により不安やストレスが蓄積された結果、徘徊が起こる場合があります。
これまでできていたのにできなくなってしまうと「自分はなぜこんなにできなくなってしまったのか」とストレスを感じてしまいます。
また、病院に入院したり、入所する介護施設を転所したり、介護者に変更があったりなど環境に変化があった際の不安も徘徊につながるのです。
認知症徘徊が起こったときの正しい5つの対処方法
認知症徘徊が起こった際に、家族はどのように対処すればいいのでしょうか。正しい対処方法は以下の5つです。
● 優しく声をかける
● そのまま歩き徘徊に付き合う
● 理由を傾聴する
● ほかで気をそらす
● 警察に通報する
それぞれ5つの対処方法について具体的にご紹介します。
優しく声をかける
徘徊が起こった際には優しく声をかけるのが大切です。
認知症の方が徘徊してしまい、家族が居場所を把握できなくなった際には不安となるでしょう。見つかった際には安堵すると同時に「どこに行っていたの」「どこにも行かないでって言ったでしょ」など叱責したり、行動を否定したりする場合もあります。認知症の方の行動を理解するのは難しいです。
しかし、否定したり、怒られたりすると、負の感情だけが残り、家族や介護者への不信感につながってしまう可能性があります。
そのため、優しく声をかけるようにしましょう。
そのまま歩き徘徊に付き合う
そのまま歩き徘徊に付き合う方法も有効です。
徘徊を途中で止めてしまうと認知症の方にとっては目的が達成されません。そのため、数分後、数時間後に再度徘徊をしてしまう可能性があります。
そのまま歩き徘徊に付き合うと、徘徊の目的を達成でき、また運動の機会となるため疲れて徘徊しなくなるでしょう。
理由を傾聴する
優しく声をかけるのと同様に、理由を傾聴する方法も有効です。
「家に早く帰らないといけない」「子どもが帰ってくるから早くご飯を作らないといけない」と考え差し迫った必要を感じて徘徊している場合もあります。
居ても立っても居られない状況にさらされています。
なぜ歩いているのか理由を尋ね、認知症の方に寄り添ってみましょう。理由を傾聴するだけで、安心したり、納得したりすると徘徊をやめる場合があります。
ほかで気をそらす
徘徊している理由はさまざまです。しかし認知症の方にとっては家に帰る、子どもを迎えに行くなどの目的があります。
ほかで気をそらすと徘徊する理由を忘れ行動が落ち着く場合があります。また「お迎えがくるまでお茶を飲みませんか?」「外は寒いから上着を着ましょう」など別の行為につなげるのも効果的です。
警察に通報する
徘徊は危険です。徘徊するとひとりで外に出ているときに事故にあったり、戻ってこられなくなり真夏であれば熱中症・脱水となったり、真冬であれば低体温症となったりするなどの危険があります。
徘徊に気づいた際にはすぐに対応しなければなりません。場合によっては、警察に通報し捜索を依頼するのも必要です。
認知症の方の介護が不安になったら、介護施設への入居を検討してみるという手もあります。
ケアスル介護なら、認知症の度合いや年齢、予算に合わせてあなたに合った介護施設を探すことが可能です。
問い合わせフォームから簡単に相談可能ですので、ぜひ一度相談してみてはいかがでしょうか。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
家族の介護負担を軽減できる具体的な徘徊の予防策
認知症の方の徘徊は本人だけではなく、介護を担う家族にも大きな負担となります。予防策を取り入れると負担を軽減できる可能性があります。予防策は以下の4つです。
● 適度な運動をする
● 趣味活動や仕事をする
● デイサービスなどの介護サービスを利用する
● 自治体のサービスを利用する
家族の介護負担を軽減できる4つの予防策について具体的にご紹介します。
適度な運動をする
適度な運動が徘徊の予防に有効です。
夜間の徘徊は、家族にとって負担が大きくなります。家族が仕事をしていたり、子育てをしていたりする場合には、特に負担が大きいです。
日中に散歩をしたり、出かけたりするなど適度な運動を取り入れると生活のリズムが整い、満足感も得られます。夜間の睡眠につながり、家族の負担を軽減できるでしょう。
趣味活動や作業をする
趣味活動や簡単な作業などの役割を与えるのも有効です。
何もなく、ぼーっと過ごしていると、認知症の方だけではなくても、動き出したくなるものです。認知症の方は現状が理解できないため、焦燥感にかられます。
以前にしていた趣味活動を生活の中で取り入れたり、簡単な仕事を与えたりすると自己肯定感が満たされ、行動が落ち着きます。
デイサービスなどの介護サービスを利用する
デイサービスを利用すると日中の活動量を確保できます。デイサービスに通っている日中だけでも介護から離れられるため、家族の介護負担を軽減でき、休息を確保できます。
ケアマネジャーに相談し、デイサービスのほかに、訪問看護や訪問介護など介護サービスの利用を検討していくと無理のない介護につながるでしょう。
自治体のサービスを活用する
居住している自治体には、認知症の徘徊に対してさまざまサービスを提供している場合があります。まずは地域包括支援センターに相談してみましょう。
特に夜間の徘徊対策は地域との協力が欠かせません。家族だけではなく、地域のサービスを利用したり、地域の住民同士で情報を共有したりすると徘徊した際にも自宅まで送ってくれる方がいるかもしれません。
家族の介護負担軽減のために、自治体のサービスの活用が大切です。
徘徊を予防できる3つのグッズを紹介
徘徊にはさまざまな対応策があります。近年では徘徊を予防できるグッズも販売されるようになりました。
● ドアセンサーを設置
● GPS装置を入れる
● 持ち物に記名する
それぞれ3つのグッズについて具体的にご紹介します。
ドアセンサーを設置
ドアセンサーを設置すると家族が外出に気づけ、徘徊を予防できる可能性があります。窓から外出する場合もあり完全に徘徊を予防できるわけではありません。しかし、ドアから徘徊してしまった場合、早期に気づけます。
玄関に鏡を置いたり、花を飾ったりするなど興味を持つものを用意すると外出行動に気づく時間稼ぎにもなるでしょう。
GPS装置を入れる
GPS装置を入れるのも有効な手段の一つです。首から下げるタイプのものや靴につけておけるタイプのものなどさまざまなGPS装置があります。認知症の方がよく身に着けるバッグやよく履く靴などを把握したうえで、入れるようにしましょう。
GPS装置があれば徘徊を追跡でき、危険を未然に防げる可能性があります。
持ち物に記名する
認知症の方は、記憶障害の状況により自分で氏名や居住地を言えません。キーホルダーや財布、衣服などの持ち物に氏名や連絡先を記名し、発見してもらいやすいようにしましょう。
記名するのは一つではなく、複数あった方が効果的です。
捜索する際には顔写真を用意したり、その日の服装などを記録しておくのも役に立ちます。
認知症徘徊について正しく知り、安全に対応しよう
認知症徘徊は、認知症の症状の一つであり、徘徊をする理由はさまざまです。徘徊をしている認知症の方にとっては、自宅に帰る、子どもを迎えに行くなど目的がある行動です。
しかし、徘徊すると家族の介護負担が大きくなるだけではなく、時には危険にさらされます。今回ご紹介した対応策やグッズを活用し、徘徊の予防や安全な対応につなげましょう。
高齢者が転んでけが、骨折をすると寝たきりとなる可能性があります。そのため、段差が高すぎないか、廊下や階段は滑りやすくないかなどを確認しておくのが大切です。詳しくはこちらをご覧ください。
認知症見守り・SOSネットワークを活用して素早く探し始められる体制を整えているところもあります。詳しくはこちらで解説しています。