高齢の家族に療養型病院への入居が必要になった場合、療養してほしいと考える方は多いでしょう。
しかし、療養期間が長くなると、心配なのがお金の面ではないでしょうか。
本記事では介護療養型施設サービスの中から、病院での療養にかかる費用の内訳と、実際の自己負担額を解説します。
自己負担額が高額になった場合の救済措置と、その手続き方法についても解説するので安心して家族の療養に努めてください。
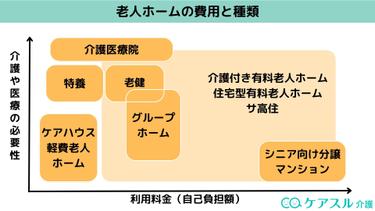
介護療養型病院の概要
介護療養型病院は、介護療養型施設サービスの中で、療養病床を有する病院に分類されます。治療が終わり、症状が慢性期になった方で療養が必要だと判断された方の療養施設です。以下の2つについて解説します。
- 利用できる対象者
- 専門のスタッフによる医療的ケアとサービス
介護サービスも受けられますが、介護施設と違い「病院に入院している」面が強い施設です。医療ケアが手厚いので、酸素吸入やインスリン投与などケアが必要な方も安心して入居できます。
利用できる対象者
療養病床を有する病院を利用できる対象者は、65歳以上かつ要介護1以上の医療的ケアが必要と判断された方が対象です。厚生労働省では下記の通り定められています。
(基本方針) 第一条の二 指定介護療養型医療施設は、長期にわたる療養を必要とする要介護者に対し、 施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他 の世話及び機能訓練その他の必要な医療を行うことにより、その者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。 引用:介護療養型医療施設(厚生労働省)
療養型の病院に入院する形になるため、症状が回復すると退去を求められる場合もあります。
専門のスタッフによる医療的ケアとサービス
療養病床を有する病院には医師が常駐しており、専門スタッフによる高度な医療ケアが受けられます。提供されているサービスは、医療ケアや生活介護、リハビリです。
経管栄養、酸素吸入、喀痰吸引、インスリン投与など、介護施設では受け入れが難しいケースもあるケア全般を受けられるのです。
介護サービスも提供しているので、排泄介助や入浴介助などの生活支援も受けられます。しかし介護施設とは違い、入院施設の面が強いので介護サービスが不十分だと感じられるかもしれません。
また高度な医療ケアに対応した介護施設をお探しの方は、ケアスル 介護で相談してみることがおすすめです。
ケアスル 介護では全国で約5万もの施設から、入居相談員がご本人様にぴったりの介護施設を紹介しています。
「幅広い選択肢から納得のいく施設を探したい」という方は、まずは無料相談をご利用ください。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
介護療養型病院での費用の内訳と自己負担額とは
医療ケアが充実していると、その分費用が心配になってしまいます。療養病床を有する病院は、居住費やサービス費用は特別養護老人ホームなどと大きくは変わりません。以下に療養型病院における費用ついて5つに分けて解説します。
- 居住費用
- 日常生活自立度により異なるサービス提供費用
- 治療内容による加算
- 介護にかかる費用
- 保険適用外の費用
- 食事代
入居一時金などは不要です。しかし、必要な医療的ケアや症状によって治療費や加算があります。費用の内訳と、実際の自己負担額について解説します。
居住費用
居住費用は介護保険適用外の自己負担です。居住費は「医療・介護を通じた居住費負担の公平化」により負担が定められています。費用の基準は水道光熱費であり、今後変更になる可能性もあるのでご注意ください。また、費用は所得に応じて違います。以下の表は居住費についてまとめています。
居住費(日額)
| 多床室 | 従来型個室 | 食費 | |
| 基準費用日額 | 370円 | 1,160円 | 1,380円 |
| 負担額(第1段階) | 0円 | 490円 | 300円 |
| 負担額(第2段階) | 370円 | 490円 | 390円 |
| 負担額(第3段階①②) | 370円 | 1,310円 | 650円 |
| 第4段階 | 377円 | 1668円 | 1360円 |
個室と多床室とがあり、個室はプライベートが保たれる分費用が高額です。また指定難病患者の方は居住費の負担が0円です。
日常生活自立度により異なるサービス提供費用
サービス費用は介護度や日常生活自立度によって変わります。寝たきりなど介助が必要になるほど費用は高額です。以下の表は介護サービス費用をまとめています。
介護サービス費用(日額(1円が10年の1割負担の場合)
| 従来型個室〈療養機能強化型A〉 | 従来型個室〈療養機能強化型B〉 | 従来型個室 | |
| 要介護1 | 618円 | 609 円 | 593円 |
| 要介護2 | 716 円 | 704円 | 685 円 |
| 要介護3 | 927 円 | 914 円 | 889 円 |
| 要介護4 | 1,017 円 | 1,001 円 | 974 円 |
| 要介護5 | 1,099 円 | 1,099 円 | 1,052円 |
※看護6:1,介護4:1の場合の基本単位
療養機能強化型Bに比べて、療養機能強化型Aのほうが、医療処置やターミナルケアを受ける方の割合が大きいです。そのため、費用も高くなる傾向です。以下の表は各種サービス加算についてまとめています。
各種サービス加算(1点が10円で1割負担の場合)
| 経口移行加算 | 280円/月 | 認知症行動・心理症状緊急対応加算※7日間が限度 | 200円/日 |
| 経口移行加算Ⅰ | 400円/月 | 低栄養リスク改善加算 | 300円/月 |
| 経口移行加算Ⅱ | 100円/月 | 口腔衛生管理体制加算 | 30円/月 |
| 療養食加算 | 6円/回 | 口腔衛生管理加算 | 90円/月 |
| 排泄支援加算 | 100円/月 | 初期加算 ※最初の30日のみ | 30円/日 |
| 認知症専門ケア加算Ⅰ | 3円/日 | 他科受診時費用※月に4回が限度 | 362円/日 |
| 認知症専門ケア加算Ⅱ | 4円/日 | 在宅復帰支援機能加算 | 10円/日 |
どのような加算がされるかは入居者の状態により違うため、医師に確認するとよいでしょう。
治療内容による加算
療養型病院における加算される治療は特定診療として加算されます。以下の表に特定診療加算についてまとめています。
特定診療加算 ※(1点が10円で1割負担の場合)
| 感染対策指導管理 | 6円/日 | 医学情報提供(Ⅰ) | 220円/回 |
| 褥瘡対策指導管理 | 6円/日 | 医学情報提供(Ⅱ) | 290円/回 |
| 初期入院(入所)診療管理
※1~2回 |
250円/回 | 理学療法(Ⅰ) | 123円/回 |
| 重度療養管理 | 125円/回 | 理学療法(Ⅱ) | 73円/回 |
| 特定施設管理 | 250円/日 | 言語聴覚療法
※1日3回が限度 |
203円/回 |
| 重症皮膚潰瘍管理指導 | 18円/日 | 集団コミュニケーション療法
※1日3回が限度 |
50円/回 |
| 薬剤管理指導
※月に4回が限度 |
350円/回 | 摂食機能療法
※月に4回が限度 |
208円/回 |
ほかに処方された薬代などが加算されます。こちらも加算されるか医師に確認すると安心です。
参照:厚生労働大臣が定める特定診療費及び特別診療費に係る指導管理等及び単位数(厚生労働省)
保険適用外の費用
療養型病院では、保険適用外の費用や雑費もかかるため注意が必要です。
入院中のテレビカード代や肌着などの日用品代が必要です。また、おむつも費用には入っていないので適宜購入しなければなりません。入院中の病衣のレンタル費用もかかります。
実際の自己負担額
療養病床を有する病院における介護療養施設の場合、介護保険が適用されるので、1~3割の自己負担で利用できます。以下の表は利用費用例(1点10円の場合)について記載しています。
※要介護2 補足給付は第2段階の場合(療養機能強化型B型の従来型個室に30日間入所)
| 日額 | 月額(30日) | |
| 居住費 | 490円 | 14,700円 |
| 食費 | 390円 | 11,700円 |
| 介護サービス費 | 704円 | 21,120円 |
| 認知症専門ケア加算Ⅰ | 3円 | 90円 |
| 初期加算(入所日から30日間のみ) | 30円 | 900円 |
| 口腔衛生管理体制加算 | ― | 900円 |
| 合計 | 1,617円 | 49,410円 |
※要介護4 経管栄養をしているほぼ寝たきりで補足給付は第2段階の場合(療養機能強化型Bの従来型個室に30日間入所)
| 日額 | 月額(30日) | |
| 居住費 | 490円 | 14,700円 |
| 介護サービス費 | 1,001円 | 30,030円 |
| 食費 | 390円 | 11,700円 |
| 排泄支援加算 | 100円 | 3000円 |
| 初期加算(入所日から30日間のみ) | 30円 | 900円 |
| 褥瘡対策指導管理Ⅰ | 6円 | 180円 |
| 重度療養管理 | 125円 | 3,750円 |
| 合計 | 2、142円 | 64,260円 |
これらに薬代、おむつなどの日用品代などを足した金額が必要費用です。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
自己負担額が高額になった場合に利用できる5つの制度
もし自己負担額が高額になり、支払えないほどの金額になったらどうしたらよいのでしょうか。国からの救済措置があります。以下の5つです。
- 国民健康保険などから支給される高額療養費制度
- 無利子で貸し付けを受けられる高額療養貸付制度
- 自治体が支払い困難と認定した際に利用できる高額療養費受領委任払い制度
- 利用料の分割払い
- ホームレスや要保護者が利用できる無料低額診療事業
ここからは救済措置の制度について、また各種手続きについて解説します。
国民健康保険から支給される高額療養費制度
療養が必要であり、かつ一定の金額以上に高額の自己負担額が発生した場合に国民保健などから支給される医療費制度です。認定される金額は、年齢や所得によって変わります。以下の表を参照してください。
70歳以上
| 区分 | 上限額 |
| 年収約1,160万円~ | 252,600円+(医療費-842,000)×1% |
| 年収約770万円~約1,160万円 | 167,400円+(医療費-558,000)×1% |
| 年収156万~約370万円 | 80,100円+(医療費-267,000)×1% |
| 年収156万円~約370万円 | 57,600円 |
| 住民税非課税世帯Ⅰ | 24,600円 |
| 住民税非課税世帯Ⅱ
※年金収入80万円以下など |
15,000円 |
参考元:厚生労働省
69歳未満
| 区分 | 上限額 |
| 年収約1,160万円~ | 252,600円+(医療費-842,000)×1% |
| 年収約770~約1,160万円 | 167,400円+(医療費-558,000)×1% |
| 年収約370~約770万円 | 80,100円+(医療費-267,000)×1% |
| ~年収約370万円 | 57,600円 |
| 住民税非課税世者 | 35,400円 |
参考元:厚生労働省
世帯ごとの上限額となるので、夫婦で療養している場合に合算して申請できるのです(同じ健康保険に加入している場合)。高額療養費制度はあとから過払い分が支給される形になるので、先に支払いを終える必要があります。立て替え払いをしたくない場合は、「健康保険限度額適用認定証」を取得すれば、最終的な自己負担額だけを支払えば済みます。
保険適用の費用に対して発生するため、差額ベッド代や食費、居住費は含まれないので注意しましょう。
無利子で貸し付けを受けられる高額療養貸付制度
健康保険限度額適用認定証を取得せず、高額療養費制度を先払いした場合は、申請してから支給まで2~3か月程かかるのば一般的です。利用される方の中には一時的に支払うのが困難な方や、すぐに支給を受けたい方もいるでしょう。
そこで、高額医療費が支給されるまで無利子で貸付を受けられる高額療養貸付制度があります。支給される費用の8割程度を借りられます。
利用できるのは国民健康保険などに加入されている方で、かつ支払先の病院から承諾を得られている方です。
申請は加入している健康保険によって違います。
- 医療機関に高額療養貸付制度利用の承諾を得る。
- 健康保険会社または役所が「保険年金課」にて貸付申請書類を交付。
- 医療機関に必要事項の記入を依頼。
- 医療機関へ限度額内を支払う。
- 保険証・貸付申請書・領収書を加入している保険会社もしくは役所に提出。
申請書は健康保険の指示にしたがって申請しましょう。
自治体が支払い困難と認定した際に利用できる高額療養費受領委任払い制度
自治体によっては「高額療養貸付制度」ではなく「高額療養受領委任払い」を取り扱っています。高額療養費受領委任払いとは、自治体が費用を病院に立て替えて支払ってくれる制度です。
利用できるのは、対象の自治体の国民健康保険に加入している方で保険料を滞納していない方です。
自治体が支払い困難と認めた場合にのみ適用されるため、貯蓄があったり所得が十分であったりする場合は認められません。高額療養費受領委任払いを申請すると高額療養費の受給対象から外れます。
申請は各自治体の役所にある「保険年金担当課」でしましょう。
利用料の分割払い
高額療養貸付制度や高額医療費受領委任払いの対象外の方で、支払いが難しい方もいるでしょう。病院によっては費用の分割払いに対応しています。分割の場合の利子も病院ごとに異なるので、まずは病院に問い合わせるとよいでしょう。
また、医療費をクレジットカード払いできる病院もあります。病院に支払う時点では一括払いを選択しますが、その後「あとから分割払い」の仕組みを利用してカードでの支払いを分割支払いに変えられる場合もあります。
分割払いだけではなく、高額になって悩んだ時は病院のソーシャルワーカーに相談してもよいでしょう。
ホームレスや要保護者が利用できる無料低額診療事業
無料低額診療事業は、全日本民主医療連合会が実施している制度です。ホームレスや要保護者、低所得者などの支払いが困難な方に無料で診療するサービスです。困窮していると認められた場合に限られます。
患者からの申し出で、事業の対象に適合しているかを検討したうえで利用できます。
また、生活が改善されるまでの一時的な制度であるため、健康保険に加入するか生活保護の受給が開始するまでの期間が対象です。
参考:医療費でお困りの方はご相談ください(無料低額診療)(全日本民主医療機関連合会)
また「難しくて実際に払う金額がよく分からない…」という方は、ケアスル 介護での相談がおすすめです。
ケアスル 介護ではご本人様の身体状況や必要となる介護サービスをお伺いしたうえで、入居にどれくらいの費用が掛かるのかもご案内します。
「分からないことを相談して安心して施設を選びたい」という方は、まずは無料相談からご利用ください。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
2024年4月からは介護療養型病院から介護医療院へ
2024年4月より介護療養病床が介護医療院へと変更となります。医療療養病床は療養型病院として残りますが、役割ははっきりと分けられます。以下に、介護医療院の特徴を2つ解説します。
- 医療ケアと生活施設を兼ね備えた介護医療院
- 療養型病院との違い
介護療養型病床が入院としての面が強く、症状が回復したら退院となるのに対して介護医療院は介護施設です。
医療ケアと生活施設を兼ね備えた介護医療院
療養型病院には医療療養病床と介護療養病床があります。どちらも慢性期の療養が必要な方の病床です。医療療養病床が療養用の施設に対し、介護療養病床は介護サービスがある点で異なっていました。
しかし近年、それぞれの施設に明確な区別がなくなり、医療病床を残して介護病床を廃止すると決定したのです。また、高齢者の長期に渡る療養の必要性や、ターミナルケアの必要性から入居施設として必要なケアが受けられる施設が新設されました。
参考:介護療養病床・介護医療院の これまでの経緯(厚生労働省)
介護療養型病院との違い
治療を目的とし、治療が終われば退院となる療養型病院。医療的ケアを受けながら、住まいとしての役割を果たすのが介護医療院です。治療をある程度終えられた方が入居します。医療機器が充実しているので、喀痰吸引や酸素吸入などの高度な医療ケアを受けられるのが特徴です。
特養(特別養護老人ホーム)などに比べると加算で高額になる場合があるので、高度な医療ケアが必要でない場合は老健(介護老人保健施設)も含め検討してもよいでしょう。
高額な自己負担額も制度の活用で軽減可能
健康保険での制度を利用すれば、自己負担額が高額になっても自己負担は軽減されます。安心して高度な治療を受けられるようなシステムになっているのです。
しかし、自分で書類を作成して申請するものも多いので、知らなければ有利な制度を適用できない可能性もあります。
病院には支払いが困難な方のためにソーシャルワーカーを設置している場合が多いので、悩んだ際は気軽に相談してはいかがでしょうか。
医師との相談の上、医療ケアが継続して必要であればほかの介護施設を検討してもよいでしょう。医師から紹介状を書いてもらえる場合があります。高度な医療ケアが必要であれば介護医療院を検討してはいかがでしょうか。詳しくはこちらをご覧ください。
基本的には医療保険の対象になる費用を対象としています。差額ベッド代やおむつ代は対象とならないのでご注意ください。民間の医療保険では差額ベッド代が賄われる場合があるので、加入している保険を確認してみるのもよいでしょう。詳しくはこちらをご覧ください。





