訪問看護、訪問介護、通い(デイサービス)、泊まり(ショートステイ)の4つのサービスを一つの事業者で利用することが出来るサービスに看護小規模多機能型居宅介護があります。
似ているサービスに小規模多機能型居宅介護がありますが、看護小規模多機能型居宅介護は訪問看護が加わったサービスとなります。同じ事業者であれば月額費用を払えばどのサービスをどれだけ使ったも同額なのであらゆる組み合わせのサービスを利用することが出来ます。
制度のシンプルさや料金体系などからメリットが多いと言われている看護小規模多機能型居宅介護ですが、デメリットはあるのでしょうか。
本記事では、看護小規模多機能型居宅介護のデメリットからメリット、向いている人まで詳しく紹介していきます。
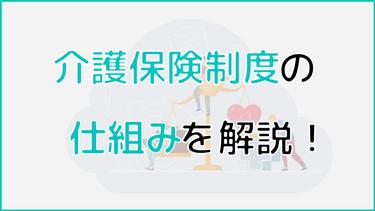
看護小規模多機能型居宅介護のデメリットは?
看護小規模多機能型居宅介護のデメリットは以下の5つです。
- 利用人数に上限がある
- 狭いコミュニティに適応しないといけない
- 事業所のある市区町村に住んでいる方しか利用できない
- 小規模多機能型居宅介護と比較すると料金が高い
- 人数によっては継続利用ができない
それぞれのデメリットについて紹介していきます。
利用人数に上限がある
看護小規模多機能型居宅介護のデメリットの一つ目は利用人数に上限があることです。
というのも、小規模という名前の通り看護小規模多機能型居宅介護は定員が定めれており登録定員は最大で29名、通いサービスは最大18人、宿泊サービスは最大9人までと定められています。
したがって、利用登録する際に定員に達しているとそもそも利用することが出来ない可能性がある点や、通いサービス・宿泊サービスも定員が定められているため毎日同じサービスを利用し続けることが出来ないのが一般的です。
したがって、定員によって登録が出来ない可能性がある点や継続的に同じ介護サービスを利用することが出来ない可能性がある点が看護小規模多機能型居宅介護のデメリットであると言えるでしょう。
狭いコミュニティに適応しないといけない
看護小規模多機能型居宅介護のデメリットの2つ目は狭いコミュニティに適応しないといけない点です。
というのも、看護小規模多機能型居宅介護は上述したように定員が定められているので少人数のコミュニティとなる点や看護師や介護士も同じ方が担当となる可能性が高いので、どうしてもコミュニティが狭くなります。
良好な人間関係を築くことが出来れば大きなメリットとなりますが、人間関係構築が難しい方や認知症などで対人関係を築くのが難しいという方にとっては利用が難しくなるかもしれません。
事業所のある市区町村に住んでいる方しか利用できない
看護小規模多機能型居宅介護は地域密着型介護サービスと呼ばれる枠組みの介護サービスのため、事業所のある市区町村に住民票がある方しか利用することはできません。
地域密着型サービスとは、今後増加が見込まれる認知症高齢者や中重度の高齢者の方が住み慣れた地域で生活を続けることが出来るように、市区町村が指定した事業者が地域住民に提供しているサービスのことを指します。
グループホームなども地域密着型サービスに含まれ、看護小規模多機能型居宅介護も要介護1以上で住民票が同じ自治体にある方しか利用することが出来ないというルールがあるのがデメリットと言えるでしょう。
小規模多機能型居宅介護と比較すると料金が高い
看護小規模多機能型居宅介護は訪問看護サービスが付帯しているため、小規模多機能型居宅介護と比較すると料金が高くなっているのもデメリットとして挙げられるでしょう。
看護小規模多機能型居宅介護の料金体系としては、以下の基本料金に加えて事業者ごとの人員配置や提供サービスに応じて加算されるサービス加算、そして食費などの自己負担額があります。
看護小規模多機能型居宅介護の基本料金は以下の通りです。
| 介護区分 | 同一建物以外に居住の場合(1ヶ月につき) | 同一建物に居住の場合(1ヶ月につき) |
|---|---|---|
| 要介護度1 | 12,401円(12,401単位) | 11,173円(11,173単位) |
| 要介護度2 | 17,352円(17,352単位) | 15,634円(15,634単位) |
| 要介護度3 | 24,392円(24,392単位) | 21,977円(21,977単位) |
| 要介護度4 | 27,665円(27,665単位) | 24,926円(24,926単位) |
| 要介護度5 | 31,293円(31,293単位) | 28,195円(28,195単位) |
出典:厚生労働省「看護小規模多機能型居宅介護の報酬・基準について」
※1単位10円、介護保険の自己負担割合を1割として計算しています。
一方で、小規模多機能型居宅介護の基本料金は以下の通りとなってます。
| 同一建物以外に居住の場合(1ヶ月につき) | 同一建物に居住の場合(1ヶ月につき) | |
|---|---|---|
| 要支援1 | 3418円(3418単位) | 3080円(3080単位) |
| 要支援2 | 6908円(6908単位) | 6224円(6224単位) |
| 要介護1 | 10364円(10364単位) | 9338円(9338単位) |
| 要介護2 | 15232円(15232単位) | 13724円(13724単位) |
| 要介護3 | 22157円(22157単位) | 19963円(19963単位) |
| 要介護4 | 24454円(24454単位) | 22033円(22033単位) |
| 要介護5 | 26964円(26964単位) | 24295円(24295単位) |
出典:厚生労働省「小規模多機能型居宅介護」
※1単位10円、介護保険の自己負担割合を1割として計算しています。
金額を比較すると、小規模多機能型居宅介護よりも看護小規模多機能型居宅介護の方が3000円ほど高いことがわかります。そのため、訪問看護が必要ないという方は小規模多機能型居宅介護を利用するのも一つの手と言えるでしょう。
看護小規模多機能型居宅介護のメリット
看護小規模多機能型居宅介護のメリットは以下の5つとなります。
- 利用者の体調や家族の状況に合わせて利用できる
- 顔なじみの職員が対応してくれる
- 利用手続きが一回で良い
- 高額な初期費用が掛からない
- 看護職員による訪問看護にも対応
それぞれのメリットについて解説していきます。
利用者の体調や家族の状況に合わせて利用できる
看護小規模多機能型居宅介護のメリットの1つ目は、利用者の体調やk族の状況に合わせてサービスを組み合わせて利用することが出来る点です。
看護小規模多機能型居宅介護は上述したように訪問看護、訪問介護、通い、泊まりを組み合わせて利用することが出来、利用者や家族状況に合わせて柔軟に変更することが出来ます。
例えば、家族が普段の介護のレスパイト(休息)として一時的にショートステイを利用することや、冠婚葬祭などの急用でショートステイを利用するなども可能となっています。
そのため、看護小規模多機能型居宅介護では利用者の体調や家族の状況に合わせて柔軟にサービスを変更することが出来るのがメリットと言えるでしょう。
顔なじみの職員が対応してくれる
看護小規模多機能型居宅介護のメリットの2つ目は、顔なじみの職員が対応してくれる点です。
というのも、看護小規模多機能型居宅介護は利用者だけではなく職員も少人数で決まった方が毎回対応してくれるので、認知機能が低下している方や人見知りの利用者の方でも安心して利用することが出来ます。
したがって、看護小規模多機能型居宅介護は顔なじみで良く知った方が対応してくれるのがメリットと言えるでしょう。
利用手続きが一回で良い
看護小規模多機能型居宅介護は登録手続きをする一回だけで様々な介護サービスを利用することが出来るので手続きがラクというメリットがあります。
通常デイサービスやショートステイ、訪問看護、訪問介護はそれぞれの事業者に対して利用手続きをしなくてはなりませんが、看護小規模多機能型居宅介護は登録時の一回の手続きで完結するので利用手続きがシンプルな点がメリットと言えるでしょう。
普段仕事をしていて時間をあまりとることが出来ないという場合などでは利用手続きが楽なのはメリットと言えるでしょう。
高額な初期費用が掛からない
看護小規模多機能型居宅介護は高額な初期費用が掛からないのもメリットと言えるでしょう。
月額費用だけのシンプルな料金体系となるので、老人ホームに入居する際に必要な入居一時金のような高額な初期費用が掛からないのがメリットと言えるでしょう。
料金としては食事や日常生活費など自己負担額もかかりますが、計算方法も基本料金にサービス加算料金を足した介護サービス費と自己負担額というシンプルなものとなっています。
看護職員による訪問看護にも対応
看護小規模多機能型居宅介護の最大のメリットは、看護師による医療措置に対応していることです。
主治医との連携や指示書にしたがってインシュリン注射や喀痰吸引などが出来るので、自宅で医療ケアを受けながら過ごしたいという方にとってはメリットが大きいでしょう。
また、事業所によっては看取りにも対応していることあるので、自宅で看取りを行いたいという方はぜひ利用を検討してみても良いかもしれません。
看護小規模多機能型居宅介護に向いている人は?
看護小規模多機能型居宅介護に向いている人としては、以下の3つの特徴のどれかに当てはまる人と言えるでしょう。
- 柔軟な対応を求めている方
- 同じ環境、スタッフを求めている方
- 独居で医療行為が必要な方
それぞれの特徴について解説していきます。
柔軟な対応を求めている方
看護小規模多機能型居宅介護に向いている方として先ず最初に挙げられるのは、柔軟な対応を求めている方と言えるでしょう。
看護小規模多機能型居宅介護では上述したように4つのサービスを本人の状況や家族の状況に合わせて柔軟に組み合わせて利用することが出来ます。
本人だけではなく、介護をしている家族の方が普段仕事をしている方や突発的な予定が入る可能性が高い方の場合は特に向いていると言えるでしょう。
同じ環境、スタッフを求めている方
看護小規模多機能型居宅介護は同じ環境、スタッフを求めている方にも向いていると言えるでしょう。
看護小規模多機能型居宅介護はその名の通り小規模のため、利用者だけではなく看護職員・介護職員も顔なじみの方となります。
上述したように、本人が人見知りや認知機能が低下していて多くの方を覚えているのが難しいという場合は利用を検討してみても良いかもしれません。
独居で医療行為が必要な方
最後に、看護小規模多機能型居宅介護は訪問看護にも対応しているので、独居で医療行為が必要な方には向いているサービスであると言えるでしょう。
例えば、介護者が週末にだけ自宅に戻って介護をするようなケースであれば平日は訪問介護と訪問看護を利用して過ごすという選択肢もあるかもしれません。
したがって、独居で訪問看護を始め様々なサービスを求めている方は看護小規模多機能型居宅介護に向いていると言えるでしょう。
看護小規模多機能型居宅介護のデメリットのまとめ
看護小規模多機能型居宅介護のデメリットは以下の5つです。
- 利用人数に上限がある
- 狭いコミュニティに適応しないといけない
- 事業所のある市区町村に住んでいる方しか利用できない
- 小規模多機能型居宅介護と比較すると料金が高い
- 人数によっては継続利用ができない
また、同様に利用者の体調や家族の状況に合わせての利用が出来るなどのメリットも少なくないのが特徴の施設です。
小規模多機能型居宅介護とどちらの利用が良いかなども検討しながら、自分は向いているかを再度確認してみましょう。

看護小規模多機能型居宅介護のデメリットは以下の5つです。
①利用人数に上限がある
②狭いコミュニティに適応しないといけない
③事業所のある市区町村に住んでいる方しか利用できない
④小規模多機能型居宅介護と比較すると料金が高い
⑤人数によっては継続利用ができない
詳しくはこちらをご覧ください。
看護小規模多機能型居宅介護のメリットは以下の5つとなります。
①利用者の体調や家族の状況に合わせて利用できる
②顔なじみの職員が対応してくれる
③利用手続きが一回で良い
④高額な初期費用が掛からない
⑤看護職員による訪問看護にも対応
詳しくはこちらをご覧ください。






