要支援1は、要介護認定の中では1番軽度の状態ではあるものの、一部の生活動作に手助けや見守りが必要な状態とされています。また要支援2は、要支援1よりもその支援を必要とする範囲が広くなります。
要介護認定の中では軽度の認定ではあるものの、自立した状態とは認められていないため、離れて暮らしている場合、ご家族の方が不安に感じるのも無理はありません。
少しでもご本人の負担を軽減するべくヘルパーの利用を検討している方の中には、「週に何回利用できるの?」「1回の利用時間は?」といった疑問を持つ方も少なくないでしょう。
本記事では、ヘルパーの利用回数や費用、その他のサービスについて紹介します。
不安やお悩みの解消に役立てていただければ幸いです。


要支援1・要支援2のヘルパーの利用回数
本章では、ヘルパーの利用回数や制限、その理由について解説します。
利用回数の上限
要支援1は週2回、要支援2は週2~3回まで
要支援1の方のヘルパーの利用は、週に2回までと定められています。
週に3回の利用を認められるのは、要支援2の方のみです。
このような利用制限がある背景としては、2017年3月までは「介護予防訪問介護(ヘルパー)」は国が制度を決め、都道府県や政令指定都市等が管理していましたが、2017年4月から「介護予防・日常生活支援総合事業」として市区町村レベルで管理する形に移行したことがあります。
それ以前はほかの介護保険サービスと同様に、区分支給限度基準額で定められた範囲内であれば人によって週の回数は決めることが出来ていましたが、現在は市町村ごとにルールを決めており、多くの自治体で要支援1のヘルパーの利用は週に2回までとされ、要支援2は週に3回までが認められています。
例えば、荒川区の場合、週2回を超える利用は要支援2の方に限りますとの記載があり、要支援1の方は週に2回までの利用に限られていることが分かります。
出典:荒川区
ヘルパーの利用を検討する場合には、事前に自治体に確認するようにしましょう。
区分支給限度基準額により、利用を制限されるケースも
自治体による利用制限の他にも、介護保険の1か月あたりの負担限度額である「区分支給限度基準額」を超える場合に、ヘルパーの利用を制限されるケースがあります。
介護保険サービスを利用する際、要介護認定を受けた方であれば、1~3割の自己負担額で利用することができますが、その際に介護保険側が負担してくれる限度額が区分支給限度基準額となります。
要支援1・要支援2の区分支給限度基準額は、以下のように定められており、この金額の範囲内であれば1~3割の自己負担額で介護保険サービスを利用することができます。※1単位の金額は自治体ごとに異なる場合があり、表記の自己負担額は1単位=10円の場合の金額。
| 区分 | 区分支給限度額(単位) | 自己負担1割 | 自己負担2割 | 自己負担3割 |
|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | 5,032 | 5,032円 | 10,064円 | 15,096円 |
| 要支援2 | 10,531 | 10,531円 | 21,062円 | 31,593円 |
この金額を超えてしまった際には、全額自己負担でのサービス利用、もしくは利用が認められない可能性もあるため、注意しましょう。
ヘルパーの1回当たりの利用時間は?
ヘルパーを利用する際の利用時間については、明確な制限はありません。
ですが、そもそも要介護状態にま至っていない要支援1の方の訪問介護の目的は、生活援助を例にとると、掃除や洗濯、調理などの日常行為ができなくならないように“支援”することで、代行することではありません。1回の利用で長時間利用するのはあまり現実的とは言えません。
データをみると、要支援・要介護1の方の利用時間の割合としては、「30分以上1時間未満」が4割、「1時間以上1時間半未満」が2割強、「1時間半以上2時間未満」が3割程度とされていますが、利用を検討する際には、お身体の状態、生活状況に合わせて利用回数や時間を考慮することが重要です。
出典:WAM独立行政法人福祉医療機構「介護予防訪問介護について」
施設への入所を検討しているという方は、ケアスル 介護がおすすめです。ケアスル 介護なら、入居相談員にその場で条件に合った施設を教えてもらうことができるためご希望に沿った施設探しが可能です。
「プロに相談したい」という方は、ご気軽に無料相談を活用ください。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
要支援1・要支援2のヘルパーにかかる料金
前章で、区分支給限度基準額を超えた場合は全額自己負担、もしくは利用が制限される可能性もあると紹介しましたが、実際に要支援1・要支援2の方がヘルパーを利用した場合、どのぐらいの費用がかかるのでしょうか。
以下で詳しく紹介します。
ヘルパー利用時の料金例
要支援1・要支援2の方がヘルパーを利用した際の費用例を紹介します。
以下の表はサービスごとに定められた利用単価の平均値と自己負担額(1割)になります。
| サービス内容 | 単位数(全国平均) | 自己負担(1割の場合) |
|---|---|---|
| 訪問介護(生活援助)20分以上45分未満 | 約193単位 | 約205円 |
| 訪問介護(生活援助)45分以上 | 約237単位 | 約251円 |
| 身体介護 30分未満 | 約250単位 | 約265円 |
| 身体介護 30分以上 | 約396単位 | 約420円 |
例えば、訪問介護45分のヘルパーを週に1回利用した場合、1か月あたり約1,000円前後の自己負担となります。
訪問看護45分を週に2回+通所サービスを併用した場合、1か月あたり約2,000~3,000円台の自己負担となります。
ヘルパーの「一回当たりの単位数」は要支援1でも要支援2でも変わりません。ただ「区分支給限度額」は異なり、他の介護予防サービスと併用する場合は、区分支給限度基準額を超過してしまう可能性は十分にあるため、注意しながら利用するサービスや頻度を決定しましょう。
区分支給限度基準額を超えた場合、自費での利用は可能?
区分支給限度基準額を超えた場合、自費でサービスを利用することは可能と言えます。
ですが、ヘルパーのみを利用する場合は、利用回数はそれぞれ定められているため区分支給限度基準額を超える心配はあまりありません。
その他の介護保険サービスとの併用で区分支給限度基準額を超えてしまった場合は、自費であれば利用することは可能ですが、決して安くはない費用のため、なるべく区分支給限度基準額は超過しない方が良いでしょう。
要支援1・要支援2で利用できるその他のサービス
要支援1の方は、ヘルパー以外にも多くの介護保険サービスを受けることができます。
要支援1の方が利用することができる介護保険サービスは、以下の通りです。
| サービス 分類 |
名称 | 概要 |
|---|---|---|
| 訪問型 | 介護予防訪問入浴介護 | 自宅にヘルパーが訪問し、自分で行うのが困難な入浴、排せつ、食事等の介助や、調理、洗濯、掃除等の家事をサポートする |
| 介護予防訪問リハビリ | 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などの専門家が利用者の自宅に訪問し、リハビリを行う | |
| 介護予防訪問看護 | 医師の指示に基づき看護師等が利用者の自宅に訪問し、療養上のお世話や診療の補助を行う | |
| 介護予防居宅療養管理指導 | 通院が困難な利用者に対し、医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士などが利用者の自宅を訪問し療養上の管理・指導・助言を行う | |
| 通所型 | 介護予防通所リハビリ | 要介護状態になることを予防するため、老健(介護老人保健施設)・病院・診療所・介護医療院に通い、リハビリを行う |
| 介護予防通所介護(デイサービス) | 要介護状態になることを予防するため、施設に通って食事、リハビリ(自立訓練)、認知症予防のための活動を行う。 | |
| 介護予防認知症対応型通所介護 | 認知症の症状が明らかに見られる方に対し、心身機能の維持回復を目的とした専門的なケアを行う | |
| 短期入所型 | 介護予防短期入所生活介護 | 老人ホーム等に短期間入所し、入浴・排せつ・食事等の介助や機能訓練等のサービスを受けることができる |
| 介護予防短期入所療養介護 | 老健や介護医療院等の医療機関に短期間入所し、看護および医学的管理の下で介護や生活援助、医療ケア、機能訓練等のサービスを受けることができる | |
| 複合型 | 小規模多機能型居宅介護 | 利用者の選択に応じて「訪問」「通所」「宿泊」の3つを組み合わせて利用できるサービス |
| 施設型 | 有料老人ホーム | 「介護(入浴・排せつ・食事の提供)」「洗濯・掃除等の家事の供与」「健康管理」のうちいずれかひとつ以上をサービスとして提供している施設 |
| ケアハウス(自立型) | 家族の援助が難しく自立生活に不安がある人に向けた介護施設 | |
| サ高住 (サービス付き高齢者向け住宅) |
介護福祉士や社会福祉士などの職員による安否確認や生活相談サービスを受けることができる高齢者専門のバリアフリー賃貸住宅 | |
| その他 | 福祉用具の貸与・販売 | 手すりやスロープ、歩行器、歩行補助器などの福祉用具のレンタル・購入が可能 (要介護度によって対応している用具が異なり、要支援では車椅子や介護ベッドのレンタルには介護保険が適用されない) |
| 在宅改修 | 住み慣れた家で快適に過ごすことを目的に自宅をリフォームする住宅改修に関して、介護保険による一部支給を受けることができる | |
| 介護予防特定施設入居者生活介護 | 要支援認定を受けたうえで有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などに入居している方を対象とした介護サービス |
自宅にヘルパーを呼びサービスを受ける以外にも、施設に通いサービスを受ける「通所型」や、施設に1日から30日という短期間入所しサービスを受ける「短期入所型」等のサービスを受けることが可能です。
区分支給限度基準額という利用限度はあるものの、多種多様のサービスを受けることができるため、どのサービスを受けたいか検討してみるといいでしょう。
要支援1の方のケアプラン例
本章では、要支援1の方のケアプランを紹介します。
1週間当たりのサービス利用回数や費用等が分かるため、ぜひ参考にしてみてください。
ここでは、以下の方を例にケアプランを紹介します。
自宅内の移動は自力で行えているものの、腰痛やひざ関節痛が生活に支障を与えている。日常生活には支障がはないが、家族は遠方に暮らしているため、日常的な支援が困難。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00~9:00 | |||||||
| 9:00~10:00 | 通所介護 (デイサービス) |
||||||
| 10:00~11:00 | 訪問介護 | 訪問介護 | |||||
| 11:00~12:00 | |||||||
| 12:00~13:00 | |||||||
| 13:00~14:00 | |||||||
| 14:00~15:00 | |||||||
| 15:00~16:00 | |||||||
| 16:00~17:00 | |||||||
| 17:00~18:00 |
週に1回の通所リハビリと2回のヘルパー(介護予防訪問介護)を利用するというケアプランになっています。
また、上記のケアプランの場合の1か月の料金は、以下のようになります。
| 利用サービス | 利用頻度 | 利用回数/月 | 金額/回 | 金額/月 |
|---|---|---|---|---|
| 介護予防訪問介護 | 2/週 | 8 | 定額 | 23,490円 |
| 通所介護(デイサービス) | 1/週 | 4 | 定額 | 16,720円 |
| 合計 | 40,210円 | |||
| 自己負担(1割の場合) | 4,021円 | |||
出典:厚生労働省
料金については、お住いの地域や利用する事業者によって異なるため、サービスを利用する際は事前に確認するようにしましょう。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
要支援2の方のケアプラン例
本章では、要支援2の方のケアプランを紹介します。ここでは、以下の方を例にケアプランを紹介します。
娘と同居している要支援2の認定を受けた80歳男性。
ほとんど問題なく生活できるものの、足腰が衰え始め、家事に負担を感じている。
日中は娘が働きに出ているため、サポートが受けられない平日のサービス利用が主になる。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00~9:00 | ご家族からのサポート | ご家族からのサポート | |||||
| 9:00~10:00 | 介護予防通所リハビリ(デイケア) | 介護予防通所リハビリ(デイケア) | |||||
| 10:00~11:00 | |||||||
| 11:00~12:00 | |||||||
| 12:00~13:00 | |||||||
| 13:00~14:00 | 訪問介護 | 訪問介護 | |||||
| 14:00~15:00 | |||||||
| 15:00~16:00 | |||||||
| 16:00~17:00 | |||||||
| 17:00~18:00 |
主に、介護予防訪問介護もしくは介護予防通所リハビリ(デイケア)を利用するケアプランになりました。
介護予防訪問介護では、この方が負担に感じている掃除・洗濯・買い物・調理といった家事に関する支援が受けられるため、ご家族からのサポートが受けられない平日の日中の負担を軽減しながら生活できるでしょう。
また、介護予防通所リハビリは、施設に通い、身体機能の維持・回復を目的としたリハビリを受けることができるサービスになります。リハビリ以外に生活支援や見守りなども受けられるため、ご家族のいない日中に利用することで安心して生活することができるでしょう。
上記のケアプラン例の場合、毎月で必要な料金は以下のようになります。
| 利用サービス | 利用頻度 | 利用回数/月 | 金額/回 | 金額/月 |
|---|---|---|---|---|
| 介護予防訪問介護(30分以上1時間未満) | 2/週 | 8/月 | 利用回数に応じた月額制 | 23,490円 |
| 介護予防通所リハビリ(7時間以上8時間未満) | 2/週 | 8/月 | 月額制 | 36,150円 |
| 合計 | 59,640円 | |||
| 自己負担(1割の場合) | 5,964円 | |||
これらの費用はあくまでも一例であり、介護予防訪問介護は市区町村、介護予防通所リハビリは事業所やその規模、所要時間によって費用が異なるため、注意が必要です。
出典:厚生労働省「公表されている介護サービスについて」
出典:杉並区「介護予防・生活支援サービス 訪問型サービス・通所型サービスの基準」
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
要支援1・要支援2で一人暮らしすることは可能?
「親が要支援1/要支援2の認定を受けたが、一人暮らしをしているため心配」という方もいらっしゃるでしょうが、要支援1.2であれば、介護保険サービスを利用することで一人暮らしをすることは可能です。
要支援1は、自立した状態ではないものの要介護認定の中では1番軽度の判定であり、日常生活の一部に見守りや支援が必要という状態です。食事やトイレなどは基本的に1人で可能であるため、かかりきりの介護や支援をする必要はありません。そのため、前述のケアプランのように週に2回ほどサービスを利用し、ご本人の負担を軽減してあげることで、十分に一人暮らしは可能と言えるでしょう。
要支援2は、要支援1に比べると支援が必要な範囲が広がり、家事や歩行、立ち上がりなどに一部支援が必要な状態です。こちらも基本的に食事やトイレなどの基本動作は一人で行うことができるため、介護保険サービスを有効に活用することで一人暮らしは可能になります。
とはいえ、離れて暮らしていると、症状の悪化や体調の変化に気付きづらいのも事実です。こまめに電話をする、週末だけ自宅を訪ねるなどの方法で、定期的に様子を確認するようにしましょう。
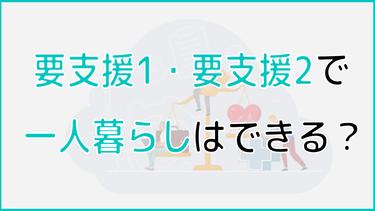
まとめ
要支援1の方のヘルパーの利用回数は週に2回まで、要支援2の方は週に2~3回までと定められています。
それ以上の回数のヘルパーを受けることはできませんが、その他の介護保険サービスと組み合わせることで、より多くサービスを受けることができます。
ですが、区分支給限度基準額という負担限度額を超過した分は、全額自己負担となってしまうため、注意が必要です。
利用するサービスを決める際には、ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談すると良いでしょう。
そのほか、要支援1について詳しく知りたいという方は、以下の記事も参考にしてみてください。
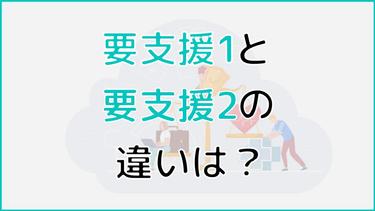
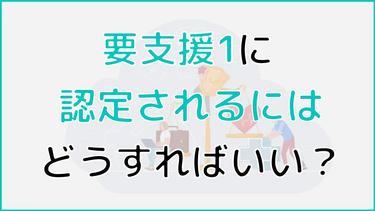
要支援1の方のヘルパーの利用回数は、週に2回まで、要支援2の方は週に2~3回までとなります。詳しくはこちらをご覧ください。
明確な制限はなく、「30分以上1時間未満利用している」という方が約4割と1番多くなっています。また、利用時間が30分増加するごとに費用も加算されていくため注意が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。





