世帯分離は、親子で同居している場合に、生計を別にするときにおこなわれることがありますが、夫婦の場合は、どちらかが施設に入っているなど別居している場合は世帯分離が認められることがあります。
世帯分離によって介護保険サービスの自己負担額が少なくなったり、公的介護施設に入所した際の費用が軽減できますが、夫婦間で世帯分離をする際はいくつか注意点があります。
そこで本記事では、夫婦間での世帯分離はできるのか、夫婦間で世帯分離をする際の注意点まで徹底解説します。
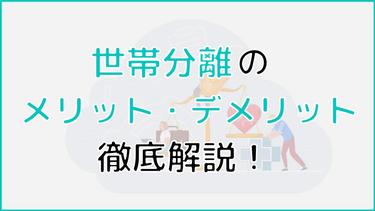
世帯分離は夫婦間でもできる?
夫婦が同じ住所で生活している場合、民法で扶助義務があるため世帯分離はできません。ただし、事実上の別居状態など同じ生計でないことが認められた場合に限り、世帯分離できることがあります。
本章では世帯分離とは何かをおさらいし、その後夫婦で世帯分離が認められる場合、認められない場合について解説します。
夫婦間でも世帯分離ができるケース
夫婦間でも世帯分離が認められるケースとしては、夫婦であっても生計を共にしていないという実態があることが認められる場合です。
例えば、高齢者は夫婦のどちらかが施設に入所している場合が対象です。夫婦のどちらかが施設に入所することで自宅に残ったもう一方の生活が安定しない場合は入所した介護施設に住民票を異動することで世帯分離ができることがあります。
ただし、前述したように世帯分離をする際は世帯主に独立した家計を営むことが前提になるので、施設に入所していないもう一方が世帯分離をしても独立して生活できない場合は生活保護の受給なども可能となります。
また、家計を別にしていなくても、DVや虐待を受けている場合など、状況によっては世帯分離ができることもあるので地域包括支援センターや役所の窓口で確認してみましょう。
夫婦間で世帯分離ができないケース
夫婦間で世帯分離をすることができないケースとしては、独立した家計を営んでいると認めることができないケースなどです。
というのも、民法では「同居、協力および扶助の義務」が定められており夫婦間は基本的にはお互いに扶養することが前提となっています。そのため、役所で申請をしても認められません。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
夫婦間で世帯分離によって変わる介護費用と注意点
夫婦間で世帯分離により、結果として世帯の所得が減り介護費用の負担軽減につながることがあります。
介護費用の負担軽減につながる要因となるのは、主に下記の3つのポイントです。
|
一方で夫婦間で世帯分離をすることにより、結果として費用負担が増えることもあるため注意が必要です。
費用負担が増える可能性とあるのは、主に下記の3つのポイントです。
|
世帯分離によって変わる介護費用と注意点に関しては、下記の記事で分かりやすく解説していますのでぜひお役立てください。
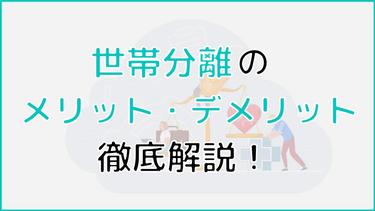
夫婦間で世帯分離をするまでの手順
夫婦間で世帯分離の手続きを行う方法は、市区町村の窓口で「世帯変更届」を提出する必要があります。
世帯変更届の提出ができるのは、本人、世帯主、または同一世帯の方となっており、本人または同一世帯員以外の方が申請する場合は委任状が必要になるので注意しましょう。
手続きについては市区町村によって手続きが異なることがありますので、詳しくは窓口で質問してみましょう。
夫婦間で世帯分離は基本的にはできない
ここまで夫婦間で世帯分離をすることによる、変化注意点について解説しましたが、いかがでしょうか。
基本的に、夫婦間での世帯分離はできません。
夫婦どちらかが施設に入居するなどして行う世帯分離は、ケースによって介護保険サービスの自己負担額が軽減される一方で、健康保険の扶養から外れた方が国民健康保険に加入しなくてはならないなど、支出の変化がありますので、注意が必要です。
夫婦間での世帯分離は、夫婦であっても家計を別で管理している場合は認められる場合もあります。ただし、基本的には民法上「協力・扶助の原則」が認められているため、互いの扶助をすることが前提とされており認められないことがほとんどです。詳しくはこちらをご覧ください。
例えば、高齢者の場合は夫婦のどちらかが施設に入所しているという場合が該当します。夫婦どちらかが施設に入所することで自宅に残ったもう一方の生活が安定しないことが考えられるので、こういったケースでは入所した介護施設に住民票を移すことで世帯分離が出来ることがあるのです。詳しくはこちらをご覧ください。





