「特養に申し込んだけれども、入所判定会議とはいったい何だろうか?」
特養(特別養護老人ホーム)は申し込み順で入所できるわけではなく、入所判定会議において優先順位が決まります。
本記事では、特養における入所判定会議とは一体何かについて詳しく解説していきます。
また、入所判定の基準がどうやって決まるか、実際の入所判定基準表を参考に説明した上で、どうすれば優先的に入所することができるのかも紹介します。

特養(特別養護老人ホーム)の入所判定会議とは?
特養(特別養護老人ホーム)の入所判定会議とは、特養への入所希望者に対して施設側が入居の可否判断ならびに入居の優先順位を決める会議です。
入所判定会議の実施は、厚生労働省が定めた「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」に記載されています。
指定介護老人福祉施設は、入所申込者の数が入所定員から入所者の数を差し引いた数を超えている場合には、介護の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、指定介護福祉施設サービスを受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させるよう努めなければならない。
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号)より抜粋
多くの特養では月1回会議が開催され、入所予定者の心身の状態や家庭環境を考慮して入所の優先順位を決定します。
この章では、特養の入所判定会議の目的、参加者、そしてどんな話し合いが行われるか順に解説していきます。
入所判定会議の目的
入所判定会議の目的は、主に下記の役割があります。
- 新規入所申込者の受付と検討
- 当該施設内の運営状況の把握
- 当該施設からの入院者の把握
- 入所待機者の優先順位の決定
入所判定会議では、入居待機者の優先順位を決めるのみならず、施設の運営状況や入院者の確認も行います。
例えば、当該施設に入所していた人が退院復帰した場合、再入所を円滑に行うためにサポートをします。
空床が発生した際に誰を優先的に入所するかを決めるためにも、施設の運営状況の把握が必要です。
入所判定会議の参加者
入所判定会議は、専門知識を有する下記のような方々によって開催されます。
- 施設職員
- 施設長
- 生活相談員
- 介護支援相談員
- 看護主任
- 介護主任
- 栄養管理士
- 理学療法士
- 施設職員以外
- 居住介護支援事業所の介護支援相談員
- 保険者(市区町村)の担当職員
- 第三者としての立場を有するもの(地域住民団体の代表者など)
厚生労働省が提示した「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について」において、入所を判定する会議では介護スタッフや看護スタッフの代表者など、現場で作業している職員の参加も推奨しています。
また、施設職員外の参加者として、当該施設の評議員のうち地域代表として加わっている者や、福祉サービスに関する苦情解決の担当者を選任すると良いともされています。
参加人数や開催要件は当該施設により異なりますが、原則月1回開催し、議長は施設長が就任します。
入所判定会議の内容
入所判定会議は、入居待機者の優先順位を決めるのみならず、施設の運営状況の把握なども行います。
特養(特別養護老人ホーム)にて入居者を決定する必要が生じた場合、入所申込書や事前の訪問面談の内容に沿って、入所する優先順位を決定します。
指定介護老人福祉施設は、入所申込者の入所に際しては、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等(法第八条第二十四項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。)の利用状況等の把握に努めなければならない。
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号)より抜粋
入所判定の基準は、上記のように本人の心身状態、生活歴、病歴、介護サービスの利用状況をもとに施設が配点を規定しています。
介護度や家庭環境の状況を踏まえて、入所希望者一人ひとりに判定点数を付けていきます。入所希望者全員の配点が完了したら、数字が高い順から名簿を作成し、点数が一番高い人から優先的に入居が決まります。
ただし、既に入所している人よりも入居予定者の介護度が重度であったとしても、施設の運営状況によっては入所ができないことがあります。
例えば部屋単位の男女別構成比や、医療や設備の関係で入所しても適切な処置ができないと判断されるケースがあります。既に入所している方々が健やかに過ごしていくためにも、入所判定会議での運営状況の把握が求められます。
入所判定の基準は、次章にて詳しく解説していきます。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
特養(特別養護老人ホーム)の入所判定の基準は何で決まる?
特養(特別養護老人ホーム)における入所判定基準は、主に3つで構成されます
- 本人の状況
- 介護者の状況
- 生活経済の状況
特養の入所判定会議では、入所希望者が提出した「入所申込書」に沿って判定点数を算出します。
この章では入所の優先順位を決める判定基準が具体的に何で構成されているか、実際の入所判定基準表を参考にしながら詳しく解説していきます。
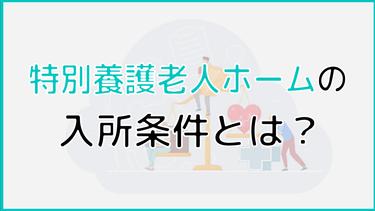
本人の状況
本人の状況について確認することは、主に下記の3つがあります。
- 要介護度の重度
- 自立しているか
- 個別に対応が必要なこと
これらの点数は、申込時に提出した入所申込書における「入所希望者本人の状態」に沿って総合的に判断されます。
特養(特別養護老人ホーム)に申込ができるのは、要介護認定で要介護1~5の判定を受けている方(原則要介護3以上)が対象です。
要介護度の数字と比例して判定点数が上がります。施設によっては、要介護2と判定を受けてからどれくらいの年月が経ったかを確認するところもあります。
入所予定者がどれくらい自立しているかは、要介護認定で使用される「認知症高齢者の生活自立度」や当該施設の基準によって決まります。こちらも認知症の進行度合いが高いほど点数が上がります。
また、入居予定者に障害や生活行動の支障がある場合も評価点数に加算されます。具体的には、下記のような症状がみられると点数が上がることがあります。
- 認知症による徘徊がみられる
- 意思の相通が困難である
- 食事のときに毎回むせてしまう
- 排せつや入浴が1人で行えない
- 移動方法は車椅子である
その他、既往歴や内服薬の有無などの、入所予定者の医療状況も確認します。施設によっては、入所前に健康診断書などの提出を求められることがあるため、入所希望先が必要な書類に漏れがないように準備しましょう。
介護者の状況
介護者の状況とは、入居希望者を介護する家族がどのような状態であるかを評価します。具体的には、当該施設の地域に住んでいるかや、日中の勤務時間などを確認します。
厚生労働省の報告によると、特養への入所申込理由で一番多いのは「介護者が高齢、障害、疾病がある(約37%)」と発表しています。その次は「介護者が就労している(約36%)」「1人暮らしで常時介護できる人がいない(約20%)」と報告しています。
参照:厚生労働省 [特別養護老人ホームの入所申込者の実態把握に関する調査研究報告書]
特養入所優先順位の介護者の評価基準として、下記のような例があります(点数や詳細は各施設により異なります)。
| 介護者の状況 | 説明 | 点数 | |
| 身寄りなし | 独居・別居を問わず、身寄り(親、配属者、子、子の配属者)がいない | 80 | |
| 実質的な介護者なし | 同居している介護者はいるが、その介護者も要介護3以上であること
同居している介護者がおらず、介護者が県外にいる |
70 | |
| 独居 | 県内に介護者がいるが、1人暮らしをしている(世帯分離は対象外) | 60
(重複可) |
20 |
| 介護者が高齢又は疾病 | 主たる介護者が70歳以上の高齢、障害者手帳を有する、病気疾病がある | 20 | |
| 介護者が就労・複数介護・育児 | 主たる介護者が週に20時間以上就労している(非正規雇用等も含む) | 20 | |
参照:北九州市 特別養護老人ホームの入所決定方法 [入所判定基準表]
表を見てわかるとおり、入居予定者に身寄りがいない(同居・別居を問わず、親族や子どもがいない)場合は、入所の判定点数が高くなります。また、主たる介護者自身も要介護認定を受けていたり、高齢で介護もままならない状態でも判定点数が上がります。
入居予定者に同居している家族や身内がいる場合は、家族がどれだけ介護に時間を充てることができかが判断されます。
例えば、専業主婦(主夫)の方がいる家族と、共働きの家族とを比べたら、共働きの方が判定点数が高くなります。日中に介護ができる専業主婦(主夫)がいる場合は、家事の大変さにかかわらず緊急度が低いとみなされるケースが多いです。
また、共働きであっても、週20時間や週40時間など普段どれだけの時間勤務しているかも優先順位を決める基準にしている施設もあります。
なお、介護者の状況については、介護の程度や認知症の状況など個人差が出る本人の状況と異なり、比較的基準が分かりやすいです。家族のお住まいや就労状況により明確に区分することができるため、上記の表よりも細かく判定基準を設けているところもあります。
生活経済の状況
生活経済の状況では、入所予定者の生活的状況や入所待機期間がどれくらいであるかを判断します。
介護サービスの利用状況の評価基準として、下記のような例があります(点数は各施設の基準により異なります)。
| 介護サービスの利用状況 | 評価項目 | 点数 |
| 在宅サービスの利用率
(過去3カ月の平均) |
80%以上 | 50 |
| 60%以上80%未満 | 39 | |
| 49%以上60%未満 | 23 | |
| 20%以上40%未満 | 17 | |
| 20%未満 | 6 | |
| 施設サービス等の利用期間
(通算) |
3年以上 | 50 |
| 2年以上3年未満 | 39 | |
| 1年以上2年未満 | 23 | |
| 6か月以上1年未満 | 17 | |
| 6か月未満 | 6 |
参照:諏訪広域連合 特別養護老人ホーム(特養)入所案内 [入所優先順位の評価基準(R2.1.1版)]
上記の表からもわかるとおり、介護サービスを利用している回数や期間が長ければ長いほど、介護の必要性が高いと判断されます。
ただし、介護サービスの利用状況については、上記のようにどれくらいの期間利用したかを基準とするところもあれば、申込時点でどこで入居待機しているか(在宅や病院など)を判断材料にする施設もあります。基本的には、在宅で介護している方が点数が高いです。
介護サービスがどれくらい受けられているか以外にも、入所申込者が住んでいる住宅状況も判断となります。
住居の状況については、下記のような例があります(点数は各施設の基準により異なります)。
| 住宅の状況 | 詳細 | 点数 |
| 住宅がない | 15 | |
| 住宅がある | 立ち退きを求められている | 12 |
| 入居希望者の居室が2階以上で、エレベータや階段昇降機がない | 10 | |
| 入居希望者の部屋がない | 8 | |
| 入居希望者の居室と同じ階に、トイレや浴槽がない | 8 | |
| 本人の行動、心理状態により、近隣から苦情がある | 12 | |
参照:大田区 特別養護老人ホームへの入所を希望される方へ [第一次評価及び第二次評価点数表]
上記の表のように、入所希望者に住宅がない(立ち退きを求められている)場合は、入所の緊急性が高いと判断されます。住宅がない場合とは、長らく医療機関に入院していて、退院が決まったけれども戻る家や頼りになる親族がいない方などが当てはまります。
また、生活行動に階段の上り下りが必要など、現在住んでいる家で介護を続けることが難しいと想定されると、特養に入居する必要性が高まります。
その他の判断基準として、入居予定者が家庭から虐待や介護放棄されているなどの事情がある場合には、判定点数に加算されます。要介護認定の判定が要介護1,2の方であっても、身内から虐待などを受けている場合は優先的に入所できることもあります。
なお、特養の入所順位の判定基準を各市区町村のホームページや当該施設のサイトに掲載しているところもあります。入居を希望している地域では、どのような判断基準で優先順位が決まるのか確認してみるのも良いでしょう。
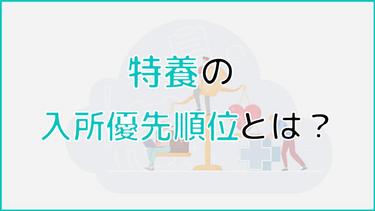
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
特養(特別養護老人ホーム)の優先順位を上げるには?
特養(特別養護老人ホーム)の入所判定会議の判定基準を踏まえたうえで、入所の優先順位を上げる方法として下記の3つが挙げられます。
- 入所の緊急性を伝える
- 介護度の変化は細かく報告
- 職員と顔なじみになり、状況を理解してもらう
特養に入所するためには、前章で解説したように様々な評価基準があります。要介護度や身寄りの有無を意図的に変えることはできませんが、、「入所判定」における優先順位を上げて、できるだけ早く入所するためには、おさえるべきポイントがあります。
この章では、特養入所の優先順位が上がる方法を、順に解説していきます。
入所の緊急性を伝える
特養(特別養護老人ホーム)の入所の緊急性が上がることにより、判定点数が上がります。
入所希望者の要介護を意図的に変えることはできませんが、例えば、介護者が働いていると、緊急性が高いと評価され、優先順位があがります。
前章でも解説したように、特養に優先的に入所するためには入居予定者の状況のみならず、介護者の就労状況も判定基準となります。
例えば、専業主婦(主夫)がいる家庭と、介護者が就労中の家庭とでは、日中の介護者が仕事で不在の家庭の方が、入所の緊急度が上がります。逆に日中介護できる専業主婦(主夫)や身内が近くにいる場合は、緊急度がそれほど高くないと判断されます。
ここで言う「就労中」とは必ずしも正社員である必要はありません。判定基準の例にもあるように、週に何十時間以上働いているかが判断基準となることが多いです。
専業主婦(主夫)がいる家庭であれば、仕事に就くことを検討するのも良いかもしれません。もちろん同時に、不在中の見守り、介護をどうするかを検討することも不可欠となります。
介護度の変化は細かく報告
特養(特別養護老人ホーム)に入所申込をした後も、入居予定者や介護者の状況が変化した際には、細かく報告することが大切です。
特養の入所申込をしても、あとは入所決定まで放置してしまう方が多いです。待機期間中に要介護度に変化があったり、認知症などの新たな症状が見られるなどの変化が生じることもあります。
基本的には入所判定会議が終わり次第連絡を入れるのが一般的であるため、入所待ち期間に「現状はいかがでしょうか?」といった特養からの問い合わせはありません。
施設によっては、要介護度や家庭環境に変化が生じた場合はご連絡を入れるよう入所申込書に記載している施設もあります。優先的に入所したいならば、こまめに連絡をすることが大切です。体調や家庭環境に変化があった場合は、必ず報告しましょう。
職員と顔なじみになる
特養(特別養護老人ホーム)の職員に顔を覚えてもらうことで、特養入所の優先順位を上げてもらえるケースがあります。
入所判定会議には、介護スタッフの代表者が参加します。利用者を受け入れる側のスタッフも、全く知らない人よりはある程度事情を知っている方の方が受け入れやすいといえます。また、利用者の在宅での状況(大変さ)をスタッフが把握していれば、入所の優先順位も上がるでしょう。
そのため、介護サービスや短期入所生活介護(ショートステイ)を行っている特養であれば、積極的に利用しましょう。介護サービスをどれくらい利用しているかは入所の判断基準につながります。特養が実施しているサービスを利用すれば、入居予定者は施設の雰囲気を体感できて、介護者も介護の負担を下げることにもつながります。
ただし、職員に顔を覚えてもらうことにもデメリットがあります。たとえば、他の入居者に迷惑をかけるなど、施設職員に対して悪い印象を与えてしまうこともあります。入所前に介護スタッフより厄介な利用者だと思われてしまうと、入所を断られてしまうケースも稀ではありますが、あるようです。
また特養(特別養護老人ホーム)への入居をお考えの方は、ケアスル介護への相談がおすすめです。ケアスル介護では全国で約5万もの施設から、入居相談員がご本人様にぴったりの介護施設を紹介しています。
「幅広い選択肢から納得のいく施設を探したい」という方は、まずは無料相談をご利用ください。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
まとめ
特養(特別養護老人ホーム)の入所判定会議では、特養への入所希望者に対して施設側が入居の可否判断ならびに入居の優先順位を決めます。
入所判定の基準は各自治体のホームページや特養のサイトにて掲示していることが多いため、気になる方は確認してみると良いでしょう。
また、判定基準を把握することにより、どうしたら優先順位を上げることができるかがわかります。もちろん、介護状態の詐称や虚偽の報告はできませんが、優先順位が上がりやすい方法がないわけではありません。

なるべく早く特養に入所したい方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
特養への入所希望者に対して施設側が入居の可否判断ならびに入居の優先順位を決める会議です。会議開催の推奨は、厚生労働省が定めた「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」に記載されています。詳しくはこちらをご覧ください。
特養(特別養護老人ホーム)における入所判定基準は、「本人の状況」「介護者の状況」「生活経済の状況」の主に3つで構成されます。詳しくはこちらをご覧ください。





