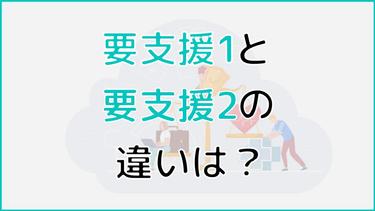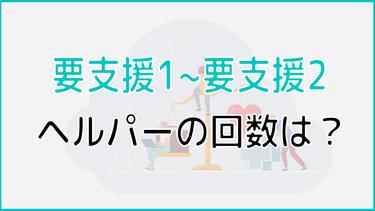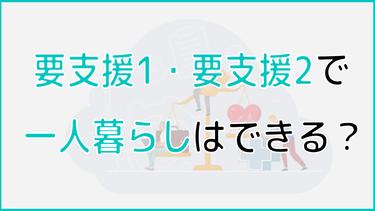高齢化社会が進む昨今では高齢の親と同居し、日常生活の支援をしている方も多くいらっしゃいます。
そんな方々の中には暮らしのなかで親に必要な介助が増えてきたため、介護サービスの利用を検討し始める方も少なくありません。
しかし介護サービスを利用したくても、「手続きやルールが難しくてよく分からない!」という人も多いでしょう。
介護保険を適用して介護サービスを受けるには、要介護認定にて最低でも「要支援1」の認定を受ける必要があります。
「うちの親はまだ比較的元気だけど、要支援1の認定を受けられるの?」
「そもそも要介護認定が難しくて、どう進めていけば良いか分からない…」
そんな疑問をお持ちの方々のため、今回は「要支援1」の認定を受けるための必要条件や要介護認定の流れ、そのほか認定を受けるために知っておきたいポイントまで詳しく解説して行きます。

要支援1に認定されるには?
要支援1に認定されるには、以下の2つの要件を満たすことが必要です。
- 立ち上がる際などに補助を必要とする状態であること
- 要介護認定を受けること
次項からそれぞれの要件について詳しく説明して行きます。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
要支援1に認定されるには?①立ち上がる際などに補助を必要とする状態であること
要支援1に認定されるための要件として1つ目は、本人が立ち上がる際などに補助を必要とする状態であることです。
食事やトイレに関しては誰かの支えがなくても1人で行えるものの、部屋の掃除や着替えといった複雑な動作での介助が必要な場合も、要支援1と判断される要件として定義されています。
また、要支援1は8段階ある要介護認定で最も軽度な症状です。
「うちの親はまだ元気だから認定は受けられないだろう…」とお思いの方も多いのですが、前述のとおり一部に介助を必要とするだけで自力で生活のほとんどのことをこなせる方も、要支援1の認定対象となり得ることを理解しておきましょう。
認定基準は厚生労働省の「要介護認定基準時間」
「立ち上がる際などに補助を必要とする状態」と定義されている要支援1ですが、厳密には1日における介護に要する時間が定められています。
厚生労働省が定めた「要介護認定基準時間」が判断の基準となっており、要支援1は介護に要する時間が1日に対して「25分以上32分未満」である判断された場合のみ認定されることになります。
それぞれの要介護認定の区分における「要介護認定基準時間」は以下の通りです。
| 区分 | 介護に要する時間 |
| 要支援1 | 25分以上32分未満 |
| 要支援2 | 32分以上50分未満 |
| 要介護1 | |
| 要介護2 | 50分以上70分未満 |
| 要介護3 | 70分以上90分未満 |
| 要介護4 | 90分以上110分未満 |
| 要介護5 | 110分以上 |
それぞれの自治体によって判断基準には違いがあるため、詳しく知りたい方はお住まいの自治体へ問い合わせてみることがをおすすめします。
以上より要支援1の認定を受けるためには、本人が立ち上がる際などに補助が必要な状態であり、1日「25分以上32分未満の介助」を要していることが必要なのです。
要支援1に認定されるには?②要介護認定を受けること
要支援1に認定されるための要件として2つ目は、要介護認定を受けることです。
要介護認定とは、自治体が審査によって本人がどの程度の介護を必要とするかを判定することを指します。
介護度は自立(非該当)、要支援1~2、要介護1~5の8区分に分類されており、数字が大きいほどに重度であることを示しています。
必要書類の提出や聞き取り調査を経て、要支援1以上の認定を受けると、介護保険を適用のうえで介護サービスが利用できることになるのです。
本章では要介護認定を受ける際の流れについて、順を追って解説して行きます。
難しければ、自治体やお近くの地域包括支援センター、居宅介護支援事業所でもサポートしてくれます。相談してみましょう。
- 必要書類の提出
- 訪問調査
- 主治医意見書の作成
- 一次判定
- 二次判定
- 認定通知
1. 必要書類の提出
まずはお住まいの市区町村にある地域包括支援センター、もしくは役所の福祉窓口に必要書類を提出しましょう。
必要書類として定められているものは、自治体によって異なる場合があるためwebサイトなどを確認しながら用意することがおすすめです。
ここでは参考例として、豊島区における必要書類を紹介します。
65歳以上の方(第1号被保険者)
- 介護保険要介護認定・要支援認定申請書
- 介護保険被保険者証(65歳の誕生日前までに郵送されている)
- 主治医の氏名・医療機関名・所在地・電話番号
- 個人番号(マイナンバーの確認ができるもの)
- 身元確認ができるもの(顔写真付きの身分証等)
介護保険要介護認定・要支援認定申請書については市町村の窓口でもらうことができますが、基本的にwebサイトからダウンロードすることも可能です。
また、本人ではなく代理人(家族や居宅介護支援事業者等)が提出する場合は、以下の書類の提出が必要になります。
- 代理権の確認ができるもの(委任状等)
- 代理人の身元が確認できるもの(顔写真付きの身分証等)
出典:豊島区
2. 訪問調査
必要書類を提出し受理されたあとは、訪問調査が行われます。
訪問調査とは、各自治体の職員や委託されたケアマネジャーなどが申請者本人の自宅を訪問し、心身の状態や介護状況、日常生活、家族や住まいの環境等について調査するというものです。
調査項目については、以下の通りです。
1. 身体機能・起居動作
- 麻痺の有無・関節の動きの制限
- 寝返りや起き上がりの可否
- 立位や座位の保持の可否
- 視力や聴力
2. 生活機能
- 移乗や移動の可否
- 食事の状況
- 排せつや排便の可否
- 歯磨きや洗顔、整髪の状況
- 衣類の着脱
3. 認知機能
- 意思の伝達の可否
- 生年月日や年齢を言えるかどうか
- 居場所を理解しているか
- 徘徊の有無
4. 精神行動障害
- 被害妄想や作り話
- ひどいもの忘れ
- 情緒不安定
- ものを破壊する
5. 社会生活への適応
- 薬の内服
- 金銭の管理
- 買い物
- 調理
- 集団行動の可否
訪問調査では、普段よりも張り切ってしまう高齢者の方も多く、調査員の方に生活の実態が正しく伝わらないこともあります。
そのようなケースを避けるためにも、訪問調査の当日は必ずご家族の方も立ち会い、調査終了後に普段の様子を伝えるなどすることがおすすめです。
3. 主治医意見書の作成
訪問調査後は、主治医意見書の作成が行われます。
訪問調査で確認した本人の心身状態について、主治医に医学的な意見を求めるために行うものです。
自治体が主治医に直接作成を依頼するため、本人やご家族が主治医に依頼する必要はありません。
なお、主治医がいない場合には、自治体が決めた医師の診断を受ける必要があるため、把握しておきましょう。
4. 一次判定
主治医意見書の作成が済んだ後は、一次判定が行われます。
一次判定とは、訪問調査時の調査結果と主治医意見書を基に、必要事項をコンピューターに入力し要介護度を決めるというものです。
5. 二次判定
一次判定の後は、二次判定が行われます。
二次判定とは、一次判定の結果や訪問調査時の調査結果、主治医意見書を基に、保険・医療・福祉の専門家が介護や支援が必要か、またどの程度必要なのかを判定するものであり、要介護度を決める最終判断の場となります。
主に訪問調査の結果や主治医意見書に記載されている特記事項を判断材料とし、コンピューターで判断することができない、より複雑で専門性の高い判定がなされます。
6. 認定通知
二次判定を行った後に、本人の要介護度が認定されます。
要介護度は8段階あり、介護度の低い方から順に要支援1・要支援2・要介護1・要介護2・要介護3・要介護4・要介護5のいずれかの認定なったと通知されることになります。
またこれら7段階に加えて判定の結果、非該当(自立)と認定されることもあり、その場合は介護保険のサービスを受けることはできませんので注意しておきましょう。
要支援1に認定されるために知っておきたいポイント
ここまでは要支援1の認定を受けるための必須要件を解説してきました。
本章では、安心して要支援1の認定を受けるために知っておきたいポイントや、心掛けておきたいことを解説して行きます。
- 要支援・要介護の状態に該当するか事前に確認する
- 訪問調査には必ず家族も立ち会う
- 判定に不服があるときは申し立てが可能
要支援1の状態に該当するか事前に確認する
要支援1の認定を受けるため知っておきたいポイントの1つ目は、要支援1の状態に該当するか事前に確認することです。
というのも要介護認定は、認定結果の通知を受けるまでおよそ1か月という決して短くない時間を要します。
それに加え、要支援や要介護ではなく、非該当(自立)と認定された場合には、介護保険サービスを利用することができないという事態になってしまいます。
したがって時間や手間の浪費を避けるためにも、要支援1に該当する状態を正しく理解し、要介護認定を受ける本人が該当するかを確認しておくことが大切と言えるでしょう。
訪問調査には必ず家族も立ち会う
要支援1の認定を受けるため知っておきたいポイントの2つ目は、訪問調査には必ず家族も立ち会うことです。
というのも要介護認定における訪問調査では、「よその人に情けない姿を見せたくない」といつもより張り切ってしまう高齢者の方も少なくありません。
そのせいで、自分でできないことを「できる」と答えてしまうこともあります。
このようなケースでは、自治体の職員に生活の実態が伝わらないため適切な認定を受けることが難しく、実際の状態より軽度の要介護度だと判断されることもあるのです。
そのため、訪問調査の際にはご家族の方が必ず立ち会い、生活の実情を伝えられることが大切であると言えます。
また訪問調査が終わり、調査員の方と2人になれるタイミングで「日常生活での本人の様子のメモを渡す」「具体的なエピソードを伝える」等の方法で伝えてみると、調査員の方も普段の様子をイメージしやすくなるかもしれません。
判定に不服があるときは申し立てが可能
要支援1の認定を受けるため知っておきたいポイントの3つ目は、要介護認定の判定に不服な場合は申し立てが可能であることです。
例えば申請時の担当窓口へ問い合わせることで、訪問調査結果や主治医意見書等の認定結果の元となった資料を閲覧することができます。
特に主治医意見書は認定結果に大きな影響を持つため、よく読んで確認しましょう。
資料を確認し、それでも認定結果に納得がいかない場合には、介護保険審査会という機関に不服申し立てを行うことができます。
要介護認定の結果に不当な点がないかを審査したうえで、申し立てが妥当なものだと判断された場合は、要介護認定の結果を取り消し、改めて審査をやり直すことになります。
ただ、認定結果の取り消しの審査に加え、もう一度要介護認定の審査を行うため、時間がかかることを覚悟する必要があるため、注意しておきましょう。
また別の方法として「区分変更申請」というものもあります。これは、身体状況や環境の変化により、現状の介護度が合わなくなったときに、要介護度の区分の変更を申請するものです。不服の申し立てよりは、よく使われる手段です。詳しくは、ケアマネジャーに相談してみましょう。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
まとめ
要支援1の認定を受けるには、以下の2つの要件を満たすことが必要です。
- 立ち上がる際などに補助を必要とする状態であること
- 要介護認定を受けること
要支援1は8段階ある要介護認定で最も軽度な症状です。
「うちの親はまだ元気だから認定は受けられないかな…」とお思いの方も多いのですが、一部立ち上がりの際などに介助を必要とするだけで自力で生活のほとんどのことをこなせる方も、要支援1の対象となり得ることを理解しておきましょう。
また要介護認定は、認定結果の通知を受けるまでおよそ1か月という決して短くない時間を要します。
時間や手間の浪費を避けるためにも、要支援1に該当する状態を正しく理解し、要介護認定を受ける本人が該当するかを確認しておくことが大切と言えるでしょう。
そのほか要介護認定における訪問調査においては、生活の実態を正しく伝えるために本人だけではなく、家族も立ち会うことがおすすめです。
必要とされる介護を安心して受けられるように、要支援1に関する状態をはじめ要介護認定について正しく理解することが大切だと言えるでしょう。
今回紹介したものの他に、要支援1について詳しく知りたいという方は、以下の記事も参考にしてみてください。